忙しくて子どもに合えないときの親の言動で注意すること
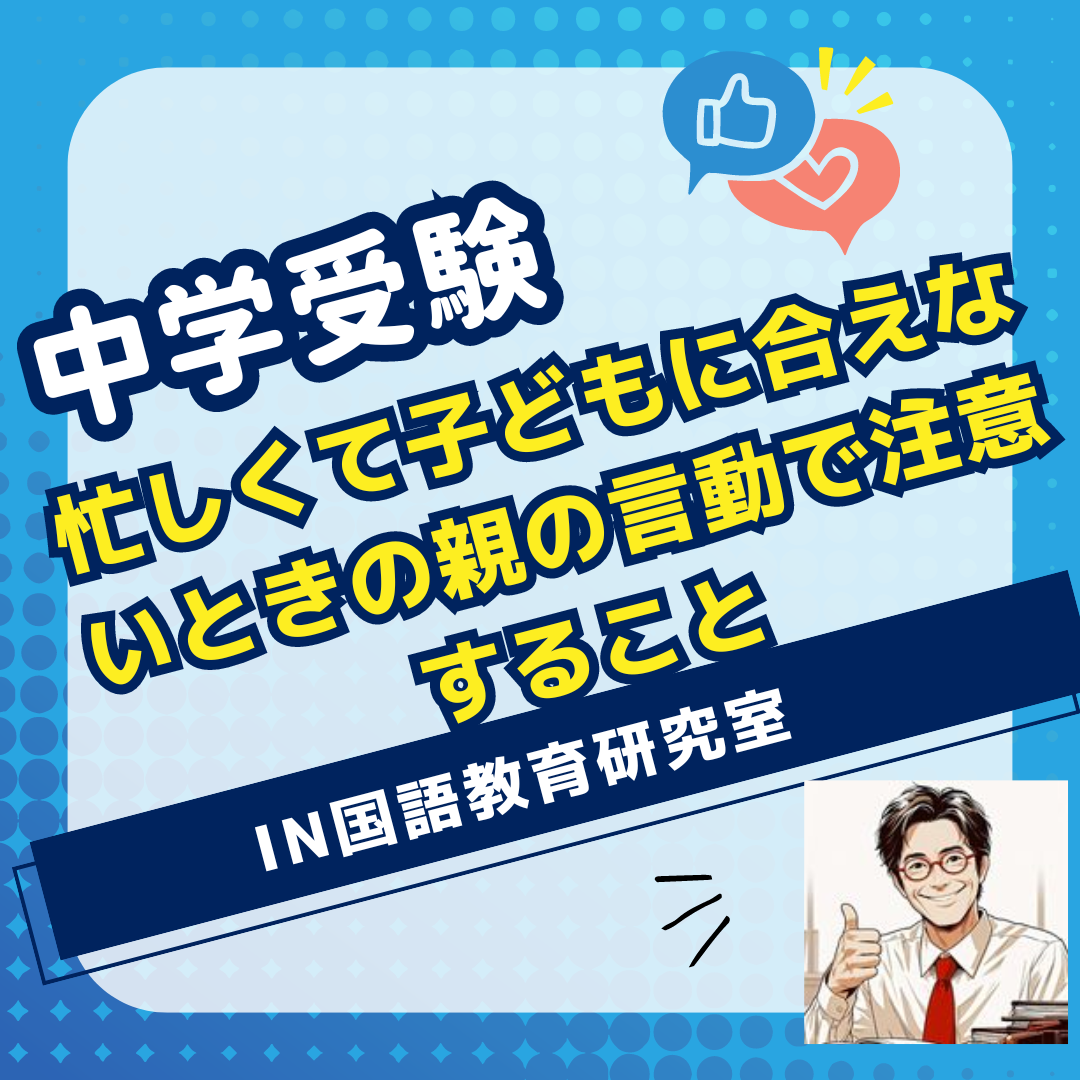
父の日が過ぎました。プレゼントや感謝の言葉をもらった方、そうでない方(日常)様々なご家庭があると思います。どんな形であれ、大切なのは日頃の感謝を伝えること。特別な日だけでなく、日常の中でも感謝の気持ちを伝えることが家族の絆を深める鍵です。日々の忙しさに追われがちですが、小さな感謝の言葉や行動が積み重なって大きな愛情となります。毎日を大切に過ごし、感謝の気持ちを忘れずに伝えていきましょう。
受験に関してどのように家族が接するかは、その家庭ごとに様々ですが以下の問題でちょっと父親、母親、もしきょうだいが見ていれば、受験生に対する接し方について考えてみてください。
【問題】忙しいときに子どもに合えないとき、父親はどんな接し方をしますか?
(1)メモやメッセージを書いて子どもが見えるところに置おく
(2)SNSやメールを送る
(3)電話する
(4)休みの日に息抜きを一緒に長時間過ごす
【答え】(3)
メラビアンの法則という第一印象についての認知度の割合があります。
視覚55%、聴覚48%、言語7%ただし、これは、「第一印象」に限っています。
家族ですので、「忙しいときという限定」で考えてみましょう。
大切なのは視覚55%、聴覚48%、言語7%とはいっても、それぞれ「笑顔(相手を安心させる)」、「声のトーン」、「伝わりやすい言葉」のどこで子どもに気持ちを伝えるかを考えてみましょう。忙しいのですからその場でできうることというのが大切です。
(1)(2)基本的に文字のみを使う場合は、「感情」は伝えにくいです。
事務的な連絡やスケジュールの確認など、一般的に感情を伴わない情報を伝える。どうしても気持ちを書きたいのならば、最後に一言「頑張っているね」くらいの添え書きや絵文字がよいでしょう。忙しいのですから。
※「がんばれ!」は「こんなに頑張っているのに…。」と子どもに誤解されることがままあります。
(3)電話は、相手の表情やしぐさなどの視覚情報が得られないです。
しかし、親が忙しいときに、ちょっとでも電話してくれるという認識を子どもが持てるかどうかです。
(その時ではなくても大人になるにつれて、いずれ気がつきます。)テレビ電話で視覚を少し補うこともできます。
(4)息抜きで対話も時間をとっているのでメラビアンの法則でいうと最も効果的です。
しかし、先述したように、メラビアンの法則はあくまでも第一印象です。
家族は「第1印象ではなく、第100万印象」です。
「家族全員が応援してくれている」
「お父さんは仕事で忙しいのに自分のことを考えてくれている」
このように子どもがちょっとでも感じていることです。
(4)は罪滅ぼしみたいになったら気まずいですね。父親の「家族サービス」は死語と認識する時代です。
■最悪な例として挙げておきます。
・日曜の夜、お父さんの時間が空いている。
・突然、家族で食事に出かけようと言い出す。
・子どもは大喜び。
・しかし、お母さんと子どもは本来、模試の解きなおしに充当する時間のはずだった。
もし、家族で食事に出かけたらば、子どもはどう考えるか?
→「ああ、お母さんとの約束は守らなくていいんだ!」
もし、家族に食事に出かけていなかったらばどうなっていたか?
→「決めたスケジュール通りに行うことは大切なんだ!」
どちらが、中学受験にとって、生活スケジュールを全うするにはよいですか?
こんなときには、お母さんがきっぱり「スケジュールをずらさない」ことを死守しましょう。
→「ありがとう。でも、今日は子どもがこれから勉強するから、別日に改めて再設定してほしい。」とお願いするのが無難です。
この言い方は「自分よし」、「相手(父・子)良し」、「家族良し」の「三方良し」です。
※お父さん、お母さんは役割は逆でも同じです。

受験期は子どもだけでなく家族全体にとって大きな挑戦です。親としては、忙しい中でも子どもの勉強や精神面を気に掛けることが重要です。具体的には、日々の声掛けや励まし、小さな成果を共に喜び、失敗を受け入れて次へのステップを共に考える姿勢が求められます。親の支えが子どもの自信とモチベーションに繋がります。子どもにとって最大の理解者であり、応援者であることを忘れずに、一緒に目標に向かって歩んでいきましょう。
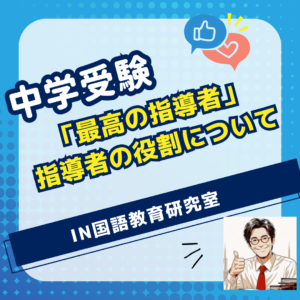

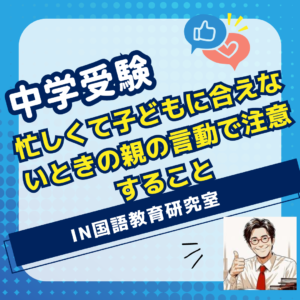





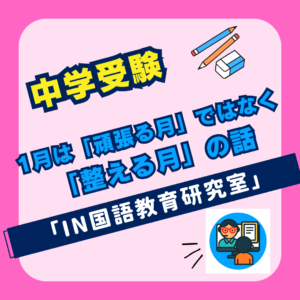
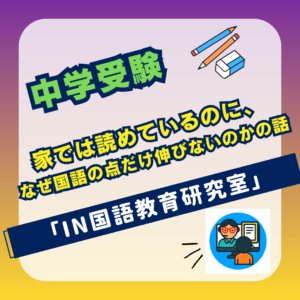
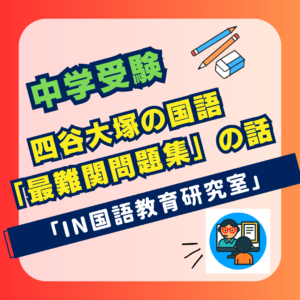

コメント