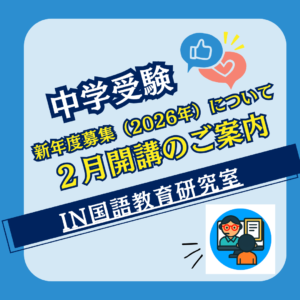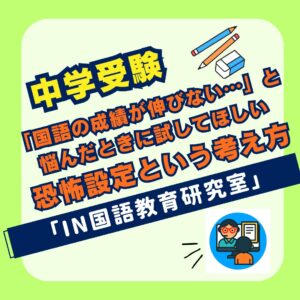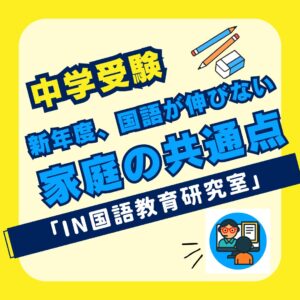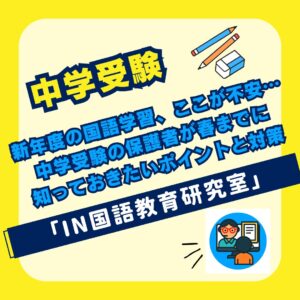解答欄が埋まらない…「書けない子」を支える親のひと言とは
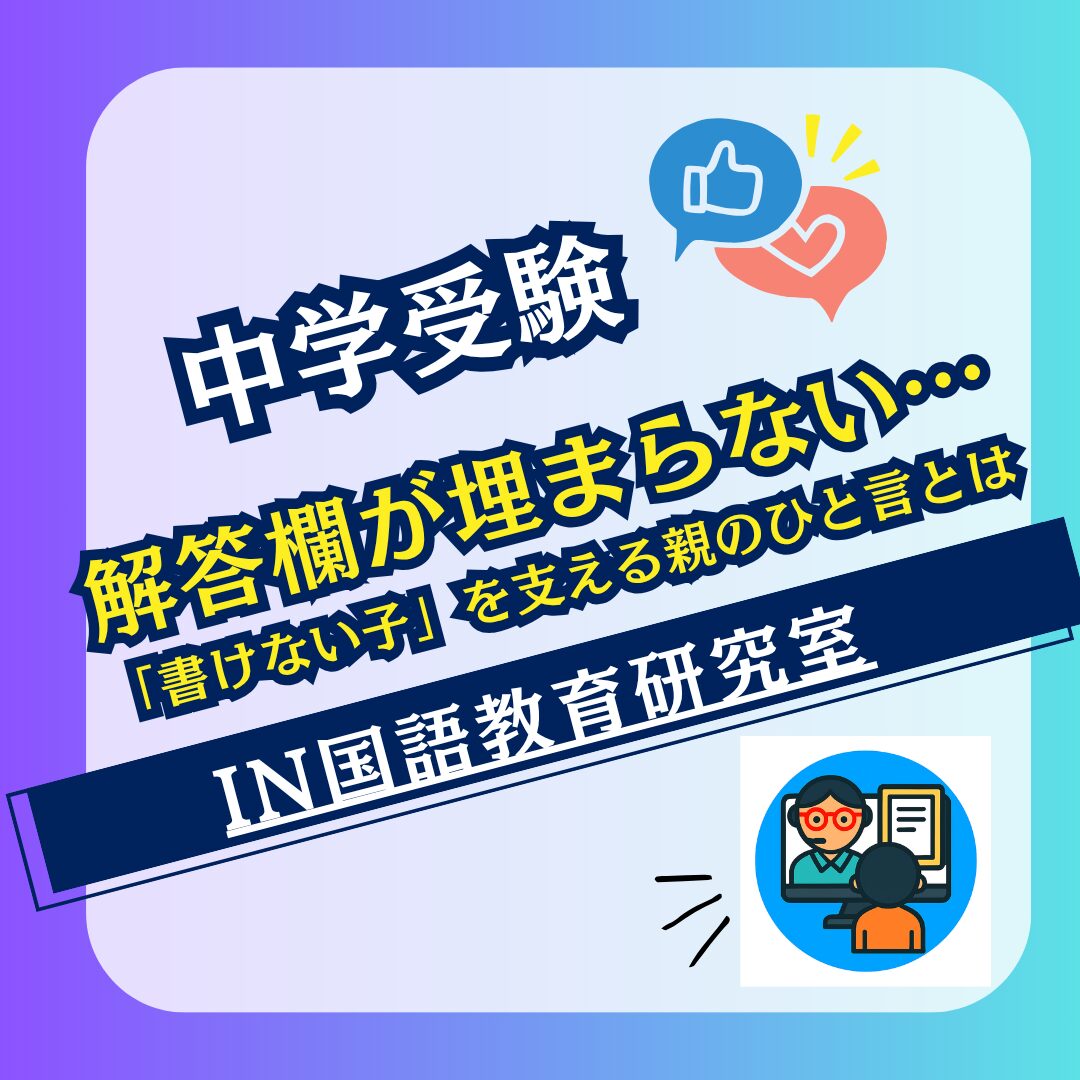
「うちの子、記述問題が苦手…」その悩みを希望に変える、魔法の言葉、知りたくありませんか?国語の記述問題、お子さんはスラスラ書けていますか?もし、顔をしかめてペンが止まってしまうなら、それは決して才能のせいではありません。「書けない」の裏側には、必ず理由があります。もしかしたら、問いを正しく理解できていないのかもしれない。頭の中にあるイメージを、言葉にする方法がわからないのかもしれない。自信がなくて、最初の一行が書けないのかもしれない。でも、大丈夫です。国語の記述が苦手なお子さんほど、ご家庭でのほんの少しの声かけで、劇的に変わる可能性があります。今回は、お子さんの「書けない」理由を紐解き、親御さんが今日から使える、魔法のような言葉をたっぷりご紹介します。「すごいね!」「面白いね!」だけじゃない、子どもの思考を刺激し、表現力を引き出す、具体的な声かけのテクニックを、事例を交えながらわかりやすく解説します。記述問題への苦手意識を克服し、「書くって楽しい!」と思えるようになる、親子のための実践的ガイドブックと思ってください。楽しさが少しでもないと継続は難しいですね。
The answer sheet won’t fill in… What parents can say to support children who ‘can’t write’.
空白の解答欄

「解答欄が真っ白で止まる」「時間がなくなるまで何も書けない」こうした書けないという悩みは、実は能力不足ではなく、「言葉にする準備が整っていない」 ことが多いのです。書くためには…。
- 内容を理解する
- 大事な部分を選ぶ
- 言葉をまとめる
- 文にして書く
という4段階が必要です。しかし、多くの子は1〜4を同時にやろうとしてパンク します。時間の制約と内容の難しさがあがるにつれて、やっつけ作業になることも、記述の解答が白紙になることもあります。
文節と単語の違い、自立語と付属語の関連性がわかると設問が読み易くなります。混乱している場合が多いのでまずは文節(○○語)、次に単語(品詞)、最後に自立語と付属語(「語」で混乱します。)
その言葉、逆効果かも…? 書けない子を追い詰める【3つのNGワード】徹底解剖
お子さんが記述問題に取り組んでいる時、つい口をついて出てしまう言葉はありませんか?良かれと思って言った言葉が、実は逆効果になっているかもしれません。ここでは、お子さんの「書けない」をさらに深刻化させてしまう、代表的なNGワードを3つご紹介します。
1.「早く書きなさい」
この言葉は、お子さんに時間的なプレッシャーを与え、焦りを生み出します。記述問題が苦手なお子さんは、すでに「書けない」という焦りを感じていることが多いもの。そこにさらに「早く」という追い打ちをかけることで、思考が停止し、ますます書けなくなってしまう可能性があります。
- なぜNG?
焦りは集中力を奪い、冷静な判断力を鈍らせます。結果として、問題文を読み違えたり、思いついたアイデアを整理できずに混乱したりする原因になります。 - どう言い換える?
「落ち着いて、ゆっくりでいいよ」「時間はあるから、焦らずにね」など、安心感を与える言葉を選びましょう。タイマーをセットするのではなく、「あと〇分くらいで終わりそうだね」と、残り時間を意識させる程度に留めるのがおすすめです。書くスピードは特に焦らせないようにすることです。あまり時短にはなりません。書く前の思考の整理に時間をかけることです。
2.「どうして埋めないの?」
白紙の解答用紙を見て、つい言ってしまうこの言葉。しかし、お子さんにとっては「書けない自分」を責められているように聞こえてしまいます。書けない理由を理解しようとせず、結果だけを求めるような言い方は、お子さんの自信を喪失させ、自己肯定感を下げてしまう可能性があります。
- なぜNG?
「埋めなければならない」という義務感だけが先行し、内容の伴わない、質の低い文章を生み出す原因になります。また、書けないことへの罪悪感から、さらに書くことを避けるようになってしまうかもしれません。 - どう言い換える?
「何が難しい?」「どこで手が止まっているの?」など、書けない原因を探る質問を投げかけましょう。具体的な問題点が見つかれば、解決策を一緒に考えることができます。
3.「わかってるなら書けるでしょ」
知識があることと、それを文章で表現できることはイコールではありません。この言葉は、お子さんの努力や苦悩を無視し、「わかっているのに書けないのは、怠けているからだ」と決めつけているように聞こえてしまいます。
- なぜNG?
お子さんは「わかっているのに書けない自分はダメだ」と感じ、自己嫌悪に陥ってしまう可能性があります。また、親に理解してもらえないと感じ、相談することをためらうようになるかもしれません。 - どう言い換える?
「わかっていることを言葉にするのは難しいよね」「一緒に言葉を探してみようか?」など、共感の言葉を伝えましょう。お子さんの知識を認めつつ、表現のサポートを申し出ることで、安心して記述問題に取り組める環境を作ることができます。
これらのNGワードは、お子さんの焦りを強め、記述問題への苦手意識をさらに悪化させてしまう可能性があります。言葉を選ぶ際には、お子さんの気持ちに寄り添い、安心感を与えることを心がけましょう。
今日から実践!お子さんの「書く力」を育む【魔法の声かけ3選】
記述問題に苦戦するお子さんを、そっと後押しする魔法の言葉。今日からすぐに使える、3つの声かけをご紹介します。これらの言葉は、お子さんの自信を引き出し、書くことへのハードルを下げ、自力で書き出す力を育みます。

1.「まずは口で説明してみて」
いきなり書くのが難しいなら、まずは話すことからスタート!話せることは、まとめられる、そして書ける。この流れが、記述問題克服への最短ルートです。これが一番大事です。イメージさせること⇒言葉にすること⇒書くことの段階をよく観察してください。
- なぜ効果的?
話すことは、思考を整理し、言葉にする練習になります。頭の中にあるイメージを、具体的な言葉で表現することで、記述問題に必要な構成力や表現力を養うことができます。 - どう実践する?
「この問題について、どんなことを知っているか教えてくれる?」「もし友達に説明するとしたら、どう話す?」など、質問形式で促してみましょう。話を聞きながら、キーワードをメモしたり、構成を一緒に考えたりするのも効果的です。話すうちに、自然と書くべき内容が見えてくるはずです。
2.「短い言葉でいいから一個だけ書こう」
最初から完璧な文章を目指す必要はありません。まずは、書くことへの抵抗感をなくすことが大切です。「1行だけ」という目標設定は、お子さんの心理的なハードルを劇的に下げてくれます。
- なぜ効果的?
「1行だけなら、何とか書けるかも」という気持ちになり、最初の一歩を踏み出しやすくなります。一度書き始めると、勢いがつき、自然と続きを書けるようになることもあります。 - どう実践する?
「この問題で一番大切なことは何かな?それを短い言葉で書いてみよう」「この文章のキーワードを一つだけ書いてみよう」など、具体的な指示を与えましょう。書けたら、「すごいね!」「よく書けたね!」と褒めて、達成感を味わわせてあげてください。
3.「続きは一緒に考えようか」
一人で悩んでいるお子さんに、そっと寄り添う姿勢が大切です。親御さんが隣にいてくれるだけで、お子さんは「書けるまでの道」を安心して歩むことができます。
- なぜ効果的?
親御さんの存在は、お子さんに安心感を与え、精神的な支えとなります。一緒に考えることで、行き詰っていた思考が整理され、新たなアイデアが生まれることもあります。 - どう実践する?
「どこで困っているの?」「どんな言葉を使えばいいか、一緒に考えてみようか?」など、優しく声をかけてみましょう。答えを教えるのではなく、ヒントを与えたり、質問を投げかけたりしながら、お子さん自身が答えを見つけられるようにサポートすることが重要です。
途中で遮るのは思考停止させてしまいます。まずは失敗でもいいから形にさせてそれを議論できるようにすることです。改善の積み重ねほど力がつきます。国語のテストのやり直しをテスト時間以上にしない家庭が多いのは残念ですが、他の教科もあるので仕方がない反面、論理的効力やPDCAサイクルが中途半端になり指示待ちになったり、やることだけが目的のこなし勉強になってしまいます。
これらの声かけは、お子さんの「書く力」を育むだけでなく、親子の絆を深める効果もあります。ぜひ、今日から実践して、お子さんの成長を応援してあげてください。
家庭でできる!お子さんの「書く力」をグングン伸ばす【4つのサポートポイント】
記述問題対策は、塾や学校だけではありません。
ご家庭でのちょっとしたサポートが、お子さんの「書く力」を大きく飛躍させる鍵となります。ここでは、今日から実践できる、効果的なサポートポイントを4つご紹介します。
1.書く前の「言語化の練習」が効果的
記述問題に取り組む前に、まずは口頭で内容を説明する練習を取り入れましょう。書くことが苦手なお子さんにとって、いきなり文章にするのはハードルが高いもの。話すことで思考を整理し、言葉にする練習は、書く力を養うための土台となります。
- なぜ効果的?
話すことで、頭の中にある情報を整理し、論理的に構成する力が養われます。また、言葉の表現力を高め、文章で表現する際の語彙力不足を解消する効果も期待できます。 - どう実践する?
問題文を読んだ後、「この問題は何について聞いているのかな?」「どんなことを書けばいいと思う?」など、質問形式で促してみましょう。お子さんの話をじっくり聞き、相槌を打ちながら、考えを深掘りしていくことが大切です。
2.本文の重要部分に線を引いて一緒に確認
記述問題の解答は、本文の内容を理解していることが前提となります。お子さんと一緒に本文を読み、重要と思われる箇所に線を引いたり、キーワードを書き出したりすることで、理解度を深めることができます。線を引かないで脳内でできる子どももいますので、親や先生と同じやり方がよいとは限りません。認知は文字、視覚、聴覚でするものですが、お子さんによって強いもので印象付けるからです。線を引きすぎている場合はいったん辞めさせる方がよいのが個人的な見解です。
- なぜ効果的?
重要箇所を明確にすることで、解答に必要な情報を効率的に見つけ出すことができます。また、本文の内容を深く理解することで、自分の言葉で表現する力を養うことができます。 - どう実践する?
「この部分が大切だと思うけど、どう思う?」「このキーワードを使って、文章を組み立ててみよう」など、お子さんと一緒に考えながら進めていきましょう。線を引く色を変えたり、キーワードを付箋に書き出したりするのも効果的です。
3.書けたら必ず「ここ良いね」と具体的にほめる
お子さんが書いた文章を読んだら、必ず具体的な箇所を褒めてあげましょう。「すごいね」「よく書けたね」といった抽象的な褒め言葉だけでなく、「この表現がわかりやすいね」「この部分の構成が良いね」など、具体的に褒めることで、お子さんの自信を高めることができます。
- なぜ効果的?
具体的に褒められることで、お子さんは自分の書いた文章のどこが良かったのかを理解し、自信を持つことができます。また、褒められた部分を意識することで、さらに良い文章を書こうという意欲が湧いてきます。 - どう実践する?
「この例えがわかりやすいね」「この部分の言葉選びが素晴らしいね」など、具体的に褒めるポイントを見つけましょう。お子さんの努力や工夫を認め、褒めることで、書くことへのモチベーションを高めることができます。
4.誤字よりも「書き出した勇気」を評価する
記述問題が苦手なお子さんにとって、書くことは大きな挑戦です。
誤字脱字や表現の稚拙さにとらわれず、まずは「書き出した勇気」を褒めてあげましょう。
- なぜ効果的?
誤字脱字を指摘ばかりすると、書くことへの抵抗感が強まってしまう可能性があります。まずは、書くこと自体を褒めることで、お子さんの自信を高め、積極的に書く姿勢を育むことが大切です。 - どう実践する?
「最後まで書ききったね、すごい!」「難しい問題に挑戦して、えらいね!」など、結果だけでなく、プロセスを褒めましょう。誤字脱字は、後から一緒に確認すれば良いのです。
書く力は、「安心」と「小さな成功」が重なることで育まれます。ご家庭での温かいサポートを通して、お子さんの「書く力」を大きく開花させてあげてください。
まとめ:解答欄の空白は、可能性の余白。

解答欄がなかなか埋まらない。それは決して、お子さんが“できない”からではありません。まるで未完成のパズルのように、知識や思考が“まだ整っていない”だけなのです。必要なのは、ピースを繋ぎ合わせるための、ほんの少しのサポート。親御さんの温かいひと言は、まるで魔法の杖。お子さんの心に火を灯し、「書けない自分」から「書ける自分」へと、劇的な変化をもたらすきっかけとなります。今日から、難しく考える必要はありません。特別な教材も、高度なテクニックも必要ありません「まず口で言ってみようか」このたった一言を、そっとお子さんに添えてあげてください。その一言が、お子さんの眠れる才能を呼び覚まし、自信に満ちた未来へと導く、最初の一歩となるでしょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。