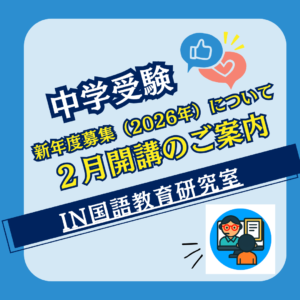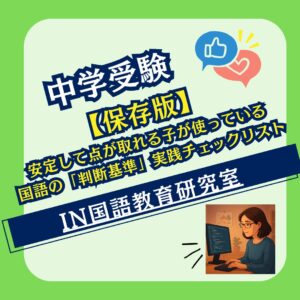11月の過ごし方:国語のリズムを整える1か月

11月は、中学受験国語にとって静かに伸びる時期です。焦る必要はありません。この時期は、知識のインプットよりも「読むリズム」と「思考の安定」をつくる月です。短時間でも毎日「読む・考える・書く」を回すことで、12月からの演習期にスムーズに移れます。
How to Spend November: A Month to Get the Rhythm of Japanese Language Right
学年別のポイント

🟦小4:読む楽しさを保ちながら、言葉にする力を育てる
・1冊の本を深く読む
・読後に「どんな気持ちになった?」を親子で話す
・自分の感じたことを3行でメモしてみる
→「言葉にする習慣」をつけると、読解の芽が自然に伸びます。
1. バラエティ豊かな読書体験を
- ジャンルを広げる:
物語だけでなく、伝記、科学読み物、歴史漫画など、様々なジャンルの本に触れさせ、興味の幅を広げましょう。 - シリーズものを活用
好きなシリーズを見つけると、継続して読む習慣がつきやすくなります。 - 図書館や書店を積極的に利用
新しい本との出会いを促し、自分で選ぶ楽しさを体験させましょう。 - オーディオブックの活用
移動中や寝る前に聞くことで、読書時間を増やし、活字を読むのが苦手な子にも有効です。
2. 「言葉にする」をサポートする具体的な質問
- 気持ちを深掘りする質問:
- 「本のどの部分が一番心に残った?それはなぜ?」
- 「もし自分が主人公だったら、どうすると思う?」
- 「この本を読んで、何か新しい発見はあった?」
- 「この本のテーマは何だと思う?」
- 物語の構造を意識させる質問:
- 「物語の始まりはどうだった?どんなことが起きた?」
- 「物語の中で一番盛り上がった場面はどこ?」
- 「物語の結末はどうだった?どうしてそう終わったんだと思う?」
- 「登場人物の中で誰が一番好き?その理由は?」
- 日常生活との関連付け:
- 「この本の内容と似たような経験をしたことはある?」
- 「この本を読んで、これから何かやってみたいことはある?」
3. アウトプットのバリエーションを増やす
- 3行メモからステップアップ:
- 3行日記:
その日の出来事と本の感想を組み合わせて書く。 - 読書ノート
本のタイトル、作者、あらすじ、感想などを記録する。 - 本の紹介文
友達に勧めるつもりで、本の魅力を伝える文章を書く。
- 3行日記:
- 創造的なアウトプット
- 絵を描く
本の印象的な場面や登場人物を描く。落書きでも構いません。 - 劇をする
本の一場面を演じる。頭の中で行う子どもが過去にいました。 - 作文を書く
本を読んで考えたことや感じたことをテーマに作文を書く。
- 絵を描く
- 家族以外との共有
- 学校の読書感想文コンクールに応募する。(将来的に次年度分を意識する)
- 図書館の「おすすめの本」コーナーに紹介文を投稿する。
4. 親子で楽しむ読書会
- テーマを決めて本を選ぶ
例えば、「冒険」や「友情」など、テーマを決めて、それぞれが本を選んで読み、感想を共有する。 - 役割分担をする
朗読、感想発表、質問など、それぞれが役割を分担して参加する。 - おやつを用意する/水分補給をする
リラックスした雰囲気で読書会を楽しめるように、おやつを用意する。
5. 焦らず、褒めて伸ばす
- 完璧な感想を求めない
どんな感想でも、まずは褒めて認め、肯定的なフィードバックを与えましょう。 - 言葉にするのが苦手な場合は、絵や図を使って表現するのもOKです
無理に言葉で表現させようとせず、様々な表現方法を認めましょう。 - 読書自体を嫌いにさせないように注意する
強制的な読書や感想文の強要は避け、読書の楽しさを損なわないように配慮しましょう。
ポイントは、読書を「楽しい体験」として捉え、言葉にする練習を「苦痛な作業」にしないことです。 根気強く、様々な方法を試しながら、お子様に合ったやり方を見つけてあげてください。
🟩小5:設問意識と語彙力を鍛える
・説明文を読むとき、「筆者の考え」と「理由」を線で結ぶ
・わからない言葉を“自分の言葉”で言い換えてみる
・「なぜその設問が出たのか」を考える
→ 問いの裏にある意図を考えられる子が、6年で記述が強くなります。
1. 設問意識を育てるための工夫
- 問題作成者の視点を取り入れる
- 「もし自分がテストを作る先生だったら、どんな問題を出すだろう?」という視点を持たせる。
- 教科書の重要箇所や、授業で強調された部分を意識させる。
- 設問の種類を意識する
- 「要約問題」「理由説明問題」「心情理解問題」など、設問の種類によって解答のポイントが異なることを理解させる。
- それぞれの設問形式に合わせた練習問題を解く。
- 「なぜ?」を深掘りする習慣
- 正解・不正解に関わらず、「なぜそうなるのか?」を徹底的に考えさせる。
- 解説を読んで終わりにするのではなく、自分で説明できるまで理解を深める。
- 間違いから学ぶ
- 間違えた問題を放置せず、原因を分析する(知識不足、読解力不足、設問の意図の誤解など)。
- 同じ間違いを繰り返さないように、ノートに記録したり、復習したりする。
2. 語彙力を効果的に増やす
- 言葉の「つながり」を意識する
- 類義語、対義語、関連語などをまとめて覚える。
- 言葉の意味だけでなく、使い方やニュアンスも理解する。
- 五感をフル活用する:
- 言葉を声に出して読む、書く、聞く。
- 言葉からイメージを膨らませる(絵を描いたり、物語を作ったりする)。
- 日常生活で積極的に使う
- 新しい言葉を会話や文章の中で意識的に使う。
- 家族や友達と「語彙力ゲーム」をする。
- 辞書や類語辞典を積極的に活用する
- わからない言葉はすぐに調べる習慣をつける。
- 類語辞典を使って、表現の幅を広げる。
3. 説明文読解をレベルアップ
- 構造を意識する
- 「はじめ」「なか」「おわり」の構成を意識し、それぞれの役割を理解する。
- 段落ごとに要約し、文章全体の流れを把握する。
- キーワードを見つける
- 重要な言葉やフレーズに線を引いたり、メモを取ったりする。
- キーワード同士の関係性を理解する。* 図やグラフを読み解く:
- 図やグラフが文章の内容をどのように補足しているかを理解する。
- 図やグラフから読み取れる情報を文章にまとめる練習をする。
- 批判的に読む
- 筆者の主張は正しいか、根拠は十分か、別の視点はないかなどを考える。
- 複数の情報源を参照し、多角的に理解する。
4. アウトプットの機会を増やす
- 要約練習
- 文章全体、段落ごとに要約する練習をする。
- 字数制限を設けて、簡潔にまとめる力を養う。
- 説明文を書く練習
- 身の回りの物事や現象について、説明文を書く練習をする。
- 図やグラフを使って、視覚的にわかりやすく表現する。
- ディスカッション
- 説明文の内容について、家族や友達と意見交換をする。
- 自分の考えを論理的に説明する練習をする。
5. 焦らず、継続することが大切
- スモールステップで進む
- いきなり難しい問題に挑戦するのではなく、基礎的な問題から徐々にレベルアップする。
- 毎日コツコツと続ける
- 短時間でも良いので、毎日継続することが大切。
- 成功体験を積み重ねる
- 小さな目標を達成するたびに褒めて、自信を持たせる。
ポイントは、設問意識と語彙力を「知識」として詰め込むのではなく、「スキル」として身につけさせることです。 積極的にアウトプットの機会を作り、実践を通して理解を深めることが重要です。
🟥小6:過去問分析の精度を上げる
1. 「読みのズレ」を徹底的に分析する
- 具体的なズレの種類を特定する
- 事実誤認: 本文に書かれていない情報を読み込んでしまう。
- 主観的な解釈: 自分の考えや感情を優先して解釈してしまう。
- キーワードの見落とし: 重要な言葉やフレーズを見落としてしまう。
- 文脈の無視: 前後の文脈を考慮せずに、部分的な意味だけで判断してしまう。
- ズレの原因を深掘りする
- 語彙力不足: 意味のわからない言葉が多すぎる。
- 読解力不足: 文構造を理解できていない。
- 集中力不足: 注意散漫で、読み飛ばしてしまう。
- 先入観: 自分の知識や経験にとらわれてしまう。
- ズレを記録するフォーマットを作る
- 問題番号、設問内容、自分の解答、正答、ズレの種類、ズレの原因、対策などを記録する表を作成する。
- 記録を分析し、自分の弱点を把握する。直接の書き込みでも構いません。やり方を思い出すことです。
2. 「根拠のある読み」を強化する
- 傍線部や指示語に注目する
- 傍線部が何を問うているのか、指示語が何を指しているのかを正確に把握する。
- 傍線部や指示語の周辺に、解答の根拠となる情報が隠されていることが多い。
- キーワードを意識する
- 文章全体を通して、重要なキーワードを特定する。
- キーワード同士の関係性を理解することで、文章全体の意味を把握しやすくなる。
- 消去法を活用する
- 選択肢の中で、明らかに誤っているものから消去していく。
- 残った選択肢の中から、最も根拠のあるものを選ぶ。
- 「なぜそう言えるのか?」を自問自答する
- 自分の解答に自信が持てない場合は、「なぜそう言えるのか?」を自問自答する。
- 根拠を明確に説明できるまで、解答を吟味する。
3. 志望校の「文の型」をマスターする
- 過去問を徹底的に分析する
- 過去問を複数年分解き、解答パターンを分析する。
- どのような構成で、どのような言葉遣いで解答すれば良いのかを把握する。
- 模範解答を参考にする
- 模範解答を参考に、自分の解答を修正する。
- 模範解答の構成や言葉遣いを真似ることで、合格答案の書き方を学ぶ。
- 添削指導を受ける
- 先生や塾の講師に添削指導を受け、客観的なアドバイスをもらう。
- 自分の弱点を指摘してもらい、改善点を見つける。
- 「型」を意識しながら、オリジナルの解答を作る
- 模範解答を丸暗記するのではなく、「型」を理解した上で、自分の言葉で解答する。
- オリジナリティのある解答は、採点者に好印象を与える。
4. 「解く→直す→気づく」ループを加速させる
- 時間配分を意識する
- 過去問を解く際に、時間配分を意識する。
- 時間内に解き終わるように、スピードと正確性を高める。
- 復習ノートを作る
- 間違えた問題や、理解が曖昧な箇所を復習ノートにまとめる。
- 復習ノートを定期的に見直し、知識の定着を図る。
- 弱点克服に集中する
- 過去問分析で明らかになった弱点を克服するために、集中的に学習する。
- 苦手な分野の問題を繰り返し解き、克服する。
- メンタル面を強化する
- 本番で力を発揮できるように、メンタル面を強化する。
- 緊張を和らげる方法や、集中力を高める方法を身につける。
5. 12月以降も継続する
- 11月は基礎固めの時期と捉え、12月以降も過去問分析を継続する。
- 直前期は、時間配分や解答スピードを意識した実践的な練習を行う。
※ 体調管理に気を配り、万全の状態で本番に臨む。
ポイントは、過去問分析を単なる問題演習で終わらせず、自分の弱点を克服し、合格力を高めるための戦略的なプロセスとして捉えることです。 徹底的な分析と改善を繰り返すことで、着実に合格に近づくことができます。
・点数よりも、「読みのズレ」をメモする
・根拠のある読みを意識する
・志望校の出題傾向に合わせた“文の型”を意識して書く
→ 11月は、「解く→直す→気づく」のループを確立する月です。体調に留意し、生活リズムが崩れていないか親子で確認しましょう。また、学習で教科・単元によっては行き詰る場合があります。過去の例でよかったこととしては行き詰ったらいったん切り上げて、塾や家庭教師の先生に相談することです。
12月へのつなぎ方
冬期講習が始まる前に、自分の読解リズムを再確認しておきましょう。朝に短文を読む、夜に1問だけ要約するなど「ルーティン」を決めておくと、冬の学習が崩れません。冬期講習が始まる前に、自分の読解リズムを再確認しておきましょう。朝に短文を読む、夜に1問だけ要約するなど「ルーティン」を決めておくと、冬の学習が崩れません。
親として寄り添うこと
12月は精神的に不安定になりやすい時期に入ります。お子さんの頑張りを認め、小さな成長も具体的に褒めましょう。特に6年生は「過去問の点数」ではなく、「読みの精度が上がったね」「難しい言葉も調べているね」など、努力の過程を評価することが大切です。ルーティン作りも、強制ではなく「一緒に考えてみようか?」と提案し、主体性を尊重しましょう。体調管理にも気を配り、温かい食事や休息を促してください。不安な気持ちに寄り添い、「大丈夫、できるよ」と励ます言葉が、何よりも力になります。
まとめ
11月は、焦らず、でも確実に「読む力」を深める準備期間。「国語の呼吸」を整え、6年生では過去問分析で「読みのズレ」を徹底的に洗い出し、弱点克服に集中しましょう。4.5年生は12月からの冬期講習に向けて、基礎知識の総復習と予習計画も忘れずに。規則正しい生活と体調管理を心がけ、万全の状態でラストスパートを迎えましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
追記
毎週の振り返りに不足しない振り返りは具体的に以下を継続するといいです。
▢音読
▢漢字練習
▢読書文章問題
▢語彙や文法
▢ テストの復習
当たり前のことが崩れ始めたら立て直しです。特に※3連休時のイベントも含め、週明けのペースをつくることが大切です。