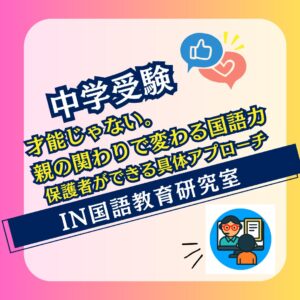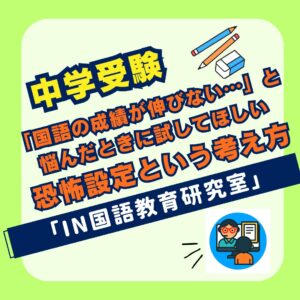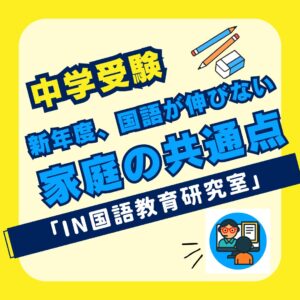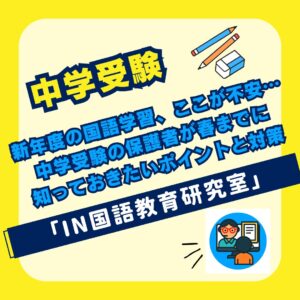才能じゃない。親の関わりで変わる国語力 ― 保護者ができる具体アプローチ
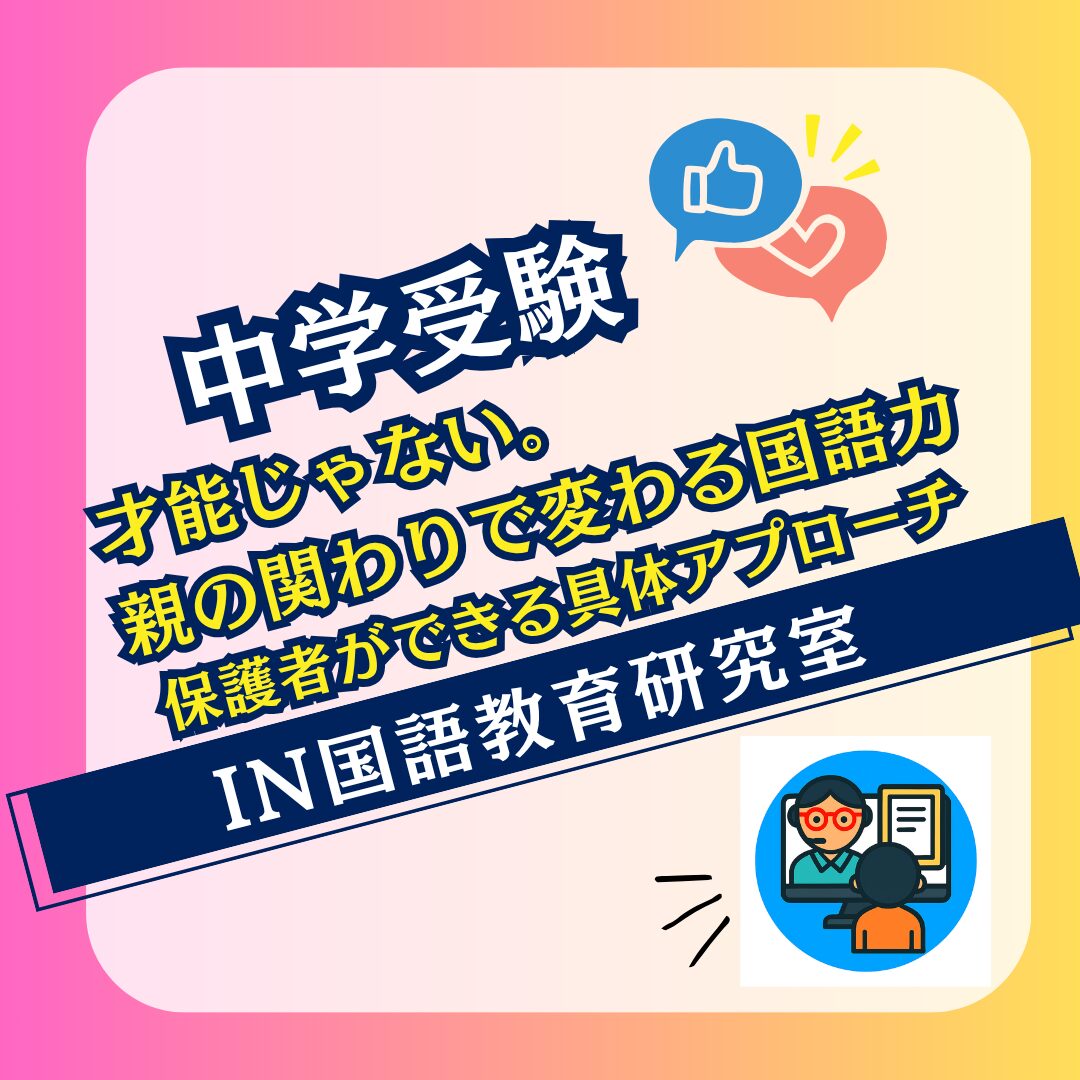
「国語が苦手だと言われたくない」「成績が伸びない」そんな悩みを持つお子さんと向き合う保護者の方は多いでしょう。でも、国語は 「才能」 よりも 「習慣と関わり方」 が鍵です。今回は、保護者の視点から、子どもの国語力を支える方法を具体的にお伝えします。It’s not about talent. Japanese language skills can change with parental involvement — Concrete approaches parents can take.
国語力を育てる「関わりの質」
- 答えの理由を聞く習慣をつける
- 音読を一緒にする時間をつくる
- 文章の「言い換えゲーム」を親子で試す
子どもが答えを言ったとき、ただ「すごいね」だけで終わるのではなく、
「どうしてそう思ったの?」と聞くことで、思考の過程を可視化できます。
また、親が短い文章を朗読して「この言い方いいね」と話すだけで、表現の感度が育ちます。国語力を育てる「関わりの質」。お子さんの国語力を伸ばすために、日々の関わり方を少し工夫してみませんか? 難しく考える必要はありません。ちょっとした声かけや遊びで、お子さんの言葉の力をぐんぐん伸ばせるのです。
- 大切なこと
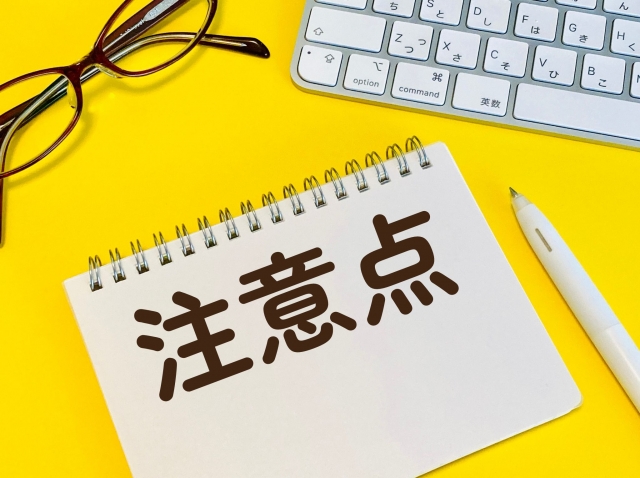
これらの関わりを通して、お子さんの国語力を伸ばす上で一番大切なことは、親御さんが楽しんで、お子さんと一緒に言葉の世界を探求することです。「勉強しなさい!」と強制するのではなく、「これ、面白いね!」「どんな意味かな?」と、好奇心を刺激するような声かけを心がけてみてください。お子さんの成長を信じて、温かく見守りながら、言葉の力を育んでいきましょう。
小さな習慣で読む力を支える
- 朝5分読む時間を確保
- 週に1本短文要約を親子でやる
- 語句帳の確認を日課にする
1日5分でも、継続すれば 「読み慣れ」 が生まれます。
例えば、月曜は語句、火曜は要約、… と曜日で分けて習慣化すると無理なく続けられます。
お子さんの「読む力」を伸ばすために、特別な教材や塾に通わせなくても大丈夫です。日々の生活にちょっとした習慣を取り入れるだけで、着実に読む力を育てることができます。まるで積み木を積み重ねるように、小さな習慣が大きな力になります。
- 習慣化のコツ
これらの習慣を無理なく続けるためには、曜日ごとにテーマを決めるのがおすすめです。例えば、月曜日は語句帳の確認、火曜日は短文要約、水曜日は読書…というように、曜日ごとに内容を変えることで、飽きずに続けることができます。大切なのは、完璧主義にならないこと。もし、一日くらいできなかったとしても、気にせずに次の日からまた始めれば良いのです。お子さんのペースに合わせて、無理なく、楽しく、習慣を続けていきましょう。
学年別工夫と注意点
- 小4〜小5:基礎語彙と表現の引き出しを育てる段階。
- 小6:記述力・過去問対応力を意識した指導を。
- 注意点:親が先回りしすぎて答えを与えないこと。自発性を失わせます。
お子さんの学年に合わせて、国語の学習方法を少し工夫してみましょう。まるで庭に花を植えるように、それぞれの時期に合った育て方をすることで、お子さんの国語力は大きく花開きます。詳しく書いていきます。見聞きしたこともあると思います。私も何度も書いていますので大切なことです。

小4〜小5
基礎語彙と表現の引き出しを育てる段階
この時期は、お子さんの言葉の基礎を固める大切な時期です。例えるなら、家を建てるための土台作り。しっかりとした土台があれば、その上にどんな家でも建てられますよね。語彙力を増やすためには、色々なジャンルの本を読ませることが大切です。物語、図鑑、伝記…何でも構いません。お子さんが興味を持ったものを、どんどん読ませてあげましょう。また、日常生活の中で、新しい言葉に触れる機会を積極的に作ってあげましょう。例えば、料理をしながら「この野菜の名前、知ってる?」「これはどんな味がするかな?」と話しかけたり、ニュースを見て「この事件について、どう思う?」と意見を聞いたりするのも良いでしょう。表現力を高めるためには、日記を書かせたり、物語を作らせたりするのも効果的です。「今日あった面白いこと」「もし自分が〇〇だったら…」など、テーマを決めて、自由に書かせてあげましょう。
大切なのは、お子さんの言葉を否定しないこと。「もっと上手に書きなさい!」と叱るのではなく、「面白いね!」「よく書けてるね!」と褒めて、自信を持たせてあげましょう。
小6
記述力・過去問対応力を意識した指導を
小学校生活の集大成となる小学6年生。中学校へのスムーズな移行、そして将来の高校受験を見据えて、特に「記述力」と「過去問対応力」を意識した学習を心がけましょう。まるで旅の準備をするように、しっかりと装備を整えて、自信を持って次のステージへ進めるようにサポートしてあげてください。
記述力アップ! 表現の幅を広げ、思考を深める
記述力は、単に文章を書く力だけでなく、思考力、分析力、表現力を総合的に高める力です。以下の方法で、お子様の記述力を効果的に伸ばしていきましょう。
- テーマを決めて書く練習
- 日記の進化版
単なる出来事の羅列ではなく、「なぜそう思ったのか」「何を感じたのか」を深掘りして書くように促しましょう。 - 意見文に挑戦
社会問題や学校のルールなど、身近なテーマについて自分の意見を述べさせます。賛成・反対の理由を明確に、根拠となる情報を提示する練習をしましょう。 - 物語の続きを創作
読んだ本の続きを想像して書いたり、登場人物の視点を変えて物語を書き直したりするのも、表現力を高める良い練習になります。
- 日記の進化版
上記は入試に直接関係しない子どももいますが、書くことでアウトプットする力が身につきます。教材を解いたついでに時々息抜きに話し合うだけでも効果があります。塾や個別、家庭教師がちょっと余談として授業の一環で準備していることもあります。
- 書いた文章を添削する
- 親子で添削
お子様の書いた文章を一緒に読み、改善点を見つけましょう。 - 具体的に褒める
良い点は具体的に褒め、「この表現は素晴らしいね」「構成が分かりやすいね」など、どこが良かったのかを伝えましょう。 - 改善点を指摘
改善点も具体的に指摘します。「この部分の表現は少し曖昧だから、具体的に書き直してみよう」「接続詞の使い方を工夫してみよう」など、具体的なアドバイスを心がけましょう。 - 第三者の意見を聞く
先生や塾の講師など、第三者に添削してもらうのも効果的です。客観的な視点からアドバイスをもらうことで、新たな発見があるかもしれません。
- 親子で添削
- 語彙力を増やす
- 類語語を活用
同じ意味でもニュアンスの異なる言葉を学ぶことで、表現の幅が広がります。 - 言葉の背景を知る
言葉の成り立ちや語源を調べることで、言葉への理解が深まります。 - 読書でインプット
様々なジャンルの本を読むことで、自然と語彙力が増えていきます。
- 類語語を活用
国語に時間をかけられない場合は、教材やテストの読解を深めてください。集中して読み解きするようにと伝えることが大切です。時間には限りがあることを入試を持って理解することになります。
時間に余裕がなければ同音異義語・同訓異字語をできるだけ繰り返して学びましょう。
過去問対応力強化! 傾向を掴み、時間配分を意識する
過去問は、志望校の出題傾向や難易度を知るための貴重な情報源です。過去問を効果的に活用することで、合格への道筋が見えてきます。
- 過去問を解くタイミング
- 夏休み明けから
基礎学力が定着してきたら、過去問に取り組み始めましょう。 - 定期的に解く
一度解いたら終わりではなく、定期的に解き直すことで、知識の定着度を確認できます。
- 夏休み明けから
- 過去問を解く際の注意点
- 時間配分を意識
試験時間を意識して解くことで、時間配分の感覚を養います。 - 自己採点
解き終わったら、必ず自己採点を行い、正答率を把握しましょう。 - 間違えた問題を分析
間違えた問題は、なぜ間違えたのかを分析し、弱点を克服しましょう。 - 解答解説を読む
解答解説を読み、正解に至るまでのプロセスを理解しましょう。
- 時間配分を意識
- 過去問ノートを作る
- 間違えた問題を書き出す
間違えた問題をノートに書き出し、解き方のポイントや注意点をまとめましょう。 - 重要語句をまとめる
過去問に出てきた重要語句をまとめ、意味や使い方を確認しましょう。
- 間違えた問題を書き出す
答案は自己採点する場合は答えは親が預かり、答え合わせのとき、直しをする時だけ渡しましょう。第三者に見てもらいアドバイスを活用するのがよいですが、提出返却に時間がかかったり、そもそも場がないということが起きないようにすることです。5年時までには個別や家庭教師をつけておくといいです。理由は一つ。子どもにとってこれ以上ない時間の使い方ができるからです。どんなに優秀な先生の1問のアドバイスをもらえるかどうかわからなければ親として、準備や対応をしないといけません。
親の役割
伴走者として、温かくサポート
小学6年生は、心身ともに大きく成長する時期です。親御さんは、お子様の頑張りを認め、温かく見守ることが大切です。親という漢字は木の上に立って見ると書きます。イメージできなければ、「親=木+立+見」で確認できますね。
- プレッシャーを与えない
結果ばかりを気にせず、努力の過程を褒めてあげましょう。 - 相談に乗る
不安や悩みを聞き、精神的なサポートをしてあげましょう。 - 休息も大切
勉強だけでなく、趣味や運動など、リフレッシュできる時間も確保しましょう。
記述力と過去問対応力を高めることは、単に試験に合格するためだけでなく、お子様の将来に役立つ力となります。焦らず、じっくりと、お子様の成長をサポートしていきましょう。
魔法の言葉!国語力を伸ばす声かけ3例
- 「この文、どこに気持ちが書いてあると思う?」
- 「この言葉の理由、教えてくれる?」
- 「別の言い方ができるとしたら?」
お子さんの国語力を伸ばすために、まるで魔法のような、効果的な声かけを3つご紹介します。これらの言葉をかけるだけで、お子さんの思考力や表現力がぐんぐん伸びていくはずです。
- 声かけのコツ
これらの声かけをする上で大切なことは、親御さんが優しく、穏やかな口調で話しかけることです。まるで友達と話すように、気軽に問いかけてみましょう。また、お子さんの答えを否定したり、馬鹿にしたりすることは絶対にやめましょう。どんな答えであっても、「なるほど、そう考えたんだね」と受け止め、褒めてあげることが大切です。これらの声かけを通して、お子さんの国語力を楽しく、効果的に伸ばしていきましょう。
まとめ
国語力は才能ではなく、育てられる力です。親が丁寧に関わることで、子どもの読む力は変わります。「関わり」 という視点を持って、今日から少しずつ関わってみてください。国語が、「得意」に変わるきっかけを、親子で作っていきましょう。
受験生は頑張っています。
最後の最後まで成績は伸びます!みんな頑張っているのでちょっとやそっとじゃ成績は上がりません。ただ、試験当日は志望校のことだけ考えればいいです。各志望校に受験者は分散しています。
小45年生は来年2月からレベルが上がります。
国語は単元は変わりませんので難易度が上がります。素材文、問い、漢字、語彙、文法、文学史など
Q&A

Q:1月は学校を休ませる?行かせる?
A:インフルエンザやコロナウイルスがはやっていれば休ませると個人的には思います。
そうでなければ普段のペースを守ることを優先し学校へは行かせます。友人関係に問題がある場合などは自粛を検討します。もし、、学校の先生に受験することを伝えていなければ、学校の先生にはっきり理由をこの時期に言っても基本は問題はありません。ほとんどの小学校の先生は周囲の生徒や子どもの様子で気が付いていると思います。
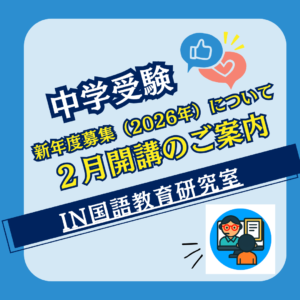
IN国語教育研究室の音声配信(1日10分で学べる 中学受験国語ラボ)
⇒Spotifyでも聴けます。