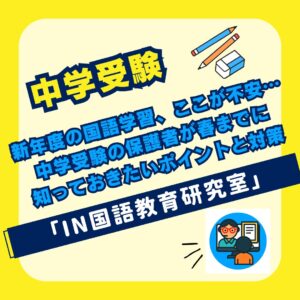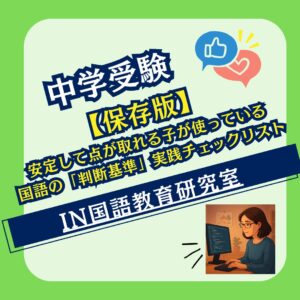国語は後半戦が勝負!10月から伸びる子の共通点とは?

中学受験の国語は「秋から伸びる」と言われます。理由は、語彙や読解技術が積み重なり、一定の基礎ができてから応用問題に挑めるようになるからです。特に10月以降は模試や過去問演習を通じて「実戦力」を鍛える段階に入ります。ここで成果を出す子には共通点があります。それは「過去問の扱い方」を正しく理解していることです。The second half of Japanese language is where you make the difference!
模試や過去問は「合否判定」ではなく「教材」
多くの保護者が誤解しがちなのは、過去問=点数を測るテストだと思ってしまうことです。
もちろん合格可能性を測る材料にはなりますが、10月の段階では「まだ伸びしろを見つける素材」として使うべきです。何度も書いていますが、模試も帳票も「教材」です。目的と目標がわかれば模試や過去問は目的達成までの目標です。問題と課題を設定するためのツールです。受けっぱなしではもったいないです。
エピソード
ある男子生徒は、志望校の過去問で初回40点台でした。親御さんはショックを受けましたが、「どこを間違えたか」を一緒に分析し、設問の意図を考える練習を継続。2か月後には70点台に到達しました。大事なのは「今できない部分」をあぶり出し、修正することなのです。
模試と過去問の使い分け
模試 → 学力の全体像を知り、弱点を把握するため
過去問 → 志望校の出題傾向に慣れ、合格点を取る練習のため
この2つの役割を混同すると、親子のストレスになります。模試は偏差値を気にするもの、過去問は点数よりも「質の高い復習」を意識するもの、と割り切りましょう。
伸びる子の共通点3つ
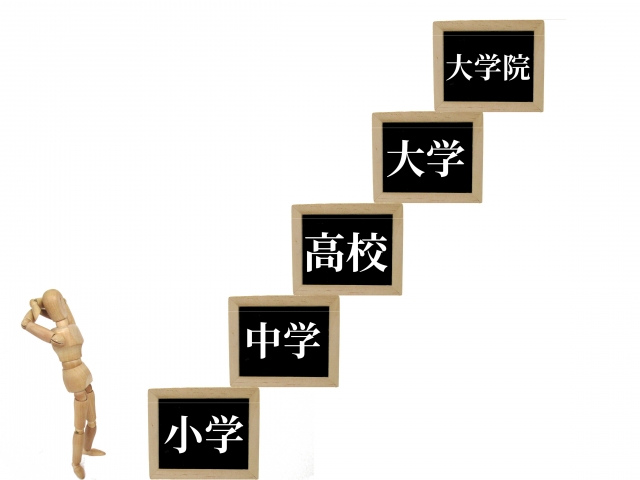
① 設問の意図を言葉にできる
「筆者の主張は?」と問われたら、「本文のここを根拠にして答えればいい」と説明できる子は強いです。
② 解答根拠を本文で示せる
「なんとなく」で選ぶのではなく、本文に線を引き「ここが答えの理由」と示せること。
③ 解き直しを繰り返せる
初回で正解できなくても、2回目・3回目で答えられるようにする。この「修正力」が国語力の成長を加速します。
➀ができるかどうかが第一判断です。
親の「声かけ」が勝負を決める
子どもは模試や過去問で点が低いと落ち込みます。
ここで「なんでできないの!」と叱るのではなく、
「ここを直せば次はできるね」「この設問は難しかったけど工夫できそうだね」と声をかけること。
親の一言が「復習する意欲」を左右します。国語は特に精神的な支えが結果に直結する科目です。
成功例と失敗例
- 成功例
過去問での誤答をファイル化し、同じ間違いをしないよう家庭で振り返った。結果、模試偏差値が半年で8ポイント上昇。 - 失敗例
過去問の点数ばかりを追い、毎回の得点に一喜一憂。子どもは「どうせ受からない」と自己否定的に…。
中途半端はやめましょう。であれば、塾や家庭教師にお願いしましょう。後悔のないようにすることです。
まとめ:10月からが国語力の伸びどき
過去問は「宝の山」です。解きっぱなしにせず、親子で「なぜそう答えたか」を確認する習慣を作れば、国語は秋から冬にかけて一気に伸びます。
この記事を読む価値は、「国語の後半戦で伸びる子と伸びない子の違い」が明確にわかること。そして、今日から実践できる具体的な声かけや復習法が手に入ることです。
国語はまだ間に合います。過去問を正しく使い、10月からの伸びを手に入れましょう。
ここだけの話⇒同じ内容ですいがエピソードや深い話をnoteに書きました2周目として読んでもらえると理解が深まります。3周目でしたら、有料購入すると親としてできる「体験行動」をイメージできます。⇒コチラ

中学受験国語のご相談はIN国語教育研究室まで
指導歴30年、5000名以上の答案分析とアドバイスの経験から、お子様の答案を徹底的に改善し、現時点の最高点を引き出すお手伝いをいたします。
「うちの子の答案、一体どこを直せば…?」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
長年の経験で培った独自の分析力で、お子様一人ひとりの弱点を見抜き、「なぜ間違えるのか」「どうすれば正解できるのか」 を明確にアドバイス。
「国語が苦手…」 と諦めかけていたお子様も、「もっと上を目指したい!」 という意欲をお持ちのお子様も、必ずや現状を打破し、「やればできる!」 という自信を持っていただけると確信しています。
今すぐ、お子様の可能性を最大限に引き出すための第一歩を踏み出しませんか?限定で、無料の答案分析&個別相談も実施中です。
「まずは話を聞いてみたい」 という方も、お気軽にお問い合わせください。
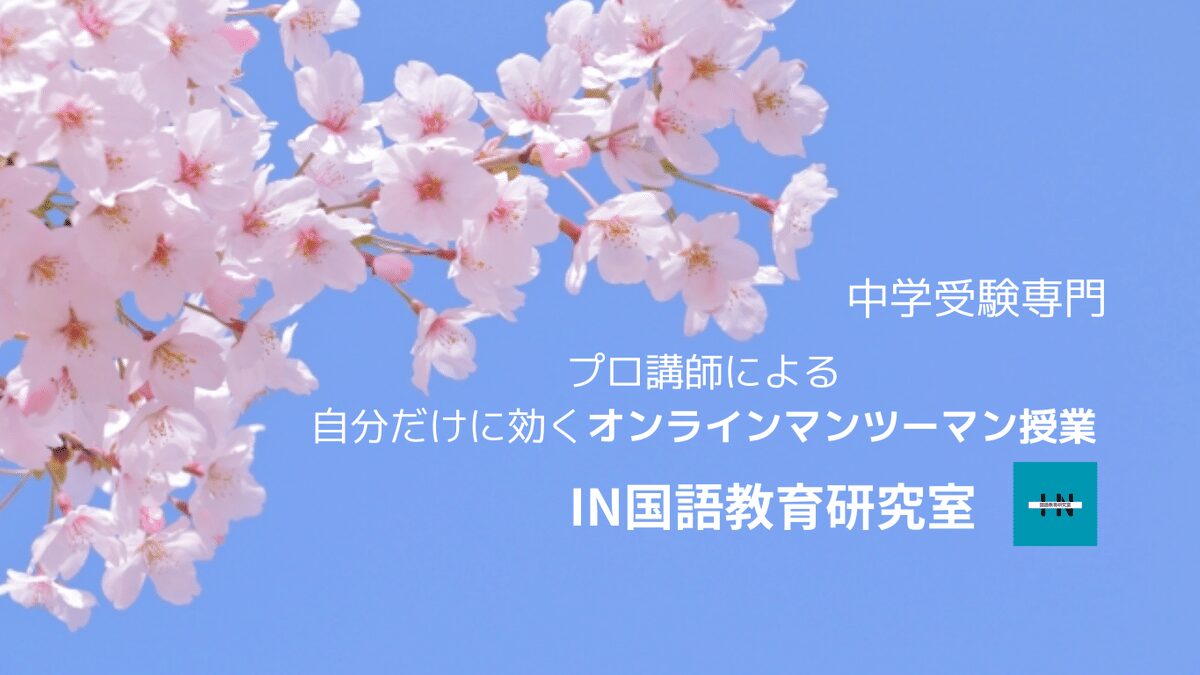
IN国語教育研究室の音声配信(1日10分で学べる 中学受験国語ラボ)
⇒Spotifyでも聴けます。