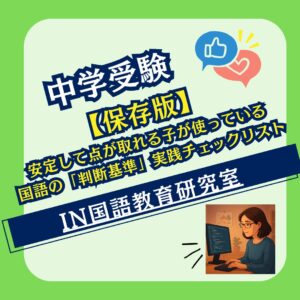中学入試国語の必勝法:説明的文章を得点源に変える家庭サポート術

説明的文章は、文章構造を理解し、設問の意図を読み取り、本文から根拠を探す力が問われます。記号選択・書き抜き・記述など形式が違っても、求められる読解力は同じ。この記事では、保護者が家庭でできる声かけや習慣づけを通して、安定した得点力を育てる方法を紹介します。
Winning Strategies for Junior High School Entrance Exam Japanese: Home Support Techniques to Transform Explanatory Texts into Points.
説明的文章は「型」で読める!でも、なぜ点が取れない?
中学入試の国語では、説明的文章が最も安定して得点できる分野とされています。感情や心情に左右される物語文と違い、論理的な構造を持つ説明文は、読み方の「型」を身につけることで着実に得点力を伸ばすことができます。しかし、実際には「読めているはずなのに、設問に答えられない」「記号問題はできるけど、記述になると手が止まる」といった悩みが多く聞かれます。これは、文章の構造や設問の意図をつかむ力が育っていないことが原因です。
説明的文章の読解では、以下の3つの力が必要です
- 文章の構造を理解する力(接続語・段落展開)
- 問題作成者の問いを理解する力(設問のねらい)
- 素材文から根拠を探す力(本文との照合)
この3つは、記号選択・書き抜き・記述といった形式に関係なく、すべての設問に共通して求められる力です。つまり、形式に惑わされず「何を聞かれているか」「どこに根拠があるか」を見抜く力こそが、得点力の土台になるのです。
家庭でできる!読解力を育てる3つの声かけ術
① 接続語に注目させる:「流れをつかむ目」を育てる
「しかし」「つまり」「たとえば」などの接続語は、文章の論理展開を示すサインです。これを見落とすと、筆者の主張や展開がつかめず、設問の意図もズレてしまいます。
家庭でのサポート方法:
- 問題を解く前に接続語に線を引かせる。
- 段落ごとに「どんな展開があったか」を確認する。
親の声かけ例:
- 「今の段落は『しかし』からどう変わった?」
- 「『つまり』の前と後で、何が整理された?」
実例: 毎朝10分の音読で接続語に色ペンを使う習慣を続けたご家庭では、模試で記述問題の正答率が安定し、「文章の流れが見えるようになった」と実感されたそうです。
② 指示語を正しく追う:「根拠を探す目」を育てる
「それ」「このこと」などの指示語は、前の内容を受けて使われる言葉です。これを読み飛ばすと、理解がズレてしまい、設問の根拠を見失います。
家庭でのサポート方法:
- 指示語が出てきたら、直前の文を指で押さえさせる。
- 具体的に言い換える練習をする。
親の声かけ例:
- 「『それ』って何を指しているのかな?」
- 「『このこと』って、どの話のこと?」
実例: 「指示語チェックタイム」を設けたご家庭では、子どもが模試で「指示語の問題が全部正解だった!」と報告。本文との照合力が育ったことで、記号問題でも記述でも根拠を見つける力が安定したそうです。
③ 要点を言い換える:「問いに答える力」を育てる
説明文の設問は、本文の要点を自分の言葉で言い換える力が問われます。これは記述問題だけでなく、選択肢問題でも「どれが本文の要点に近いか」を見抜く力につながります。
家庭でのサポート方法:
- 段落ごとに「一言でまとめると?」と問いかける。
- 筆者の主張や例示を、自分の言葉で言い換える練習をする。
親の声かけ例:
- 「この段落を一言で言うと?」
- 「筆者は何を伝えたいのかな?」
実例: 「3行要約」を習慣にしたご家庭では、記述問題で「自分の言葉で書く」力が育ち、模試でも安定した得点が取れるようになったそうです。
テストや演習時間は限られています。静時間内で自分の最高得点が取れるかどうかを解く、自己採点、やり直しのサイクルをみにつけることです。「やり直し」は自己採点後にエビングハウスの忘却曲線を利用し、「解き方」の確認をすることです。実際は授業⇒宿題⇒テスト⇒自己採点⇒解き直しの4回ほど繰り返すことです。
記号・書き抜き・記述…形式に惑わされない読解力を

設問形式が違っても、求められる読解力は同じです。記号選択では「本文の要点を見抜く力」、書き抜きでは「根拠を探す力」、記述では「問いに答える力」が問われます。これらはすべて、文章の構造を理解し、設問の意図を読み取り、本文と照合する力に集約されます。
家庭では、親が問題を解く必要はありません。問いかけや確認を通して、子どもが「読み取りの目」を育てることができます。
まとめ:親の声かけが、読解力の土台になる
説明的文章は、「型」を意識して読むだけで得点源になります。保護者ができるのは、問いかけを通して子どもの思考を促すこと。接続語・指示語・要点の言い換えという3つの視点を持つことで、どんな設問形式にも対応できる読解力が育ちます。
👉 今回の内容「中学入試国語の必勝法:説明的文章を得点源に変える家庭サポート術」に連動した「声かけフレーズ集PDF」をもNoteで配布中! 模試前の見直しや、日々の読解練習に役立つツールとして、よろしければご活用ください。PDFは有料版ですが、余計なことは書かず、内容をそぎ落として「シンプル」にしています。続かないと意味がないからです。余白は家庭によって子どもや親が書き込んで記録しておくことです。書くことに困ったら子どもに覚えたい言葉を3回、「息継ぎをしないで書く」ことをお勧めします。このシートは5回実践すればもとはとれます。親子から、摩擦や葛藤を避けるために、このPDFの内容に親の言いたいことを客観的に、言い換えれば子どもの視点を親からPDFに焦点をずらすことができます。要するに子どもへのプレッシャーが軽減できるというのがポイントです。コミュニケーションツールとして利用する場合は印刷してお使いください。

IN国語教育研究室の音声配信(1日10分で学べる 中学受験国語ラボ)
⇒Spotifyでも聴けます。
中学受験国語・受験勉強のお問い合わせはコチラ⇒IN国語教育研究室のホームページ