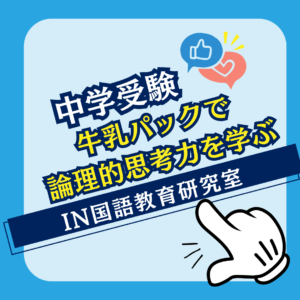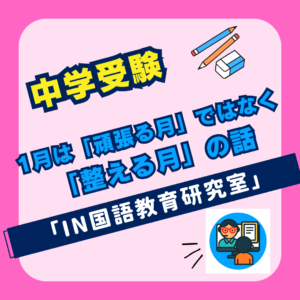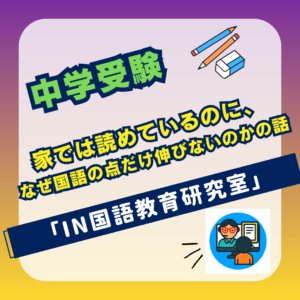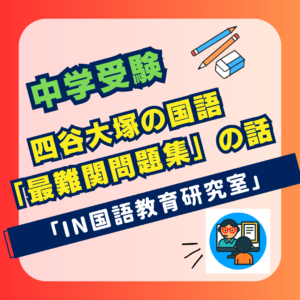牛乳パックで論理的思考力を学ぶ
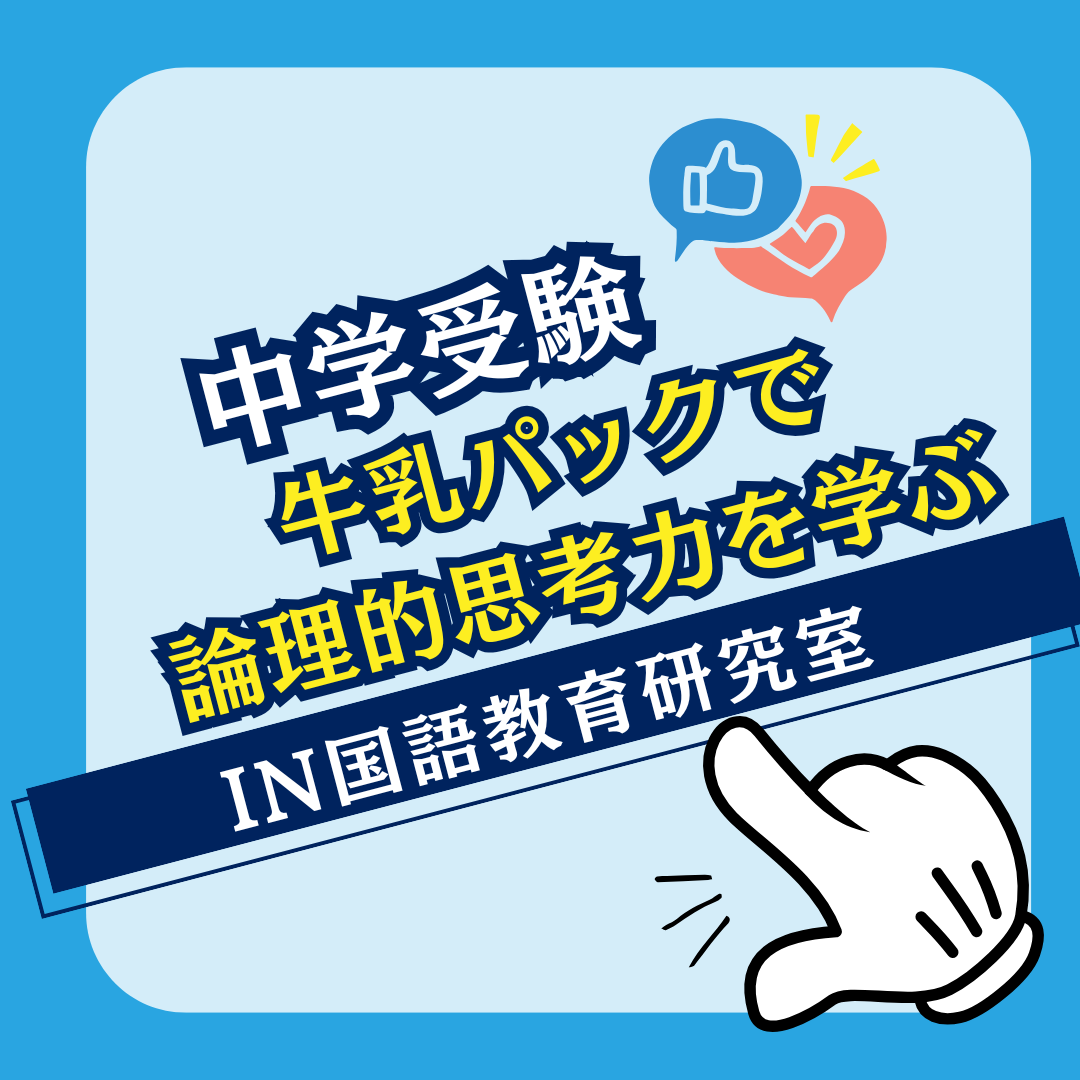
我が子が成長する過程で身につける論理的思考力は、具体的な経験の積み重ねから育まれます。今回は、「かさ」とは何かを理解する過程を通じて、論理的思考の基盤を築く重要性を探ります。かさとは物の分量や内容量を表します。一番良い例は「牛乳パック」。1リットルが1000ミリリットルであることを感覚的に理解する手助けとなることを紹介します。文字だけではなく、体験による学びの価値に焦点を当てることができます。Learning logical thinking skills with a milk carton.
論理的思考力の基盤:体験の力
論理的思考力とは、現実世界での具体的な観察や経験を通じて育まれる能力です。子どもたちが抽象的な概念をよりよく理解するためには、まず生活の中で触れる実体験が必要です。論理的思考力は、情報を分析し、判断を下す能力のことで、多くの場面で重要な役割を果たします。特に子どもの成長期には、遊びや日常生活の経験を通してこの力を育むことができます。例えば、ゲームやパズルを解く過程で問題解決能力が磨かれますし、家での料理の手伝いで計量や順序立てて作業をする練習ができます。論理的思考力を養うには、答えをすぐに教えるのではなく、「どうしてこうなるのかな?」と質問を投げかけたり、子ども自身に考える時間を与えることがポイントです。この力が身につくことで、子どもたちは情報を整理し、自分自身の考えをしっかりと表現できるようになります。
子どもたちが学ぶ「かさ」の理解
買い物に連れていくか、冷蔵庫から牛乳パックを改めて観察させてください。1L=1000mlという公式をただ教えるのではなく、牛乳パックを買う経験が子どもたちに「かさ」の概念を体感的に教えます。パックを手に持つことで、体積や容量についての理解が深まります。成分無調整、生乳等の説明をしてあげてください。酪農と畜産の違いも買い物を通じて体感させるといいでしょう。以下に挙げていることで不足していることがあれば一度でよいので小学生のうちに補ってみましょう。
・牛乳パックには1000mlと記載されている
・重さも体感できる
・使い終わったら乾かして展開図としてハサミをつかって切り処分する(図形×リサイクル)
・dlは普段は使わないが、1Lの1/10として考えるられる
・mlとgの関係、さらに小さいナノ等の「単位」、メガやギガ、テラ等にも応用が効きます。

展開図やリサイクルとセットで学べます
文字を読む前に体験の積み重ねが大切な理由
学びの初期段階では文字や公式よりも、実際の経験が優先されるべきです。体験を通じて得た「感覚」がその後の抽象的な学びを支えます。例えば、水を測る、注ぐなどの行動が容量を実感させます。これは概数(およその数)の理解も進み、桁違いによる計算ミスが激減します。国語では寸や尺、間など昔の単位を考えるときにもすんなり理解し、思考を止めずに集中力を高めます。理科社会では、数値の意味を規模や強さで把握しやすくなります。
親や指導者ができる工夫
家庭や学校で子どもたちに体験を提供する方法を解説します。買い物や料理の場面で容量を意識する活動を取り入れることで、「かさ」の学びが楽しく、より有意義になります。家庭や学校では、子どもたちが「かさ」を感覚的に学ぶ体験を意識的に提供することが、論理的思考力の成長に寄与します。例えば、買い物の場面では、子どもに牛乳パックのサイズや容量を比較する活動を提案できます。「このパックには何リットル入っているのかな?」と問いかけ、実際に手に取って確かめさせることで、容量の感覚を育てます。また、料理の場面では、計量カップを使いながら水や材料を量る体験を通じて、数値と実際の物理的な量を結びつける練習ができます。さらに、親子で「今日はどのくらいの容量が必要かな?」と考える会話を取り入れることで、子どもが自ら予測し計算する力を養います。こうした取り組みは、遊び感覚の中で学びを深める手助けとなり、子どもたちに楽しみながら論理的思考を育む機会を提供します。
まとめ
「論理的思考力」は具体的な体験から始まります。「かさ」を理解するための最初のステップは、身近なものに触れ、自分で感じることです。例えば、牛乳パックを手に取ることで、1リットルが具体的にどれくらいの容量かを感覚的に知ることができます。体験を積み重ねた結果、文字や公式の理解がスムーズになります。親や教師が適切な場を提供することで、子どもたちの思考力はさらに成長します。
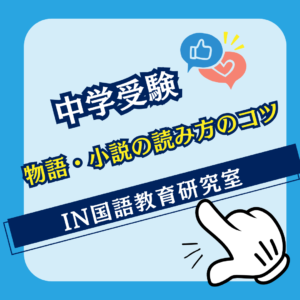
国語のテストの得点が伸びない?成績をもっとあげたい?
お困りごとはIN国語教育研究室までご相談ください。
・子ども向け:成績向上するための授業
・保護者向け:学習相談(学習のペースメイク、志望校選定、併願組みなど)
を行っています。👇
にほんブログ村 ためになったらポチしてください。励みになります!