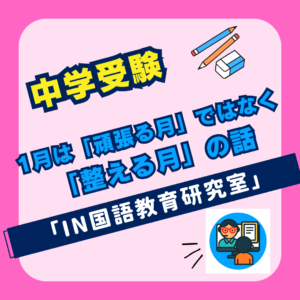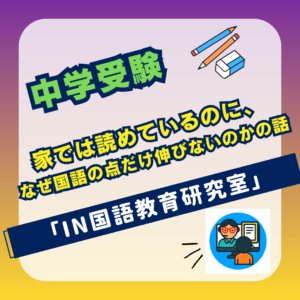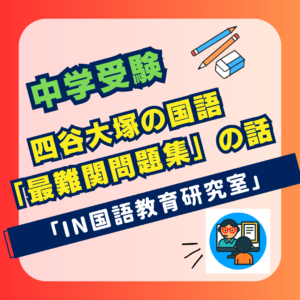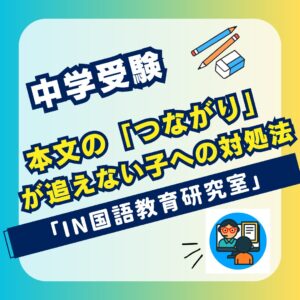「記述が苦手」を克服する!国語の文章題で確実に点を取る手順

「記述問題が苦手」「何を書けばいいかわからない」——そんな悩みを持つ親子は少なくありません。けれど、実は記述問題には“型”があります。しっかり手順を守り自分の特性を知れ、安定して得点ができるようになります。今回は、国語の文章題に取り組む際の基本的な手順と考え方をご紹介します。Overcome your “weakness in writing”! Steps to ensure you get points on Japanese word problems.
題名に注目して、テーマを予想する
文章のタイトルは内容のヒントが詰まった入口です。
「この話はどんなテーマだろう?」
「何について考えさせたいのか?」
などを予想することで、本文の理解がスムーズになります。
素材文を丁寧に読む
本文全体を一読し、大まかな流れをつかみましょう。
時間に余裕があれば、段落ごとの要点をメモしておくと、後の記述で使える情報が整理できます。
設問を分析する
問いの意図を正確に読み取ることが、記述問題の最重要ポイント。
「なぜ〜か」「どのように〜か」といった問いの言い回しから、何を求められているのかをしっかり把握します。
傍線部を手がかりにする
傍線部が示している言葉や現象が、本文のどこに位置づけられているかを考えます。
その前後に答えの根拠となる情報があることが多いので、慎重に読み直しましょう。
本文から「記述の要素」を探す
「なぜ?」「どのように?」と問いかけながら、傍線部と関連の深い部分を見つけましょう。
特に、筆者の主張・具体例・登場人物の心情や行動などがヒントになります。
思考の型を使って整理する
例えば「原因→結果」「対比→結論」「具体→抽象」などの思考の型を活用すると、考えを論理的に整理しやすくなります。
文章構成を考える
見つけた要素を、どう組み立てるかが勝負どころです。
「①答えの結論 → ②根拠 → ③理由や具体例」など、読み手にわかりやすい順番で構成しましょう。
対比、置換、因果を使えないか、記述の条件をまずは意識することです。
まとめ型に注意して書く
書き出しや締めくくりに使う表現によって、文章の印象は大きく変わります。「〜と言える」「〜と考えられる」など、問題作成者の意図に沿い、根拠と結論がぶれないよう注意しましょう。
多くの設問に対応できる字数調整の型の例
・~こと(端的) 基本
・~という~こと(単純論理) 応用
・~のではなく、~という~こと(複数要素の論理) 発展
まとめ
国語の記述問題は、「題名→素材文→設問→傍線部→本文の根拠探し→記述要素の抽出→思考の型→構成→まとめ型への注意」という順番を守ることで、確実に点が取れるようになります。重要なのは、“自分の感覚だけに頼らず、手順に沿って処理する”という意識。思考の「型」を武器に、国語の記述を得意分野に変えていきましょう!
国語のテストの得点が伸びない?成績をもっとあげたい?
お困りごとはIN国語教育研究室までご相談ください。
・子ども向け:成績向上するための授業
・保護者向け:学習相談(学習のペースメイク、志望校選定、併願組みなど)
を行っています。👇
にほんブログ村 ためになったらポチしてください。励みになります!
語彙力強化で最近出された本(語彙のグループ分けができているので、使う場合はここに乗っていない言葉は書き込むといいです。)
Amazonはこちら→中学入試 語彙力トレーニング1400プラス 1 基礎編
Amazonはこちら→中学入試 語彙力トレーニング1400プラス 2 発展編

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e679510.f3c07c5a.3e679511.259eb477/?me_id=1285657&item_id=13042953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01162%2Fbk4578212378.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b57ec68.482857cc.3b57ec69.e9458fe8/?me_id=1213310&item_id=21588189&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2386%2F9784578212386.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)