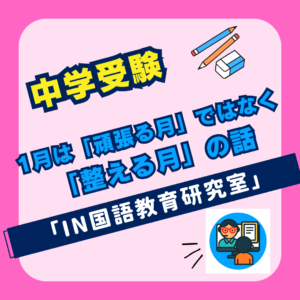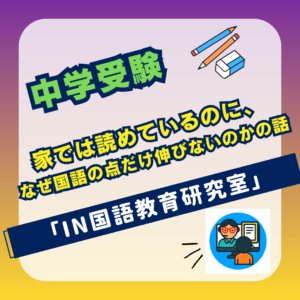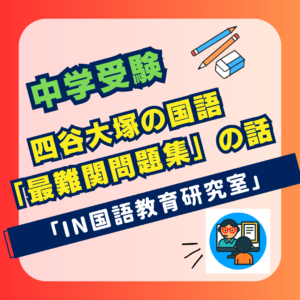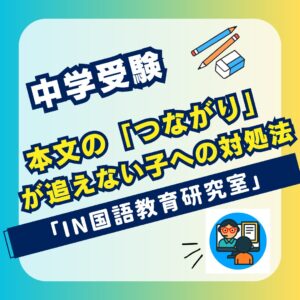設問を読み解く力を鍛える「助詞」の重要性
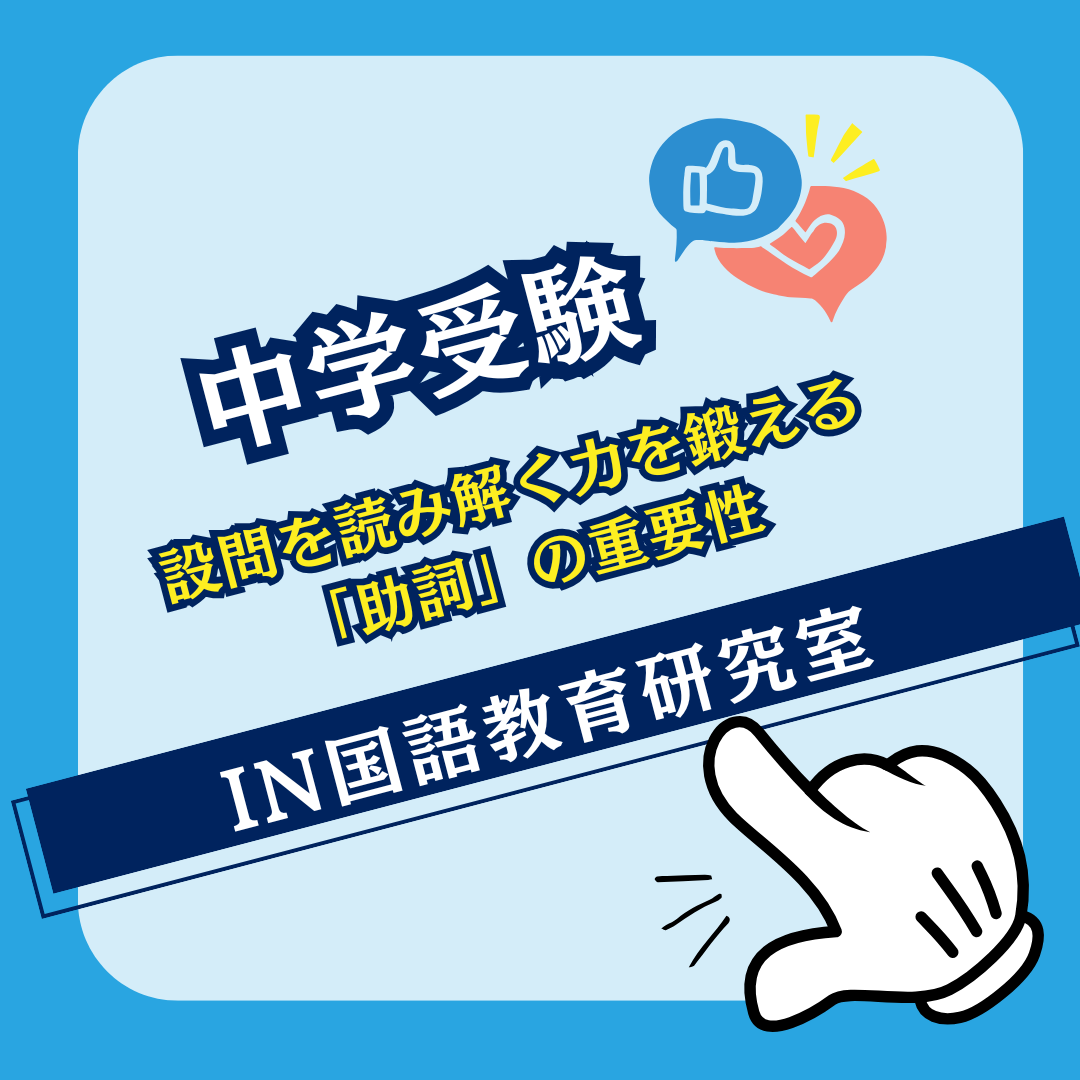
中学受験で最も求められるのは「設問を正確に読み解く力」です。特に国語では文章の流れや意味を把握するのが重要ですが、助詞に注目することで問題を解く鍵が見つかることがあります。例えば、文章題で「~に」や「~を」といった助詞の違いにより答えが変わることがあります。
The importance of “particles” in improving your ability to understand questions
“粒子”在提高理解问题能力方面的重要性.
助詞の違いが導く解答の変化
算数の文章題で数字を適当に並び替えて加減乗除していたら、以下を質問してみてください。
「10を5で割る」と「10で5を割る」の違いを教えて。
文章題が苦手という場合に私がコミュニケーションをするときの質問の一つです。
これらは助詞の「を」と「で」の使い方で解答が全くことなります。
読解力の根本が問題ですのですぐに修正してあげてください。
※学年や個人により「6を3」「2を1」に数字をかえて質問しています。
- 10を5で割る(10 ÷ 5)
10を5つに分けた場合、1つ分の値は?結果は2になります。
例:10個のキャンディを5人で均等に分けた場合、1人あたりのキャンディは2個です。 - 10で5を割る(5 ÷ 10)
5を10で分けた場合、1つ分の値は?結果は0.5になります。
例:5リットルの水を10個のコップに分けた場合、1コップの水は0.5リットルです。
子どもが自分の言葉で、まずは具体で比較しながら説明ができることです。
国語に置き換えると、特に設問に注目することです。
文節単位で設問を理解し、詳細は助詞に着目すると問題作成者の問いを理解し解答方針が思い浮かびやすいです。
- 問題: 「作者がこの段落で述べていることについて、なぜ“花を見た”と書いたか説明しなさい。」
→ 助詞「を」は行動の対象を示しており、実際に目で見たものを指している。 - 問題: 「作者がこの段落で述べていることについて、“花に見える”の理由を説明しなさい。」
→ 助詞「に」は状態や変化を示し、花が他のものと重なって感じられることを表している。
このように、助詞が持つ意味の違いを理解することで、設問の意図を深く読み解く力が育まれます。
名詞のサンドイッチの「の」は説明がより具体的にイメージできます。
文法として知っておくと処理スピードがあがりますが、記述でも字数調整ができ便利です。将来的に古文の文法でも応用できます。「木の上」「SNSの本」など具体的に理解が進みます。
助詞が変わるだけで問題の捉え方が大きく変わるため、設問を読み解く際には注意深く目を向ける必要があります。
指導者の違いが学びに及ぼす影響
指導者が「テキストを教える」のか、それとも「テキストでおしえる」のかによって、学びの本質が大きく異なります。「教える」は知識や解答を与える行為であるのに対し、「おしえる」は考えるきっかけや手法を示し、自ら答えを導き出すプロセスを促します。 一人でも「テキストでおしえる」先生に出会えることで、学びの楽しさを実感し、より深い理解を得ることができるでしょう。解説だけで事足りる子どもは自分で修正改善能力があるので現状に満足せずにブラッシュアップ。そうでない場合は、国語の記述力アップや各種テストの得点向上、志望校対策について、ご家庭ごとのカスタマイズが必要です。
まとめ
助詞と指導スタイルが生む深い学び
助詞は単なる言葉のつなぎ目ではなく、設問の意味を大きく左右する重要な要素です。同様に、指導者のスタイルも学びの深さを決める要因となります。「教える」だけでなく「おしえる」アプローチをする先生に出会うことで、子どもたちは自ら考える力を育み、問題の本質を理解する力を磨いていけます。設問を丁寧に読み解き、助詞や指導スタイルを意識することで、より深く楽しい学びの世界を目指してほしいと思っていただければ幸いです。

サピックス小6B問題で出題されました物語文。
耐えられきれない悲しみを経験した故に複数の人格を持つようになってしまったある少年の物語。ファンタジーと言いつつも多重人格や手品のトリックみたいに現実世界でも起こりうる物語なので読み易い内容だと思います。
四谷大塚「最難関問題集小6上」で出題された「家族と友人」がテーマでの小説。
馬と人が一体となってゴールを目指す耐久レース「エンデュランス」。という競技を知ることができます。500ページ超えの長編小説ですが長文読解として小分けにしながら読むといいです。
📩 お問い合わせフォームはこちら → IN国語教育研究室(自分だけに効く授業)
ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください!
にほんブログ村 ためになったらポチしてください。励みになります!