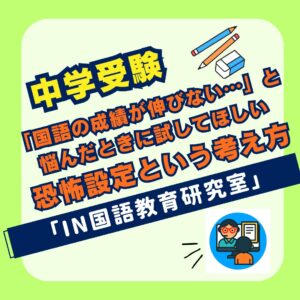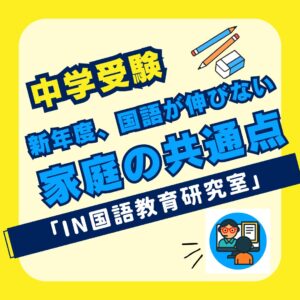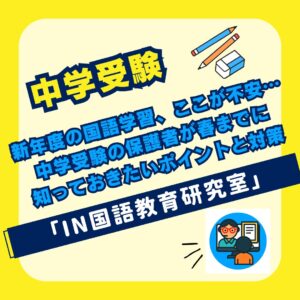接続語で迷わない:記号問題が一気に解ける3つの視点

記号問題で「どれを選べばいいかわからない」とつまずく子は意外と多いものです。原因の多くは接続語の読み取りが曖昧なことです。接続語はただの「つなぎ言葉」ではなく、筆者の論理や流れを示す重要なサインです。この記事では、家庭でできるシンプルな3つの視点と具体的な練習方法を紹介します。一言で言えば言葉と言葉、文と文を使う接着剤です。Don’t Get Confused by Connective Words.
記号問題、もう苦手とは言わせない!接続語を「道しるべ」にする3つの秘策
「記号問題がどうも苦手…」
お子さんのテストを見て、そんな風に感じたことはありませんか?実は、記号問題が苦手なお子さんの多くは、接続語を「なんとなくの意味」で処理してしまっているんです。でも、ちょっと待ってください!接続語は、文章全体の構造を理解するための道しるべです。原因と結果、対比、例示、結論など、文章の関係性を明確に示す重要な役割を担っています。つまり、接続語を正確に読み解けるかどうかが、記号問題の正答率を大きく左右すると言っても過言ではありません。そこで今回は、お子さんが接続語を「道しるべ」として活用し、記号問題を克服するための3つの秘策をご紹介します。
接続語を「言い換える」魔法
「しかし」や「だから」といった接続語を、ただ漫然と読むだけでは、その真価は発揮されません。大切なのは、接続語が持つ「機能」を短い言葉で言い換えること。例えば…
- 「しかし」 → 「前の考えと比べて違うことを言う」
- 「だから」 → 「前の内容を受けて結論を出す」
このように言い換えることで、接続語が文章の中でどのような役割を果たしているのかが、より明確になります。
まずは親御さんが、接続語の言い換えの見本を示してあげましょう。そして、お子さんに真似させてみてください。最初は難しくても、繰り返すうちに自然と理解が深まります。
接続語の前後を「セットで読む」習慣
接続語は、単独で意味を持つものではありません。前の文と後の文がどのような関係にあるのかを理解して、初めてその役割を果たすことができます。つまり、接続語の前後をセットで読むことが非常に重要です。
【練習法】
- 接続語を見つけたら、前の文を指でなぞりながら読みます。
- 「前はこう言っている → 接続語 → 後はこう言っている」と声に出して言ってみましょう。
この練習を繰り返すことで、「つながり」を視覚と聴覚の両方で確認でき、文章全体の流れを掴みやすくなります。
選択肢は本文の流れを確認した後読む
記号問題に苦手意識を持つお子さんの多くは、いきなり選択肢から読み始めてしまいがちです。しかし、これでは本文の論理とズレが生じ、混乱を招く原因となります。大切なのは、まず本文をしっかりと読み込み、「筆者は今、何を言いたいのか」を一言でまとめるクセをつけることです。
【練習法】
- 本文を読んだら、30秒で「話の流れ」を一言で言わせてみましょう。
- 最初は親御さんが手本を示してあげると、お子さんも取り組みやすくなります。
ざっくりでも構いません。思い出すことが大切です。ざっくりと思い出せない場合を「棒読み」と私は定義しています。本文の流れを把握してから選択肢を検討することで、正解を選びやすくなるだけでなく、誤った選択肢に惑わされることも少なくなります。
【まとめ】接続語を味方につけて、記号問題を得意に!
今回ご紹介した3つの秘策を実践することで、お子さんは接続語を「道しるべ」として活用し、記号問題に対する苦手意識を克服できるはずです。問題作成者は設問型式として記述、記号、書き抜きの3方式のいずれかで出題していますが、接続語(接続詞)は記号問題がほとんどです。得点源になると、副次的に修飾語(主に副詞)の挿入問題との違いもわかってきます。ぜひ、今日からお子さんと一緒に、接続語の読解トレーニングに取り組んでみてください。目に見える成果がでてくると嬉しい限りです。
接続語は文節、接続詞は単語。一文節=一単語であることが理解できている受験生とそうでない受験生では学習の解像度が異なります。答えはあっていたとしても安定した得点はとれないというのがポイントです。
【ダウンロード特典】接続語チェックシート
印刷して、不足スキルがないかを確認するためのものです。テスト時間が足りなくなるくらい設問数が多くなる前に身につけて欲しい所作ですのでお子様に必要だなとおもわれるものを取り入れてみてください。私の場合は他の解き方や暗記法などお子様に自信をもってもらうような二の矢、三の矢を用いることで、学年が上がるごとに難易度があがる際に記述に問題に時間をあてられるよう心がけています。

「お問い合わせ」や音声配信「1日10分で学べる国語ラボ」はこちらから👇