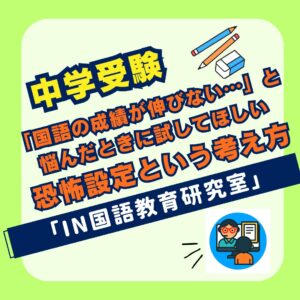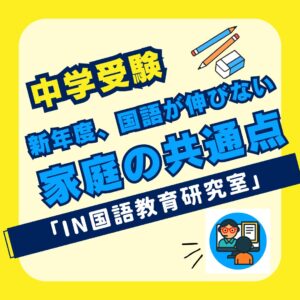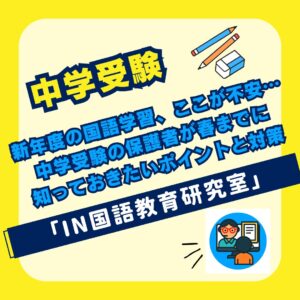「記号が合わない…」その理由は?文章のつながりを読むコツ

中学受験の国語で「記号問題が合わない…」と悩む子は多くいます。しかし、原因は国語が苦手だからではなく、ほとんどの場合「文章の流れ」を追えていないだけ。今回は、つながり読みのコツと、家でできる練習方法をまとめました。記号問題は、国語の中でも基礎力が強く問われる分野です。なぜなら、記号問題とは「筆者の話の流れ」を正しく追えているかを見る問題だからです。記号が合わない子の多くは、文章を「点」で読んでしまいがちです。段落ごとに読むのではなく、前後の関係をつなげずに読んでしまうため、選択肢で迷います。“The symbols don’t match…” Why is that? Tips for understanding the flow of a text.
記号問題が苦手な子に共通する読み方

- 段落を単体で読み、「前後の流れ」を確認しない
- 接続語や副詞を雰囲気で処理してしまう
- 理由・結論の関係を飛ばして読む
こうした読み方だと、筆者の主張がつかみにくくなり、似たような選択肢に引っかかってしまいます。
家庭でできる「つながり読み」トレーニング
① 段落ごとの要約を5秒で
「この段落、何を言ってる?」と短く言わせるだけでOKです。内容を線でつなぐ準備になります。
② 接続語を声に出す
「だから」「しかし」「たとえば」などの前後関係を、子ども自身の口で説明させると理解が深まります。「しかし」以降に重要なことが書いていますが、国語が苦手なお子様には「しかし」に〇をつけているだけの「作業」になっている場合が多いです。接続語の7種類は空で言えるようにしましょう。
③ 親が問いかけで流れをつくる
「つまり?」「どうしてそう思った?」「前は何を言ってた?」この3つだけでも、読みの質が一気に変わります。
記号問題が得意な子の暗黙知
個性がありますが、いくつかのパターンが考えられます。以下に、可能性の高いアプローチと、それぞれの詳細について解説します。
1. 論理的思考と選択肢の絞り込み
- 得意な子の特徴
- 論理的な思考力が高く、問題文の構造やキーワードを正確に把握できる。
- 選択肢に含まれる情報と問題文との整合性を素早く判断できる。
- 誤った選択肢に含まれる矛盾点や誤りを見抜くのが得意。
- 設問比較のステップ
- 問題文の正確な理解
問題文を注意深く読み、問われている内容、条件、キーワードを明確にする。図やグラフがあれば、それらも詳細に分析する。 - 選択肢の分類
各選択肢を、問題文に合致する可能性が高いもの、低いもの、明らかに誤っているものに分類する。 - キーワードの照合
各選択肢に含まれるキーワードと、問題文中のキーワードを照合する。一致しないキーワードを含む選択肢は、誤りの可能性が高いと判断する。 - 論理的な検証
残った選択肢について、論理的な整合性を検証する。選択肢の内容が、問題文の条件や前提と矛盾しないかを確認する。 - 消去法の活用
明らかに誤っている選択肢を消去し、残った選択肢の中から最も可能性の高いものを選ぶ。 - 最終確認
選んだ選択肢が、問題文全体の内容と矛盾しないか、再度確認する。
- 問題文の正確な理解
2. パターン認識と経験則の活用
- 得意な子の特徴
- 過去の類似問題を多く解いており、問題のパターンを認識する能力が高い。
- 特定のキーワードや言い回しが、正解または不正解の選択肢に頻出することを経験的に知っている。
- 問題の形式や出題者の意図を推測するのが得意。
- 設問比較のステップ
- 問題のパターン認識: 問題文を読んで、過去に解いた類似問題のパターンを思い出す。
- キーワードのパターン認識
選択肢に含まれるキーワードや言い回しが、過去の類似問題で正解または不正解の選択肢に頻出していたかどうかを思い出す。 - 選択肢の絞り込み
過去の経験に基づいて、可能性の低い選択肢を絞り込む。 - 論理的な検証
残った選択肢について、論理的な整合性を検証する。 - 直感的な判断
最終的には、直感的に最も可能性の高い選択肢を選ぶ。 - 念のための確認
選んだ選択肢が、問題文全体の内容と矛盾しないか、念のため確認する。ただし、自信があれば振り返りません。
3. 図や表の活用(イメージ化)
- 得意な子の特徴
- 問題文の内容を図や表に整理し、視覚的に理解するのが得意。
- 図や表を使って、選択肢の内容を比較検討するのが得意。
※お子さんによって文字や音で認知する場合もあります。
- 設問比較のステップ
1. 問題文の図式化: 問題文の内容を図や表に整理する。
2. 選択肢の図式化: 各選択肢の内容を図や表に整理する。
3. 図や表の比較: 問題文と選択肢の図や表を比較し、一致する部分と矛盾する部分を見つける。
4. 選択肢の絞り込み: 矛盾する部分が多い選択肢を消去する。
5. 残った選択肢の検討: 残った選択肢について、さらに詳細に検討し、最も可能性の高いものを選ぶ。
4. 時間配分とリスク管理
- 得意な子の特徴
- 試験時間全体を考慮し、各問題に費やす時間を適切に配分できる。
- 難しい問題に時間をかけすぎず、解ける問題から確実に解いていく。
- 時間切れになる前に、すべての問題に解答できるように、リスク管理を徹底している。
- 設問比較のステップ
- 時間配分の設定:
試験開始前に、各問題に費やす時間の上限を設定する。 - 優先順位の設定
解ける問題から優先的に解き、難しい問題は後回しにする。 - 時間管理
各問題に費やす時間を常に意識し、時間超過にならないように注意する。 - 見切り発車
どうしても解けない問題は、時間切れになる前に、最も可能性の高い選択肢を選んで、次の問題に進む。 - 余った時間の活用
試験終了前に時間が余ったら、見直しや、解けなかった問題に再挑戦する。
- 時間配分の設定:
ここまでで、必要な課題を見つけて演習時、やり直し時に型をみにつけると応用も効いてきます。
一発で選べる場合はそのまま。迷った場合は2択で比較し、設問に近いものと比べる、それでも難しい場合は根拠を探す。それでもダメな場合は仮置きして次に進むことです。
設問比較の際の注意点
★先入観の排除
過去の経験や知識にとらわれず、問題文に書かれている情報のみに基づいて判断する。
★深読みの回避
問題文を必要以上に深読みせず、表面的な意味を正確に理解する。
★焦りの防止
時間に追われて焦ると、誤った判断をしやすくなる。落ち着いて、論理的に考えるように心がける。
★見直しの徹底
解答後には、直後に必ず見直しを行い、写し間違いなどのケアレスミスを防ぐ。
これらのアプローチは、記号問題が得意な子が必ずしも意識的に行っているとは限りません。しかし、無意識のうちにこれらの要素を組み合わせ、効率的に問題を解いています。ここまで見てくれる先生に出あえるといいですね。
どうしても記号が絞れない場合は?
記号がどうしても絞り切れない場合の対処法はいくつかあります。状況に応じて使い分けてみてください。
1. 情報の整理と再確認(基礎)
- 問題文の再読
問題文をもう一度丁寧に読み返し、見落としている条件や制約がないか確認します。特に、記号の意味や定義が明記されている部分を注意深くチェックしましょう。 - 関連知識の確認
関連する知識や公式を復習し、問題解決に役立つ情報がないか探します。教科書、参考書、ノートなどを参照し、理解が曖昧な部分を解消しましょう。 - 具体例の検討
具体的な数値や事例を当てはめて考えることで、記号の意味や関係性をより深く理解できる場合があります。いくつか例を試してみることで、法則性やパターンが見えてくるかもしれません。 - 図や表の活用
問題文の内容を図や表に整理することで、情報の構造や関係性を視覚的に把握しやすくなります。特に、複雑な条件や制約がある場合に有効です。
2. 発想の転換(応用)
- 視点の変更
問題を別の角度から見てみることで、新たな解法やアプローチが見つかることがあります。例えば、記号の意味を逆転させて考えたり、問題をより単純化したりしてみましょう。 - 類似問題の検討
過去に解いた類似問題を参考に、解法や考え方を応用できないか検討します。類似問題の解法を参考に、自分なりの解法を組み立ててみましょう。 - 仮説の検証
いくつかの仮説を立て、それぞれについて検証してみることで、正解に近づける場合があります。仮説が誤っている場合は、その原因を分析し、新たな仮説を立て直しましょう。 - 休憩
一度問題を離れて休憩し、気分転換することで、新たな発想が生まれることがあります。リラックスした状態で問題に再度取り組むことで、意外な解決策が見つかるかもしれません。
3. 段階的なアプローチ(発展)
- 部分的な解決
問題全体を一度に解決しようとせず、部分的に解決していくことで、徐々に全体像が見えてくることがあります。まずは、解ける部分から着手し、徐々に難易度を上げていきましょう。 - 場合分け
問題の条件に応じて、場合分けを行うことで、問題をより単純化できる場合があります。それぞれの場合について、個別に解決策を検討しましょう。 - 近似
正確な解を求めるのが難しい場合は、近似的な解を求めることを検討します。近似的な解を求めることで、問題の本質を理解し、より正確な解を導き出すためのヒントを得られるかもしれません。 - 試行錯誤
様々な解法を試してみることで、正解に近づける場合があります。試行錯誤の過程で、新たな発見や気づきがあるかもしれません。
4. 他者への相談
- 先生や友人への質問
先生や友人に質問することで、自分では気づかなかった視点や解法を教えてもらえることがあります。質問する際には、自分がどこまで理解できていて、どこで詰まっているのかを具体的に説明しましょう。 - オンライン授業の活用
質問することで、様々な知識や経験を持つ人々からアドバイスをもらうのが一番早いです。10年前ではほぼなかった対応方法です。質問する際には、問題文を正確に記述し、自分が試した解法や考え方を詳しく説明しましょう。難易度が高い場合はできなくてもいいという記号問題もあります。時間を奪われないように対応法を教えてもらうことです。私の場合は「仮置き」という方法で次に進むようにアドバイスします。

5. 最終手段
- 解答の確認
どうしても解けない場合は、解答を確認し、解法を理解することに努めます。解答を理解するだけでなく、なぜその解法が有効なのか、他の解法ではなぜうまくいかないのかを深く考察しましょう。 - 類似問題の演習
解答を確認した後、類似問題を解くことで、理解を深め、応用力を高めます。類似問題を解く際には、解答を見ずに、自分の力で解けるように努力しましょう。
重要なポイント
- 諦めない
難しい問題に直面しても、すぐに諦めずに、粘り強く取り組むことが大切です。 - 記録
試した解法や考え方、詰まった箇所などを記録しておくことで、後で振り返り、改善点を見つけやすくなります。 - 反省
解答を確認した後、なぜ解けなかったのか、どこで間違えたのかを反省し、今後の学習に活かしましょう。
これらの対処法を参考に、状況に応じて最適な方法を選択し、問題解決に臨んでください。PDCAで解き方の確認をすることです。設問の意図と予想すること、そして根拠を総合判断して解くことが重要です。
まとめ
記号問題は「運」ではなく、明確な読みの技術です。文章のつながりを意識して読むだけで正答率は上がります。家庭学習の中に、短い練習を組み込むことで、国語が苦手な子でも確実に伸びます。