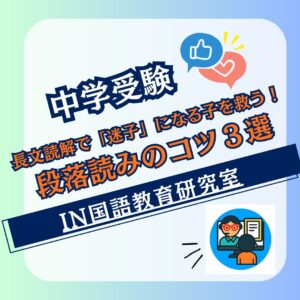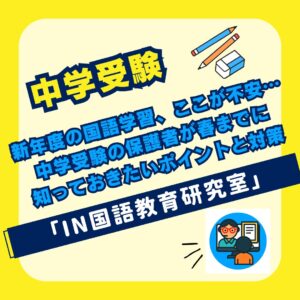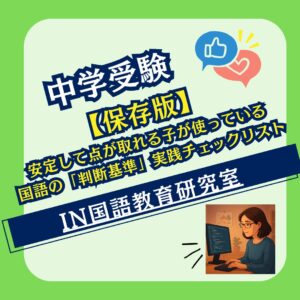長文読解で「迷子」になる子を救う!段落読みのコツ3選
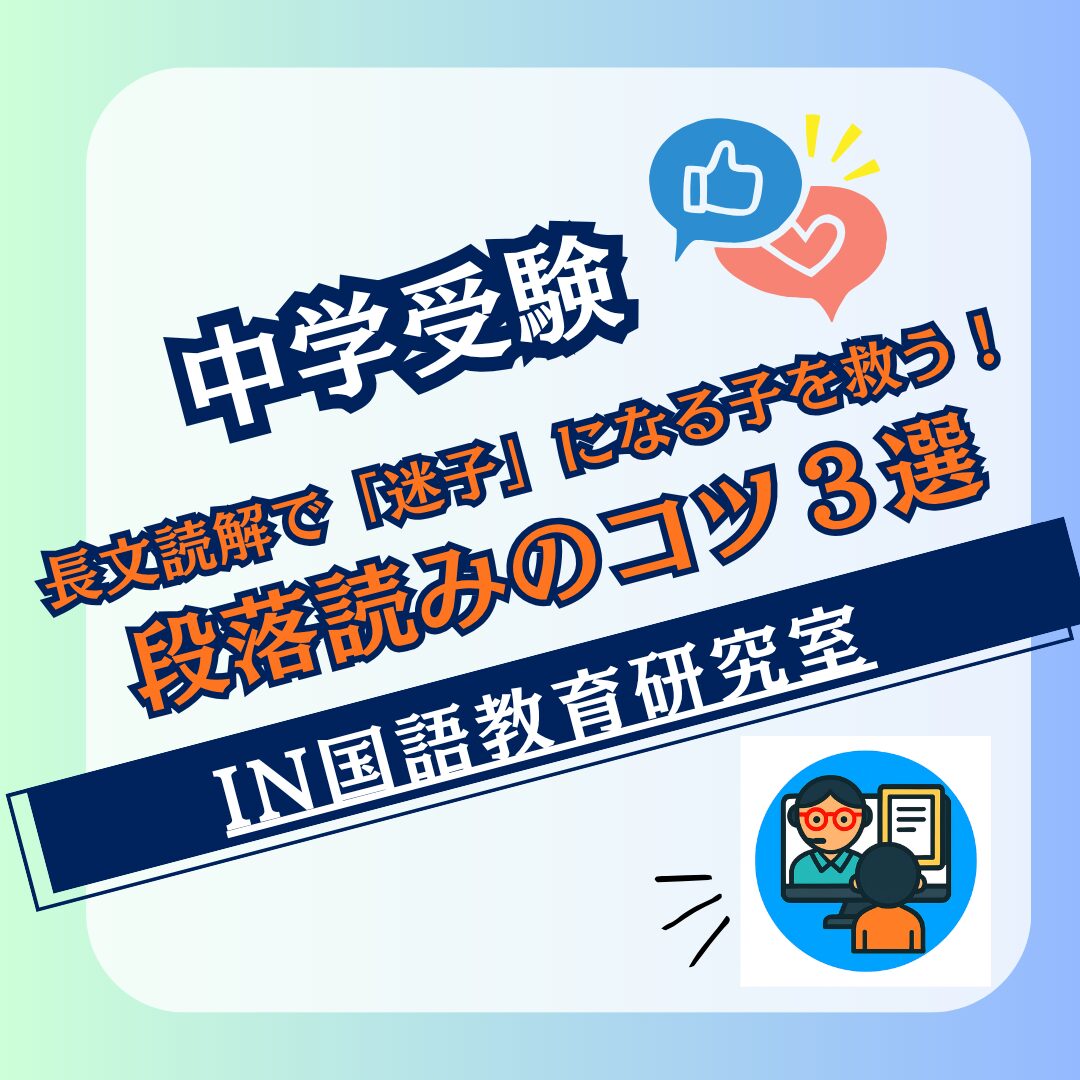
本文を読んでいるのに、内容がつかめない。国語の長文読解で迷子になる子どもに多いのが、段落や場面の役割を意識していないことです。文章は段落の積み重ねでできています。それぞれの段落には「導入」「展開」「まとめ」といった役割があり、それを意識するだけで、読みやすさが変わります。今回は、段落読みのコツを3つ紹介します。Save children who get ‘lost’ in long reading passages! 3 tips for reading paragraphs.
中学受験を制する!親御さんのための読解力向上講座
お子様の中学受験をサポートする上で、親御さん自身が文章を深く理解し、本質を見抜く力は非常に重要です。国語の読解問題はもちろん、社会や理科の記述問題、さらには面接対策にも役立つ、実践的な読解術をお伝えします。

① 前半は題名とともに「羅針盤」として捉える!
文章の最初の段落は、羅針盤であり、航海図の出発点です。筆者が何を伝えたいのか、どのような主張を展開するのか、文章全体の方向性が示されています。ここを丁寧に読み解くことで、文章の全体像を把握し、効率的な読解が可能になります。
- 具体的には?
- 目的意識を持つ
最初の段落を読む前に、「この記事は、中学受験の〇〇について教えてくれるのだろうか?」「〇〇の対策方法について解説してくれるのだろうか?」など、目的意識を持って読み始めましょう。 - キーワードを特定する
最初の段落には、文章全体を貫くキーワードが散りばめられています。例えば、「思考力」「記述力」「読解力」「論理的思考」「情報リテラシー」など、中学受験に関連するキーワードに注目し、メモを取りましょう。 - 筆者の立場を推測する
- 最初の段落から、筆者がどのような立場(塾講師、教育評論家、現役教師など)で、どのような視点から文章を書いているのかを推測しましょう。これにより、文章の信頼性や客観性を判断する手がかりとなります。
- 問題意識を捉える
- 最初の段落には、筆者が問題意識を持っている点が示されていることがあります。「〇〇の現状」「〇〇の課題」「〇〇の重要性」など、問題意識を捉えることで、文章のテーマを深く理解することができます。
- 親御さん自身の読解力向上
お子様の読解力を高めるためには、親御さん自身が積極的に文章を読み、読解力を向上させることが重要です。新聞記事や教育関連の書籍などを読み、お子様と一緒に内容について話し合うことで、読解力を高めることができます。
- 目的意識を持つ
② 中盤のは素材文の内容の「変化」を追う!
文章の中盤では、筆者の主張を裏付けるための根拠、具体例、反対意見、そしてそれらに対する反論などが展開されます。筆者の考えがどのように変化していくのか、意見がどのように展開されていくのかを注意深く追うことで、文章の論理構成を理解することができます。
- 具体的には?
- 意見の変化を捉える
筆者の意見が変化する箇所には、接続詞(しかし、一方、ただし、など)が用いられることが多いです。これらの接続詞に注目し、「何がどう変わったのか」をメモしながら読み進めましょう。 - 具体例を分析する
具体例は、抽象的な概念を理解するための手がかりとなります。具体例を分析することで、筆者の主張をより深く理解することができます。例えば、具体的な事例、データ、統計、引用などを分析し、筆者の主張を裏付ける根拠として妥当かどうかを判断しましょう。 - 対比構造を理解する
筆者は、ある概念を説明するために、対比構造を用いることがあります。例えば、「〇〇と△△の違い」「〇〇のメリットとデメリット」など、対比構造を理解することで、筆者の主張をより明確に理解することができます。 - 論理展開を把握する
筆者は、論理的な思考を用いて、自分の主張を展開します。論理展開を把握することで、文章全体の構造を理解することができます。例えば、「主張→根拠→結論」「問題提起→解決策→展望」など、論理展開のパターンを意識しながら読み進めましょう。 - お子様への問いかけ
お子様が文章を読んでいる際に、「筆者はここで何を言いたいのだろう?」「この例は何を説明しているのだろう?」「筆者の意見は変わったかな?」など、問いかけをすることで、お子様の思考力を刺激し、読解力を高めることができます。
- 意見の変化を捉える
③ 後半は「筆者のメッセージ」を読む!
文章の最後の段落は、筆者が最も伝えたいメッセージが凝縮された部分です。まとめ、主張、願いなど、筆者の思いが最も明確に表現されます。ここを丁寧に読み解くことで、文章全体のテーマを理解し、筆者の意図を把握することができます。説明的文章では論旨、文学的文章では主題と分けておくといいです。
- 具体的には?
- 結論を明確にする
最後の段落には、文章全体の結論が示されています。「結局、筆者は何を伝えたかったのか?」を明確に言葉にして確認しましょう。 - 主張を特定する
筆者の主張は、単なる意見ではなく、根拠に基づいた論理的な結論です。筆者の主張を特定することで、文章全体のテーマを深く理解することができます。 - 願いを読み取る
筆者は、文章を通じて、読者に何かを訴えかけたいと考えています。筆者の願いを読み取ることで、文章の背景にある社会的な問題意識や倫理観を理解することができます。 - 自分自身の意見を形成する
筆者のメッセージを理解した上で、自分自身の意見を形成することが重要です。「筆者の意見に賛成できるか?」「筆者の意見に反対する理由はあるか?」「自分ならどう考えるか?」など、批判的な視点を持って考えることで、思考力を高めることができます。 - お子様との対話
最後の段落を読んだ後、お子様と文章の内容について話し合いましょう。「この記事で一番印象に残ったことは何?」「筆者の意見に賛成できる?」「自分ならどう考える?」など、対話を通じて、お子様の理解度を確認し、思考力を深めることができます。
- 結論を明確にする
これらの読解術を実践することで、親御さん自身が文章を深く理解し、お子様の中学受験を強力にサポートすることができます。お子様と一緒に文章を読み解き、思考力を高め、合格を勝ち取りましょう!
文章を書いた人、問題を作った人、自分の考えという3つの立場があります。照準を合わせるのは「問題を作った人」が理想とする答えです。特に、小説は作家が解いても心情・テーマはわからないという場合もままあります。
まとめ

長文読解は「思考の可視化」!3つの視点で文章を構造的に捉える
長文読解を攻略する鍵は、文章を単なる文字の羅列として捉えるのではなく、筆者の「思考の流れ」として理解することです。今回ご紹介した3つの視点(①羅針盤としての冒頭、②変化を追う中盤、③メッセージが凝縮された結び)を意識することで、複雑な文章も構造的に捉え、本質を見抜く力が養われます。
親御さんの役割は「ナビゲーター」!優しく問いかけ、思考を促す
親御さんができる最も効果的なサポートは、お子様の読解プロセスをナビゲートすることです。「今、どの段落を読んでいるの?」「この段落は何について書かれているの?」と優しく問いかけることで、お子様は文章全体における現在地の確認、そして文章の目的を意識するようになります。
問いかけは「思考の種まき」!読解力は確実に開花する
このような問いかけは、お子様の思考力を刺激し、読解力を飛躍的に向上させるための「種まき」です。正解を教えるのではなく、お子様自身が考え、理解を深めるプロセスをサポートすることで、読解力は着実に開花していくでしょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

👇IN国語教育研究室のお問い合わせはこちら👇