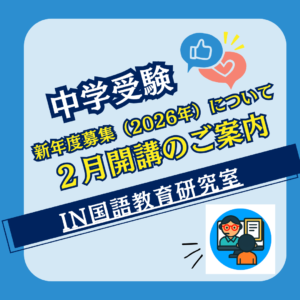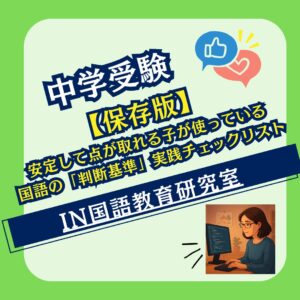「読むのが遅い」子どもに共通する3つの特徴と改善法
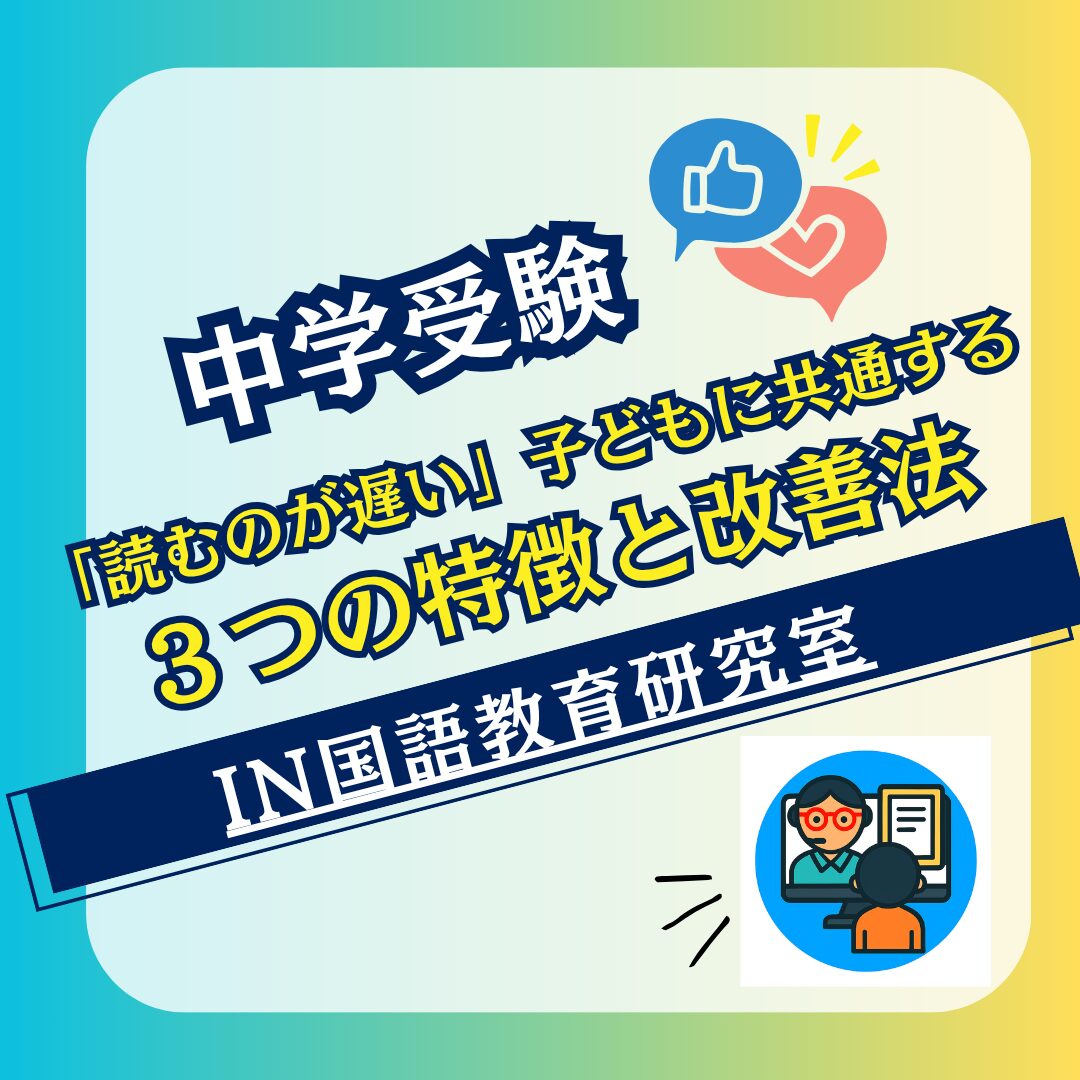
「うちの子、読むのが遅いんです」そのお悩み、解決の糸口は意外なところに!国語の相談で、保護者の皆様からよく耳にするのが「うちの子、読むのが遅いんです」というお悩みです。テストの時間配分がうまくいかない、宿題に時間がかかりすぎる…そんな状況に、親御さんも心配されていることでしょう。しかし、読むのが遅いというのは、単なるスピードの問題ではありません。 多くの場合、読み方の「クセ」や、文章に対する意識の向け方に原因が隠されています。
例えば、こんな経験はありませんか?
- お子さんが教科書を音読するとき、棒読みになっていて内容が頭に入っていない様子だった。
- 物語を読んでいるはずなのに、登場人物の名前や出来事の順番をすぐに忘れてしまう。
- テストで「問題文をよく読まなかった」というケアレスミスが多い。
これらの背景には、お子さん特有の読み方のパターンが潜んでいる可能性があります。
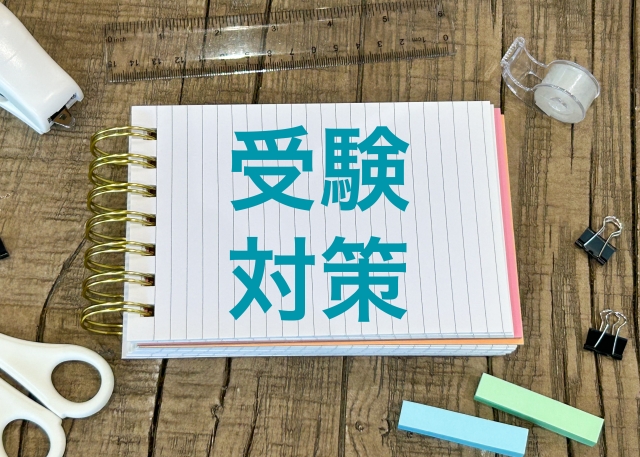
読むのが遅い子にありがちな3つのパターンと、具体的改善策
お子さんの読み方のクセを知るために、まずは以下の3つのパターンに当てはまるかどうかチェックしてみましょう。
① 一語一語を音読してしまうタイプ
このタイプの子どもは、頭の中で文章を「音」として再生するため、意味よりもリズムや発音に意識が集中しがちです。まるで音楽を聴くように読んでしまうため、内容理解がおろそかになり、結果的に読むスピードが遅くなってしまいます。
- 具体例
教科書を指で追いながら、一字一句を丁寧に音読する。
読み終わった後に「何が書いてあったか」と聞くと、うまく答えられない。全体でどんな順番でどんなことが書いてあったかを読み取れていない。 - 改善法
「段落ごとに要点を一言メモ」
段落を読み終えるごとに、その段落で一番重要なことをキーワードとしてノートに書き出します。何回もやる必要はありません。 - ポイント
メモは短く、具体的な言葉で書くように促しましょう。(物語・小説の例:「主人公の名前」「事件が起きた場所」「登場人物の気持ち」など) - 保護者向けアドバイス
最初は一緒にメモを作成し、徐々にヒントを減らしていくと効果的です。 - 期待できる効果
目と頭を連動させることで、文章の内容を意識的に捉えるようになり、理解の速さが向上します。
② 文章の構造を意識できていないタイプ
このタイプのこどもは、文章全体の流れを把握せずに、部分的に読み進めてしまう傾向があります。そのため、文章の中で「迷子」になりやすく、重要な情報を見落としたり、話の筋を見失ったりすることがあります。
- 具体例
説明文や物語文を最初から順番に読んでいるものの、途中で内容がわからなくなり、何度も同じ部分を読み返してしまう。 - 改善法
「はじめ・中・終わり」の流れをつかむ練習
文章全体を「起承転結」や「序論・本論・結論」といった構造で捉える練習をすることで、文章の全体像を把握しやすくなります。 - ポイント
新聞記事や短い物語などを使って、一緒に「はじめに何が書いてあるか」「真ん中で何が起こったか」「最後にどうなったか」を話し合うのも良いでしょう。 - 保護者向けアドバイス
図書館で物語を借りてきて、読み終わった後に簡単なあらすじを親子で語り合うのも効果的です。 - 期待できる効果
文章の構成が見えるようになると、必要な情報に的を絞って読めるようになり、効率的に内容を理解できるようになります。
③ 設問を読まずに本文を読むタイプ
このタイプの子どもは、目的意識がないまま文章を読んでしまうため、時間ばかりかかってしまい、結局何が重要なのかわからなくなってしまうことがあります。
- 具体例
テストで問題文を読む前に、いきなり長文を読み始める。結果、問題を解くために再度長文を読み返すことになり、時間を浪費してしまう。 - 改善法
「設問→本文→解答」の順に読む習慣
問題を解く前に、まず設問を読み、何が問われているのかを明確にしてから本文を読むことで、必要な情報を効率的に探し出すことができます。
※素材文の文字数が多くないと感じ、時間内で解ける場合は本文⇒設問⇒解答の順で問題ありません。 - ポイント
設問を読んだ後に、本文を読む際に注目すべき箇所に線を引いたり、メモを取ったりする習慣を身につけさせましょう。 - 保護者向けアドバイス
家庭学習の際にも、必ず問題を先に読ませるように徹底しましょう。 - 期待できる効果
読む目的が明確になることで、集中力が高まり、必要な情報を効率的に見つけられるようになります。
代表的な例なので、お子様の認知特性や好きなジャンル、その時の気分などで素材文の読み方は変わります。
読むスピードは読解の目的意識で劇的に変わる
読むスピードを上げるために、速読術を試す前に、まず 「どんな目的で読むのか」 を明確にすることが重要です。例えば、レシピを読むなら「材料と手順を把握する」、ニュース記事を読むなら「事件の概要を知る」、小説を読むなら「物語を楽しむ」といったように、目的によって読み方は変わるはずです。そこに気がつくことができれば、子どもはは自然と「早く、正確に」読めるようになるはずです。
言い方が乱暴かどうかは親が子どもに対しての要求が「車のキーを渡して、運転して」と言っていないか?
焦らず、お子さんのペースで
読むのが遅い子ほど、丁寧に考える力を持っている可能性を秘めています。焦らず、お子さんの読み方のクセを見抜き、上記の改善策を参考に、読み方の「整え方」から始めていきましょう。
保護者の皆様へ
お子さんの「読むのが遅い」というお悩みは、決して克服できないものではありません。根気強く、お子さんの成長をサポートしてあげてください。もし、ご家庭でのサポートが難しい場合は、学校の先生や専門機関に相談することも検討してみましょう。読了が第一歩、精読・乱読という問題はその先のことです。また、中学入試における国語の読解は中高校生の現代文レベルであること(特に小説)は念頭においてあげないといけません。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。