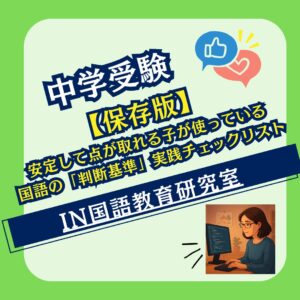文章問題が苦手な子どもの3タイプと学年別アプローチ

「文章問題そのものが苦手な子ども」のタイプを3つに分けて、学年別の対策を紹介します。お子様によってどんなことに興味があり、どんな文章を読むことが好きか嫌いかは個人差があり、日々刺激を受け成長しています。タイプはおおまかにしていますが、今回の内容を読んでいただき、「個別最適化」することで我が子の興味・関心・好奇心を引き出し、読解内容の理解と読解スピードをあげることの両輪バランスをとるきっかけとなると幸いです。
Three Types of Children Who Struggle with Word Problems and Grade-Level Approaches.
言葉の理解が浅いタイプ:苦手意識をなくす親の声掛けと注意点
お子さんが文章を読んでも、内容をしっかり理解できていないように感じたら、それは言葉の意味を十分に理解できていないのかもしれません。でも、焦らないでください!言葉の理解は、少しずつ積み重ねていくもの。まるで、お家の庭に花を植えて、毎日お水をあげるように、根気強く育てていきましょう。
大切なのは、お子さんが「言葉って面白い!」「知っている言葉が増えると、もっと世界が広がるんだ!」と思えるようにサポートすることです。
低学年(小学校1~2年生):絵本と辞書で言葉の探検隊!
- 声掛けのポイント(過去の先輩親子の会話例)
- 「わー、この絵本、すごく面白そう!一緒に読んでみようか?」と、ワクワク感を演出しましょう。
- 読み聞かせの途中で、「あれ?この言葉、ちょっと難しいね。どんな意味だと思う?」と、お子さんの考えを聞いてみましょう。
- もしお子さんが答えられなくても、「大丈夫!一緒に辞書で調べてみよう!」と、辞書を引くことを楽しい冒険のように捉えさせましょう。
- 辞書で意味を見つけたら、「へえー、そういう意味なんだ!〇〇ちゃん(お子さんの名前)も賢くなったね!」と、褒めてあげましょう。
- 「この言葉を使って、何か面白い文章を作ってみよう!」と、言葉遊びに発展させるのもおすすめです。
- 注意点
- 無理強いは絶対にNG!
嫌がるようなら、すぐに切り上げましょう。「また今度、一緒に読もうね」と声をかけて、楽しい思い出として終わらせることが大切です。 - 辞書を引くことを面倒だと思わせないように!
カラフルなイラストがたくさん載っている、子供向けの辞書を選ぶと良いでしょう。書店で候補をいくつか見て子どもが選ぶのがいいです。辞書・四字熟語・ことわざ・慣用句・語彙集を指しますが、塾で使用する教材の補足として使用する順位づけを行うとよいです。 - 完璧主義にならない!
全ての言葉を理解する必要はありません。大切なのは、言葉に興味を持つきっかけを作ることです。 - 親御さんも一緒に楽しむ!
読み聞かせや辞書引きを、親子のコミュニケーションの時間として楽しみましょう。
- 無理強いは絶対にNG!
中学年(小学校3~4年生):新聞コラムで言葉の言い換え名人!
- 声掛けのポイント
- 「新聞に面白いコラムが載ってるよ。一緒に読んでみない?」と、興味を引くように誘いましょう。
- コラムを読んだ後、「この部分、ちょっと難しい言葉で書いてあるね。もっと簡単な言葉で言い換えると、どうなるかな?」と、質問してみましょう。
- お子さんが言い換えた言葉に対して、「なるほど!それは分かりやすいね!」「別の言い方も考えてみようか?」と、一緒に考える姿勢を見せましょう。
- 「〇〇ちゃん(お子さんの名前)の言い換え、すごく上手になったね!まるで言葉の魔法使いみたい!」と、褒めて自信をつけさせましょう。
- 注意点
- 難しすぎるコラムは避ける!
子ども向けの、分かりやすいコラムを選びましょう。 - 正解を押し付けない!
大切なのは、お子さんが自分で考えて、言葉を使いこなせるようになることです。 - 焦らない!
最初はうまく言い換えられなくても、根気強く練習を続けることが大切です。 - 日常生活と結びつける!
例えば、学校で習った言葉を使って、家族に説明してみるのも良い練習になります。小学生新聞は有効なツールの一つです。最初は題材を選んであげるといいでしょう。子どもが自分で興味をもったものは切り取ってノートにはりつけておくのもよいです。
- 難しすぎるコラムは避ける!
高学年(小学校5~6年生):語彙ノートで言葉の達人!
- 声掛けのポイント
- 「〇〇ちゃん(お子さんの名前)も、もうすぐ中学生だね!難しい言葉も、どんどん覚えていこう!」と、成長を促すような声かけをしましょう。
- 「入試問題に出てくるような言葉を集めたノートを作ってみよう!まるで、自分だけの秘密の宝物みたいだね!」と、語彙ノート作りを楽しいものとして捉えさせましょう。
- ノートに言葉を書き出すだけでなく、「この言葉を使って、短い物語を作ってみよう!」「この言葉と似た意味の言葉を調べてみよう!」と、様々な角度から言葉に触れさせましょう。
- 「〇〇ちゃん(お子さんの名前)の語彙力、本当にすごいね!将来が楽しみだよ!」と、褒めてモチベーションを高めましょう。
- 注意点
- 無理な詰め込みはNG!
毎日少しずつ、無理のない範囲で進めましょう。 - 暗記だけに頼らない!
言葉の意味を理解し、文脈の中でどのように使われているかを理解することが大切です。 - 例文をたくさん読む!
実際に言葉が使われている文章を読むことで、言葉のニュアンスを理解することができます。自分で例文をつくれることが理想です。 - ゲーム感覚で取り組む!
例えば、言葉を使ったクイズを出し合ったり、クロスワードパズルを解いたりするのも効果的です。自問自答クイズができるようになると文章を読むスピードが上がってくる子どもが多いです。
- 無理な詰め込みはNG!
最後に、一番大切なことは、お子さんのペースに合わせて、根気強くサポートすることです。言葉の理解は、一朝一夕に身につくものではありません。焦らず、ゆっくりと、お子さんの成長を見守ってあげてください。そして、言葉を学ぶ楽しさを教えてあげてください。きっと、お子さんは言葉の力を身につけ、自信を持って未来に向かって歩んでいけるはずです。
想像がふくらまないタイプ:物語の世界へ導く親の声掛けと注意点

物語を読んでも、登場人物の気持ちがピンとこなかったり、場面が頭に浮かんでこなかったりするお子さん。まるで、白黒テレビを見ているように、物語の世界が少しぼやけてしまっているのかもしれませんね。でも大丈夫!想像力は、色鉛筆のように、少しずつ色を塗り重ねていくことで、鮮やかになっていくものです。
大切なのは、お子さんが「物語って面白い!」「登場人物と一緒にドキドキワクワクできるんだ!」と思えるように、物語の世界への扉を開いてあげることです。
低学年(小学校1~2年生):読み聞かせ後の「心のスケッチ」!
- 声掛けのポイント(過去の先輩親子の会話例)
- 「今日はどんなお話かな?一緒に冒険に出かけよう!」と、読み聞かせを冒険の始まりのように演出しましょう。
- 読み聞かせが終わった後、「〇〇ちゃん(お子さんの名前)は、この時、主人公はどんな顔をしていると思う?」と、気持ちを言葉にするきっかけを与えましょう。
- もしお子さんが答えに困ったら、「嬉しい時はどんな顔かな?」「悲しい時はどんな顔かな?」と、ヒントを出してあげましょう。
- 「へえー、〇〇ちゃんはそう思ったんだ!面白いね!」「主人公は、きっと〇〇ちゃんの優しい顔を見て、元気が出たと思うよ!」と、お子さんの想像力を肯定的に評価しましょう。
- 絵を描くのが好きなお子さんには、「主人公の顔を絵に描いてみよう!」と、表現方法を広げてあげるのもおすすめです。
- 注意点
- 正解を求めない!
想像力に正解はありません。お子さんが自由に想像することを尊重しましょう。 - 抽象的な質問は避ける!
「どんな気持ちだった?」と聞くよりも、「どんな顔をしていたと思う?」と、具体的な質問の方が答えやすいでしょう。抽象と具体の違いが自然にわかるようになります。 - 読み聞かせを一方的にしない!
途中で「〇〇ちゃんは、どう思う?」と、お子さんに問いかけながら読み進めるのも効果的です。どう思うまえに考えていること自体に価値を置くことからはじめるといいです。 - 親御さんも一緒に楽しむ!
読み聞かせを、親子の温かいコミュニケーションの時間として楽しみましょう。
- 正解を求めない!
中学年(小学校3~4年生):セリフ・行動・気持ちの「心の整理整頓」!
- 声掛けのポイント(過去の先輩親子の会話例)
- 「物語に出てくる登場人物って、色々なことを考えているんだね。〇〇ちゃん(お子さんの名前)も、登場人物の気持ちを整理してみよう!」と、ノート作りを整理整頓のように捉えさせましょう。
- ノートに「セリフ」「行動」「気持ち」の3つの項目を作り、「このセリフを言った時、主人公はどんな気持ちだったと思う?」「この行動には、どんな意味があると思う?」と、質問してみましょう。
- お子さんが考えたことを、「なるほど!そういうことか!」「〇〇ちゃんの考え、すごく面白いね!」と、肯定的に評価しましょう。
- 「もし〇〇ちゃんが主人公だったら、どうする?」と、自分だったらどうするかを考えさせることで、共感力を高めることができます。
- 注意点
- ノート作りを強制しない!
嫌がるようなら、別の方法を試してみましょう。素材文に書き込む子どもが多いです。見返すときに書き込みから思い出しやすいというのが理由です。 - 細かすぎる分析は避ける!
- 大切なのは、物語全体の流れを理解することです。
- 登場人物の気持ちを決めつけない! 色々な解釈があることを伝え、お子さんの自由な発想を尊重しましょう。
- 物語の内容に合わせて、ノートの形式を変える!
例えば、登場人物が多い物語では、人物関係図を作ってみるのも良いでしょう。これは中学高校へ進学した際の古文や漢文の人物関係の把握にも大きく役立ちます。
- ノート作りを強制しない!
高学年(小学校5~6年生):心情変化と場面転換の「心の地図作り」!

- 声掛けのポイント(過去の先輩親子の会話例)
- 「物語って、まるで迷路みたいだね。〇〇ちゃん(お子さんの名前)も、物語の迷路を地図にしてみよう!」と、構造的読解を地図作りのように捉えさせましょう。
- 物語の重要な場面をピックアップし、それぞれの場面で登場人物の気持ちがどのように変化したかを、図でまとめてみましょう。
- 「この場面から、次の場面に変わる時、何があったと思う?」「この変化は、物語全体にどんな影響を与えていると思う?」と、物語の構造を理解させる質問をしましょう。
- 「〇〇ちゃんの作った地図、すごく分かりやすいね!まるで物語の案内人みたいだ!」と、褒めて自信をつけさせましょう。
- 注意点
- 難易度が高すぎる物語は避ける!
複雑な構造の物語は、最初から取り組むのは難しいでしょう。 - 図の形式にこだわりすぎない!
大切なのは、物語の構造を理解することです。 - 一人で抱え込ませない!
困った時は、親御さんが一緒に考え、ヒントを与えましょう。 - 物語を読み終わった後だけでなく、読み進める中で図を更新していく!
図でなく文字やト書きのように表現するなどケースは様々ですが、リロード感覚をもつことで、物語の理解がより深まります。
- 難易度が高すぎる物語は避ける!
最後に、一番大切なことは、お子さんが物語の世界を楽しむ気持ちを育むことです。 想像力は、知識や経験と結びつくことで、豊かに広がっていきます。色々な物語に触れさせ、様々な体験をさせることで、お子さんの想像力を育ててあげてください。そして、物語を通して、お子さんの心を豊かにしてあげてください。きっと、お子さんは物語の世界を自由に旅し、豊かな感性を持って未来に向かって歩んでいけるはずです。
読む目的が曖昧なタイプ:羅針盤を持って読書!親の声掛けと注意点
文章を読んでいるけれど、何が大切なのか、何を理解すればいいのか、ぼんやりとしてしまうお子さん。まるで、羅針盤を持たずに広い海を航海しているように、どこに向かっているのか分からなくなってしまっているのかもしれませんね。でも大丈夫!読む目的を明確にすることで、羅針盤を手に入れ、迷うことなく目的地にたどり着けるようになります。
大切なのは、お子さんが「読むって面白い!」「目的を持って読めば、もっと深く理解できるんだ!」と思えるように、読む目的を意識させることです。
低学年(小学校1~2年生):物語の探偵になって「誰が」「何をした」を追え!
- 声掛けのポイント(過去の先輩親子の会話例)
- 「今日はどんなお話かな?〇〇ちゃん(お子さんの名前)は、物語の探偵になって、事件を解決しよう!」と、読むことをゲームのように捉えさせましょう。
- 読み聞かせの後、「このお話の中で、一番大事な人は誰かな?」「その人は、何をしたのかな?」と、質問してみましょう。
- もしお子さんが答えに困ったら、「主人公は、どんなことを考えていたと思う?」「主人公の行動は、物語にどんな影響を与えたと思う?」と、ヒントを出してあげましょう。
- 「〇〇ちゃんは、名探偵だね!」「〇〇ちゃんのおかげで、事件が解決したよ!」と、褒めて自信をつけさせましょう。
- 絵を描くのが好きなお子さんには、「主人公がしたことを絵に描いてみよう!」と、表現方法を広げてあげるのもおすすめです。
- 注意点
- 難しすぎる物語は避ける!
シンプルな物語から始めましょう。 - 質問攻めにしない!
楽しく読み聞かせをすることが大切です。 - 正解を押し付けない!
お子さんの考えを尊重しましょう。その後、こういう考え方もあるねとちょっと足してあげることです。 - 親御さんも一緒に楽しむ!
読み聞かせを、親子の楽しい時間として過ごしましょう。
- 難しすぎる物語は避ける!
中学年(小学校3~4年生):なぜ?なぜ?「考えるエンジン」を始動!
- 声掛けのポイント(過去の先輩親子の会話例)
- 「物語に出てくる登場人物って、色々な理由で行動するんだね。〇〇ちゃん(お子さんの名前)も、登場人物の行動の理由を考えてみよう!」と、考えることを楽しいパズルのように捉えさせましょう。
- 物語を読んだ後、「なぜ、主人公はそうしたんだろう?」「もし〇〇ちゃんが主人公だったら、どうする?」と、問いかけてみましょう。
- お子さんが考えたことを、「なるほど!そういうことか!」「〇〇ちゃんの考え、すごく面白いね!」と、肯定的に評価しましょう。
- 「〇〇ちゃんは、考える力がすごいね!」「〇〇ちゃんの考えを聞いて、私も勉強になったよ!」と、褒めて自信をつけさせましょう。
- 注意点
- 答えをすぐに教えない!
自分で考える時間を与えましょう。「沈黙は思考のゴールデンタイム」です。フリーズしていたら、まずはフリーズの原因を聞き出すことから会話を進めることです。 - 抽象的な質問は避ける!
具体的な場面を例に出して質問しましょう。何度も書いています。 - 批判的な言葉は使わない!
お子さんの考えを尊重しましょう。これも何度も書いています。 - 物語の内容に合わせて、質問を変える!
例えば、友情がテーマの物語では、「なぜ、二人は仲良くなったんだろう?」と質問してみましょう。テーマとなる熟語は友情・愛情・摩擦・葛藤・正義・平和など、魔法と同じ感覚で引き出しを作っておくことです。
- 答えをすぐに教えない!
高学年(小学校5~6年生):戦略的読解で「宝の地図」を完成させよう!
- 声掛けのポイント(過去の先輩親子の会話例)
- 「テストの問題って、まるで宝の地図みたいだね。〇〇ちゃん(お子さんの名前)も、問題という宝の地図を使って、本文という宝島から宝物を探し出そう!」と、戦略的読解を宝探しのように捉えさせましょう。
- 問題を最初に読み、何を問われているのかを理解してから、本文を読みましょう。
- 本文を読む際には、問題に関係する箇所に線を引いたり、メモを取ったりしましょう。
- 問題を解き終わったら、なぜその答えを選んだのか、根拠を説明してもらいましょう。
- 「〇〇ちゃんの宝探し、すごく上手になったね!」「〇〇ちゃんのおかげで、たくさんの宝物を見つけることができたよ!」と、褒めて自信をつけさせましょう。
上記すべて当てはまることはありません。改善できる部分で自信がついたものを定着させることです。線を引きすぎて理解が整理できない場合や、線を引くことが作業になる場合であれば、時間がかかるだけなので、線を引かない子どももいます。一律の解き方の時代ではありませんので個別最適化しながら最適解をたくさんつくれるように促してあげてください。
- 注意点
- 問題を解くことだけを目的にしない!
本文の内容を理解することも大切です。 - 時間を意識させすぎない!
焦らず、じっくりと取り組ませましょう。 - 難しい問題ばかり解かせない!
易しい問題から始め、徐々に難易度を上げていきましょう。 - 戦略的読解を強制しない!
他の方法が合っている場合は、無理強いしないようにしましょう。
- 問題を解くことだけを目的にしない!
塾の教材によって、全部やった方がよいもの、問題を厳選してやるものなど、先生の指示にまずはやり切ることです。アウトプットができていないのか、できていても演習量、問題量が足りないのかを判断する必要があります。先生に相談し、解決が難しいようでしたらプロに相談しましょう。算数と国語の得点は同じ学校が多いですので、算数と国語の成績差がありすぎる場合は縮める必要があることと、悪くとも国語の得点率は50%はとれるようにならないと他の教科も総じてよくない場合が多いと個人的に感じます。
最後に、一番大切なことは、お子さんが「読む」ことの楽しさを忘れさせないことです。
読む目的を意識することは大切ですが、それ以上に、物語の世界に浸ったり、新しい知識を得たりする喜びを感じることが重要です。色々なジャンルの本を読ませ、様々な情報に触れさせることで、お子さんの知的好奇心を刺激し、読むことの楽しさを教えてあげてください。きっと、お子さんは羅針盤を手に入れ、目的を持って読書を楽しみ、未来に向かって大きく成長していくでしょう。
まとめ
お子さんの読解力アップには、タイプ別の声かけが重要です。言葉の理解が浅い場合は、問題集や塾の教材、絵本や新聞で語彙を増やし、想像力が乏しい場合は、読み聞かせや心情整理で感情を豊かにしましょう。高学年になると読む目的が曖昧な場合は、設問を意識した戦略的読解の練習が必要です。焦らず、お子さんのペースに合わせて、言葉の面白さや物語の楽しさを伝えることが大切です。

読解や記述でお困りの場合は、IN国語教育研究室までご相談ください。