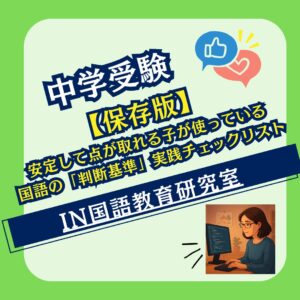3連休中の模試連続は「入試本番のリハーサル」親子で整える4つの視点

3連休に模試が立て続けに行われると、お子様はもちろんのこと、それをサポートする親御さんにとっても、疲労が蓄積するのは当然のことでしょう。慣れない会場への送り迎え、お弁当の準備、そして何よりも、お子様の頑張りを間近で見守る精神的な負担は、想像以上かもしれません。週末はゆっくり休みたい、そんな気持ちになるのも無理はありません。Taking practice exams continuously over the three-day weekend: “A rehearsal for the actual entrance exam” — Four perspectives for parents and children to prepare together.
しかし、この一見過酷にも思えるスケジュールこそが、実は1.2月の本番に向けた(地域によって異なりますね)、またとないシミュレーションの機会なのです。入試本番は、多くの場合、2〜3日連続で行われます。それは、単に知識を問われるだけでなく、体力、集中力、そして何よりも、精神的なタフさを試される時間です。
1日目の結果に一喜一憂し、2日目に引きずってしまう。そんな経験は、多くの方が経験するものです。しかし、入試本番では、過去の結果に囚われず、常に「今」に集中し、最高のパフォーマンスを発揮する必要があります。そのためには、1日ごとに気持ちをリセットし、新たな気持ちで次の日に臨む「切り替え力」が不可欠となるのです。
今回の模試は、まさにその「切り替え力」を鍛える絶好のチャンスです。連日の模試を通して、お子様は疲労を感じながらも、どのように集中力を維持し、気持ちを切り替えていくかを、実践的に学ぶことができます。そして、親御さんは、その過程をサポートしながら、お子様のメンタル面での成長を促すことができるのです。
模試の結果に目を向けるだけでなく、お子様がどのように困難を乗り越え、成長していくのか。そこに焦点を当てることで、この3連休は、単なる疲労困憊の期間ではなく、本番に向けた貴重な準備期間へと変わります。
この3連休を、お子様と共に、戦略的に、そしてポジティブに乗り越えましょう。そして、その先に待つ、輝かしい未来へと繋げていきましょう。…次回の模試に向けて、今、私たちができることは何でしょうか?

①移動時間は「集中力の土台」になる
試験会場までの移動時間は、ただの移動ではなく、心を整える貴重な時間。朝のルーティンを整え、焦らず出発することで、子どもの心に余裕が生まれます。移動中は、軽い復習かリラックスかを子ども自身に選ばせるのがポイント。主体的な選択が、試験への集中力と自信につながります。親は選択肢を提示し、最終判断は子どもに委ねましょう。
模試の復習は、単なる作業ではありません。自分の思考プロセスを理解し、弱点を克服し、「次に同じミスをしない力」を育てるための、戦略的な時間です。親御さんは、答えを教えるのではなく、お子様の考えを引き出すように質問し、対話を促しましょう。模試を「学びの宝庫」に変え、お子様の真の学力を向上させましょう。
②食事は「脳と心のエネルギー補給」
模試当日の食事は、集中力と安定したパフォーマンスを支える重要な要素。血糖値の急上昇を避けるため、玄米おにぎりやゆで卵、バナナなど、消化が良く腹持ちの良いメニューがおすすめです。模試を通して、子どもに合った食事の組み合わせを見つけておくことで、本番の食事戦略にも活かせます。食後の体調や集中力を記録しておくと、さらに効果的です。ご家庭なりのエネルギー補給について親子で話し合ってみましょう。
③休息は「次へのエネルギーを育てる時間」
試験後は、結果よりもまず休息。点数に一喜一憂せず、「お疲れさま」の一言で子どもの努力を認めましょう。30分の仮眠や軽いストレッチ、音楽などで心身をリフレッシュすることで、次の試験や学習へのエネルギーがチャージされます。分析は翌日に回し、冷静な視点で振り返るのがベスト。親の傾聴姿勢が、子どもの安心感と回復力を高めます。
④復習は「思考力を育てる宝の時間」
模試の復習は、答え合わせではなく「思考の再現」が鍵です。「なぜ間違えたのか、どう考えたのか」を言葉にすることで、思考の癖や弱点が見えてきます。親は答えを教えるのではなく、問いかけを通して子どもの考えを引き出しましょう。記録を残し、次の模試に活かすことで、「同じミスを繰り返さない力」が育ちます。復習は、真の学力を伸ばす時間です。模試のやりっぱなしだけは避けましょう。入試後はやり直しはしなくても構わないと個人的には思いますなぜなら、いったんやりきったのですから。個人差はあると思いますので家族で話し合ったり、信頼できる先生に都度、相談しましょう。
国語:試験中と解き直しで特に注意すべきこと
試験中:時間配分と「保留」の勇気
~時間配分を制する者が国語を制す!「保留」戦略で得点力UP~
国語は、問題文を読むのに時間がかかりやすく、時間配分が非常に重要です。特に、現代文、古文、漢文、記述問題など、様々な形式の問題が出題されるため、それぞれの問題にどれくらいの時間をかけるかを事前に決めておくことが大切です。
- 時間配分計画
大問ごとに目標解答時間を設定し、試験開始前に確認しましょう。 - 「保留」の勇気
どうしても解けない問題や、時間がかかりそうな問題は、潔く「保留」し、先に解ける問題から取り組みましょう。後で見直す時間を確保することで、焦りを軽減し、得点力を高めることができます。どの問題を保留にするのか、または飛ばすのかは個人差がありますが、記述は書き切る必要があります。△の積み重ねで得点をとることが合格への近道です。 - 記号書き間違い防止
時間切れで焦って記号を書き間違えてしまうことがないように、こまめに問題用紙にマークするように心がけましょう。
解き直し:なぜ間違えた?「思考の迷子」を解消する
~解き直しは「思考の迷子」探し!正解への道筋を再構築せよ!~
国語の解き直しは、単に正解を確認するだけでなく、なぜ間違えたのか、どこで思考が迷子になったのかを徹底的に分析することが重要です。
- 「思考の迷子」特定
問題文のどの部分を読み間違えたのか、どの選択肢で迷ったのか、なぜその選択肢を選んでしまったのかを具体的に分析しましょう。 - 根拠の明確化
正解の根拠を、問題文から正確に抜き出す練習をしましょう。「なんとなく」ではなく、明確な根拠に基づいて解答できる力を養うことが重要です。 - 語彙力強化
知らない言葉や意味があいまいな言葉は、必ず辞書で調べ、意味を理解するようにしましょう。語彙力は、読解力を高める上で不可欠です。 - 記述問題の添削
記述問題は、自己採点だけでなく、塾や家庭教師の先生に添削してもらうことをお勧めします。客観的な視点から、論理構成や表現方法の改善点を見つけることができます。
国語は、時間配分と解き直しが合否を分けると言っても過言ではありません。試験中は、時間配分を意識し、「保留」の勇気を持つこと。解き直しでは、なぜ間違えたのかを徹底的に分析し、思考の迷子を解消することが重要です。これらのポイントを意識して、国語の得点力を高めましょう。
まとめ
3連休模試は、単なる学力テストではなく、入試本番を「体で覚える」ための、実践的なトレーニング期間です。移動、食事、休息、復習までの流れを整え、親子で協力して“本番力”を磨き上げましょう。この3日間を最大限に活用し、お子様を合格へと導きましょう。