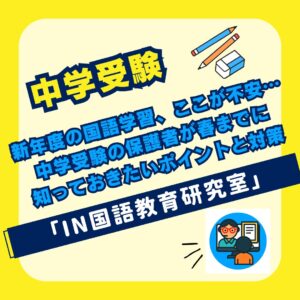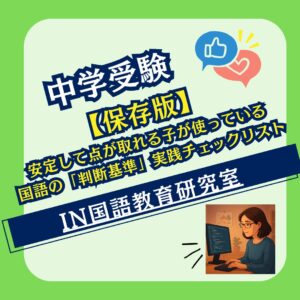朝の過ごし方で学習効率が変わる!

「夜に勉強させるより、朝に強い子どもに育てたい」――そんな声を保護者からよく聞きます。実際に、朝の過ごし方次第で学習効率が大きく変わります。夜の帳が下りる頃、机に向かうわが子の姿に、ため息をついたことはありませんか? 眠そうな目をこすり、集中力も途切れ途切れ…。そんな光景を目の当たりにするたび、「もっと朝に集中して勉強してくれたら…」と願うのは、決してあなただけではありません。「夜に勉強させるより、朝に強い子どもに育てたい」――そんな切実な声は、日々、多くの保護者の方々から聞こえてきます。
How you spend your mornings affects your learning efficiency!
「なぜ、朝なのでしょうか?」 それは、一日の始まりである朝こそ、脳が最もクリアで、吸収力も高い時間帯だからです。しかし、ただ早く起きれば良いというわけではありません。朝の過ごし方次第で、その学習効率は天と地ほどに変わってしまうのです。まるで魔法のように、朝の時間を有効活用することで、お子様の学習能力は飛躍的に向上する可能性を秘めているのです。さあ、一緒に朝の過ごし方を見直し、お子様の眠れる才能を開花させてみませんか?
朝の声かけで「安心感」と「やる気スイッチ」を入れる
子どもは「焦らせる言葉」に弱いものです。大人が急かすことで一時的に行動はするかもしれませんが、心の中では焦りと反発が生まれます。逆に「安心する言葉」をかけると、自然と行動に移しやすくなります。
- NG例:「早く!」「また遅れるよ!」「どうしてできないの?」
- OK例:「昨日より1問だけ進めよう」「ここまでできたら朝ごはんにしよう」
あるご家庭では、朝の計算問題を「一緒にストップウォッチで測ろう」と声をかけました。ゲーム感覚が子どものやる気を刺激し、短時間でも集中する習慣がついたのです。きりが悪いときにどうするかで子どもが納得するまで何度も話し合ったそうです。
専門家の視点から言うと、国語の抜き出し問題や記述問題は“焦り”で読み落としが増える傾向があります。朝に安心感を持って勉強を始めることで「設問を丁寧に読む」習慣がつきやすいのです。
生活リズムは「睡眠の確保」が第一
小学生にとって最も重要なのは「十分な睡眠」です。夜遅くまで机に向かっている子どもは、一見努力しているように見えますが、翌朝は眠くて集中できず、効率は大幅に下がります。
- 就寝時間が遅い場合、翌日のパフォーマンスはテスト結果にも直結します。
- 小学6年生の理想的な睡眠時間は 7~8時間前後。
ある生徒は、夜11時まで勉強していましたが、成績が伸び悩んでいました。保護者と相談し「22時就寝・6時起床」に切り替えたところ、朝の演習の質が明らかに変わり、模試の国語偏差値が5ポイント上がりました。
生活リズムを整えることは、単なる「健康管理」ではなく、学習効率そのものを最大化する投資です。
家庭での成功例と失敗例
私が指導してきたご家庭の中で、印象的なエピソードを紹介します。成功と失敗、両方の経験から得られた教訓は、きっと皆様のお子様を導く羅針盤となれば幸いです。
成功例:親子の絆を深め、学力も向上させた「朝の音読習慣」
あるご家庭では、毎朝たった10分だけ、親子で音読をする習慣を取り入れました。最初は国語の教科書から始め、徐々にステップアップ。入試過去問の文章にも挑戦するようになりました。驚くべきことに、声に出して読むことで、お子様の読解スピードが目に見えて向上したのです。さらに、記述問題で重要となる「根拠を押さえる力」も飛躍的に伸びました。
この成功の鍵は、単に音読をしたことだけではありません。親御様がお子様と一緒に音読することで、親子のコミュニケーションが深まり、学習に対するモチベーションが向上したのです。まるで、二人三脚でゴールを目指すように、互いに励まし合い、支え合うことで、困難な課題も乗り越えることができたのです。朝の穏やかな時間の中で、親子の絆を深めながら、学力も向上させる。まさに理想的な成功例と言えるでしょう。
失敗例:プレッシャーが勉強嫌いを招いた「朝の過去問チャレンジ」
一方で、残念な結果に終わってしまったご家庭もあります。「朝は頭が冴えているから」という理由で、いきなり過去問を1セット解かせたのです。しかし、お子様は予想以上のプレッシャーを感じ、朝から機嫌が悪くなってしまいました。親御様も焦る気持ちから、つい厳しくなってしまい、親子ゲンカが勃発。結果的に、お子様は勉強そのものが嫌いになってしまったのです。
この失敗から学べる教訓は、「朝は短時間で達成感を得ることが大切」ということです。朝の貴重な時間を、プレッシャーのかかる課題に費やすのではなく、成功体験を積み重ねることで、学習意欲を高めるべきなのです。過去問に挑戦するのは、基礎がしっかりと身についてから。まずは、簡単な問題や、興味のある分野から始めるのが賢明です。朝は、お子様の「やる気スイッチ」を入れるための時間。焦らず、じっくりと、お子様のペースに合わせて進めていくことが重要です。
30年の指導経験から言えることは、お子様の個性や性格を理解し、それに合わせたアプローチをすることが、成功への近道だということです。
成功例を参考に、失敗例を反面教師として、お子様にとって最適な学習方法を見つけてあげてください。
4.朝学習の工夫:国語力を伸ばす具体的実践
国語における朝学習の具体的メニューを挙げてみます。
05分:語彙カードで昨日の復習
10分:短文読解または漢字演習
05分:親子で文章音読
合計20分以内でも、継続すれば驚くほどの成果が出ます。重要なのは「続けられる仕組み」を作ること。例えば、終わったらカレンダーにシールを貼る、達成感を見える化するなど、小学生らしい工夫が効果的です。
5.保護者へのアドバイス
保護者にとって朝は戦場のような時間ですね。弁当作り、身支度、出勤準備。その中で子どもの勉強を見守るのは容易ではありません。だからこそ、完璧を目指す必要はありません。
「毎日やらなきゃ」ではなく「できた日はラッキー」と考える。
親が全部やるのではなく「声かけ」だけに集中する。
叱る朝を減らすことが、子どもの一日の集中を守る。
「朝勉強=家庭の安心感を育てる時間」と考えると、保護者自身の心も軽くなります。
1日子どもを起こしてから何回注意しているかカウントしてみましょう。朝学校に行くまで20回は軽く越えていませんか?どれだけ子どもの自己肯定感を奪っているかを数値化してみましょう。
とある保護者の場合
ああ、耳が痛い…! 確かに、私もついついやってしまっているかも。一日、子どもを起こしてから何回「早く!」「何してるの!」「さっさとやらなきゃ!」って言ってるか、冷静にカウントしてみると…想像以上に多いんですよね。3回どころじゃない。朝、学校に行くまでの短い時間で、20回なんて軽く超えてるかもしれない。
そう考えると、ゾッとするんです。毎日、そんなにたくさんの言葉で、子どもの心を急かして、追い詰めてしまっているのかと。どれだけ子どもの自己肯定感を奪っているんだろう…って。反省しかありません。もっと、穏やかに、寄り添って、子ども自身のペースを尊重してあげなきゃいけないのに。ついつい、自分の焦りや不安をぶつけてしまっているのかもしれません。明日からは、深呼吸して、言葉を選ぶように心がけよう。

6.まとめ
朝の過ごし方は、子どもの学習効率を左右する大きな要因です。
安心する声かけでやる気を引き出す
睡眠を最優先して生活リズムを整える
小さな達成感で自信を積み重ねる
この3つを意識すれば、国語だけでなく受験全般の力が伸びていきます。
受験直前期になるほど、夜遅くまでの勉強に偏りがちです。しかし、本当に結果を左右するのは「朝の習慣」です。
ぜひ今日から、「叱らない朝」「安心できる朝」を家庭でつくってください。それが子どもの集中力と学力を大きく伸ばす第一歩になります。
※この記事は IN国語教育研究室 の取り組みの一部です。
ご興味のある方は、ぜひホームページから体験授業にお申し込みください。
IN国語教育研究室のオンラインサービスとは?

1.保護者様向けの学習相談
週1回、月1回の選択
2.お子様の国語力向上を目的とした授業(答案分析から解答改善を行います)
レギュラー授業週1回、スポット授業:適時
Zoomにてオンラインサービスを提供しております。入試情報だけでなく、学びに関するあらゆる疑問や不安に寄り添い、信頼できる学習伴走者として共に歩みます。お困りごとがありましたら、一緒にお子様の可能性を広げていきましょう。
お問い合わせはコチラ→IN国語教育研究室
お子様向けは
・6年生は募集はあと1名です。主に過去問対策です(時期が時期なので現在は受講の制約条件があります。)
・3~5年生は2学期の学習ステージが上がりますので、週のテストや月例のテスト、外部模試の直しと改善、または消化できていない塾での教科書や特定分野の授業をカスタマイズしながら改善を積み重ねます。
成績を伸ばす鍵は、テスト後の振り返りです。IN国語教育研究室では、お子様に合った指導と保護者向け相談で、学習効率の向上をサポートしています。 Zoomにて1:1の個別指導を行っています。