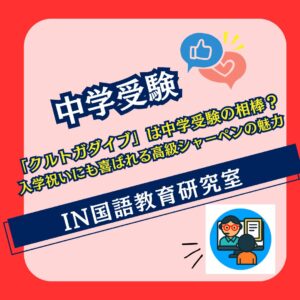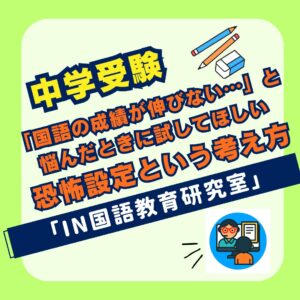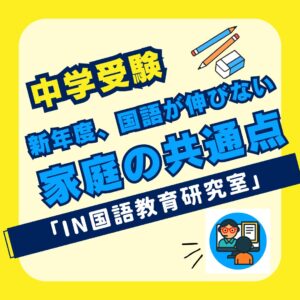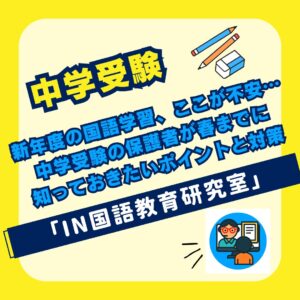過去問演習を「伸び」につなげる!国語復習の家庭サポート術

中学受験を控える家庭で、この時期に大きなテーマとなるのが「過去問演習」です。多くのご家庭では、過去問を解くたびに「今日は何点取れた?」と点数を重視しがちです。しかし、実際に伸びていく子は、点数の上下に一喜一憂するのではなく、復習に時間をかける子です。国語はとくに「ただ解いて終わり」にしてしまうと、同じようなミスを何度も繰り返してしまいます。親の伴走によって、過去問を“得点力に変えるトレーニング”へと進化させることができます。
Connecting past exam practice to ‘growth’! Home support techniques for reviewing Japanese.
よくある「過去問復習の落とし穴」
まずは、保護者が知っておきたい「ありがちな失敗パターン」を整理しましょう。

1. 点数だけ見て終わってしまう
「今日は合格最低点を超えた」「まだまだ足りない」など、点数に意識が集中してしまうケースです。
点数はもちろん重要ですが、復習で得られる気づきに比べれば、点数は単なる“結果”にすぎません。
2. 解説を読んで理解したつもりになる
解答解説を読んで「なるほど、そういうことか」と納得してしまい、それ以上深掘りしないケース。
これでは、いざ同じような設問が出ても、また同じミスを繰り返すことになります。
3. 子ども任せにしてしまう
「復習しておきなさい」と丸投げにしてしまうと、まだ学習の仕方が確立していない子どもは、何をどう復習すればいいのかわからず、形だけで終わってしまうことが多いのです。
効果的な復習3ステップ
過去問演習を本当に「力」に変えるためには、次の3つのステップを意識することが大切です。

ステップ1:ミスの原因を分類する
国語の設問ミスには必ず原因があります。
- 語彙不足
- 本文理解不足
- 設問の読み取り不足
- ケアレスミス
この4つに整理するだけでも、ミスのパターンが見えてきます。
「語彙が弱いなら日々の語彙強化へ」「設問読み違いなら設問文を声に出して読む」など、対策が具体化できるのです。
ステップ2:根拠を本文から確認する
「なぜその答えになるのか」を必ず本文に戻って確認する習慣をつけましょう。
親の声かけとしては、
- 「どの文を根拠にしたの?」
- 「その言葉は本文にちゃんとある?」
と問いかけることが効果的です。
ステップ3:“次に活かす行動”を決める
最後に大切なのは「次に同じタイプの問題が出たらどうするか」を書き出すことです。
- ケアレスミス → 「必ず見直しをする」
- 設問読み違い → 「設問文に線を引く」
- 語彙不足 → 「知らなかった語彙をノートにまとめる、または書き込む」
この「行動宣言」が次の演習につながります。
子どもにより個性があるので、矯正、強制しないことです。
家庭での声かけの工夫
復習の場で、親の言葉は子どものやる気に大きく影響します。
正解・不正解を責めるのではなく、「気づき」と「改善」へと導く声かけを意識しましょう。

具体的な声かけ例
- 「どの言葉を根拠にしたの?」
- 「もし同じ問題が出たら、どう答える?」
- 「これはケアレス?それとも読み取りの問題?」
- 「次に気をつけたいことを一つだけ決めてみよう」
このように「問いかけ」を通じて子どもに考えさせることで、主体的な学びにつながります。
復習が家庭に与える副次効果
過去問の復習は、単に学力を伸ばすだけでなく、家庭に良いリズムを生みます。
- 子どもが「考えを説明する力」が伸びる
- 親は「どこでつまずきやすいか」を把握できる
- 「できた・できなかった」の結果だけでなく「学びの過程」を共有できる
こうした積み重ねが、親子にとっても安心感を与え、受験期を乗り越える大きな支えとなります。
復習チェックのやり方
ここまでお話しした3ステップを日常に取り入れるために、以下を参考にししてください。
- 設問番号ごとに正誤をチェック
- 根拠とした本文を記録
- 気づきや迷いを整理
- ミスの原因を分類(語彙/本文理解/設問/ケアレス)
- 次につなげる工夫を記入
- 親のコメント欄つき
書き出す、書き込むことで復習が「見える化」し、繰り返すことで「自分の弱点の傾向」がはっきり見えてきます。
まとめ
過去問演習は「点数を測るための道具」ではなく、「伸びの種を見つけるための道具」です。家庭での伴走によって、その種は確実に芽を出し、入試本番につながります。点数よりも大切なのは「なぜ間違えたか」「次にどう生かすか」を子どもと一緒に考えること。それを支えるのが「復習チェック」です。時間は無限にあればいいですが、限られています。そして、集中力も必要です。得点の大きなものや失点だけに注目すると効果的です。