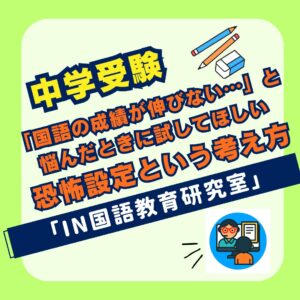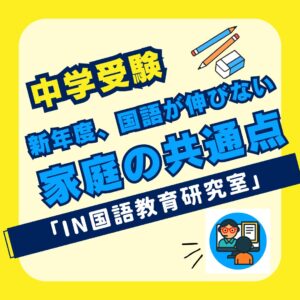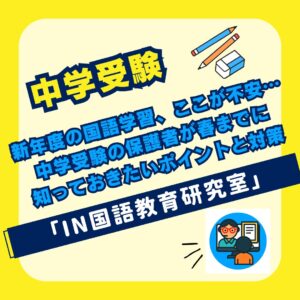国語の記述力は一生もの!思考を磨く練習の手順とコツ

国語の記述力は単なる受験対策だけでなく、人生において大切なスキルです。文章を読み解き、自分の言葉で要点を整理して伝える力は、社会に出た後も必要不可欠。本記事では、具体的な記述の手順を分かりやすく解説し、受験生と保護者が一緒に学べる方法を紹介します。このブログを参考にすることで、国語の成績向上はもちろん、将来にも役立つ思考力を養うことができます。
The ability to write in the national language is invaluable for a lifetime! Steps and tips for practicing to refine your thinking.
題名の重要性
題名は文章全体のテーマを表しています。最初に題名を読んで、筆者が何を伝えたい本なのかを理解してから素材文を読むように努めることが重要です。説明的文章では要旨や論旨、文学的文章では主題や人物像を意識できるヒントになることもあります。素材文を読む前に題名を読む癖をつけることです。
素材文と設問の読解方法

素材文を丁寧に読み、設問の内容を意識させましょう。設問に「なぜ」や「どのように」が含まれている場合、具体的な行動や原因を探すことが求められます。素材文を飛ばし読みせず、傍線部を中心に関連する文章を確認するのがポイントです。特に冒頭部はゆっくりと読むことをお勧めします。
傍線部から根拠を探すスキル
「傍線部○○は何を指しているか」などの設問では、周囲の文章に根拠があることが多いです。この根拠を探すには、指示語や接続詞を手がかりにします。例えば、「この理由」という部分があれば、その直前を探し、何を指しているのかを確認します。丁寧に根拠を探す練習は必要不可欠です。慣れれば時間はかかりません。設問が多いテストの処理の問題と課題が見えてきます。
記述の要素を整理する
たとえば素材文が物語・小説では本文中の重要な要素を見つけたら、「誰が」「何を」「どうした」を順序立てて整理します。この段階で思考の型を使い、「因果関係」「対比」「置換」「具体と抽象」等を明確にしましょう。この整理が記述問題の核となります。
文章構成を考える
次に、文章の構成を練ります。解答全体がスムーズに流れるよう、接続詞や助詞を活用して「だから」「例えば」「から」「ので」などを使い論理的に展開します。また、書き終わった後は「まとめ型」(結論だけ書く型)になっていないか確認し、具体例や根拠をしっかり補足します。
設問の結びをどうしなければならないのかが一番大切です。
題名→素材文→設問→傍線部→素材文から解答の根拠探し→記述の要素を見つける→思考の型を使う→文章構成を考える→制限字数があれば0.8をかけ、字数以上を書く。問題作成者が何を書いてほしいのかをざっくりと方針をたてて、答えを書く前に素材文のどこに要素があったかを考えることです。
まとめ
国語の記述力を磨くことは、単なる受験対策を超えた意義があります。設問を丁寧に読み、素材文から根拠を見つけて論理的に整理する練習は、生涯にわたる思考力の基盤となります。一つひとつの手順を意識し、親子で取り組むことで成績だけでなく人間力も向上させられるでしょう。
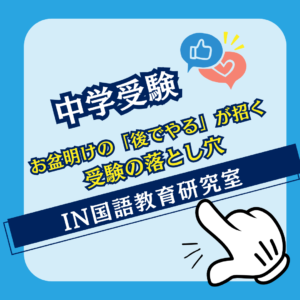
テスト対策に追われていませんか?
成績を伸ばす鍵は、テスト後の振り返りです。IN国語教育研究室では、お子様に合った指導と保護者向け相談で、学習効率の向上をサポートしています。
⏳ 9月スタートのご相談締切:8月20日まで。