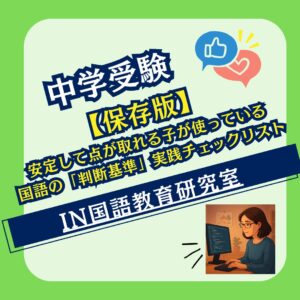「鼻白む」という表現に出会ったら? 使い方と意味を徹底解説

新聞記事で、「鼻白む」という表現に触れました。最近ではあまりお目にかからない言葉ですが、「古文や小説で何回か読んだなあ。」その都度ちょっと心にひっかかりながら読み進めていた記憶がよみがえってので、解釈の仕方について書いていきます。文章読解時の素材文の読み進める時の参考になれば幸いです。
What if you come across the expression ‘hanabirumu’? A thorough explanation of its usage and meaning.
大別すると意味は二つ
「鼻白む」とは、相手の言動や状況に気後れしたり、興ざめする状況を表す言葉です。この表現の背景には、微妙な感情や心の動きが潜んでいます。文章読解でこの言葉に出会った際のヒントを見ていきましょう。
内向きな争いが繰り返される光景に辟易し、鼻白む。
朝日新聞 天声人語より
「辟易し、鼻白む」という表現がマイナスの言葉を重ねています。これを素材として理解すること。そして、入試問題では記述問題において、心情や状況を言葉を重ねて表現する技術にも応用できます。中学受験では「鼻」が空欄補充になっていたらちょっと難しい問題になるだろうなと思います。
気後れする
気持ちが内向きに引ける状況。前後の文脈で、「ついていけない」や「迷う」等にも関連付けられそうです。
たとえば、新しい職場で専門用語が飛び交い、自分がついていけないと感じた時、「鼻白む」という感情が生まれます。 この状況では、自信の欠如や居心地の悪さが「鼻白む」のニュアンスにぴったり合います。顔つきや、内面の様子かどうかは前後の文脈から判断してみるといいでしょう。
例:A「そろそろ時間なのでお話はここまでで終わりにしましょう。お帰りください。」
B はAから一方的に話を遮られ、鼻白んだらしく、ちょっと言葉に詰まった。
「鼻白んだらしく」とあるので、内面の様子で気後れしたと判断できます。
興ざめる
興味や意欲の盛り上がりを失うこと。前後の文脈で、「反感を抱く」などにも関連付けられそうです。
好きな小説の展開が突然ありきたりな方向に進み、期待を裏切られた時、「鼻白む」という感覚を抱くことがあります。心の盛り上がりが急速に冷めた場合、このニュアンスが適切です。
例:A「ここまで命をかけて頑張ってきたが、これ以上は私の限界なので撤退する。」
「あなたがここまで周りを盛り上げて、クラス全体を巻き込んだあげくに。突然、撤退宣言するんですね。」Bは鼻白んだ表情をした。
いずれにしても、初見の場合は、マイナスのイメージとして読み進めると思いますが、現代の言葉に置き換えると、「ドン引く」などに「置換」してもよいと思います。意味を問う設問が出てきたら、それに合う解答が前後の文脈で判断できるため、設問が導いてくれます。「鼻」がポイントです。
もちろん、これ以外の使われ方も素材文にはあるでしょうから、この場合どういう意味かを問われる場合も考えられます。高校の現代文の単語参考書ではこの言葉が出ているもので判断しているので、この考え方は間違っていなかったかなと思っています。入試問題だけではなく、大学に進学すると、教育学部や文学部、一般教養の言語の学習で出会うことがあると思いますので、その世界をちょっと紹介する一例になるなと個人的に思いました。
「鼻白む」という表現は、古文(江戸時代以降)から現代の小説などで多岐に渡り使われている言葉なので、登場人物の言動=「その場の人物関係と表情や会話、動作、表情、背景など」から読み取る必要があります。テストでは時間は限られているため、さらっとマイナスのイメージとして読み進められるといいでしょう。
まとめ
「鼻白む」という表現は、日常ではあまり使われないものの、文章読解には非常に役立ちます。気後れや興ざめといった感覚を捉え、現代の言葉に置き換えることで理解が深まります。読解をスムーズにするために、言葉の背景や文脈を意識するときの一例として、素材文を読む、意味を調べる際に活用いただけると幸いです。
テストの直しの時間を十分に取れない?
お困りごとはIN国語教育研究室までご相談ください。
・子ども向け:成績向上するための授業
・保護者向け:学習相談(学習のペースメイク、志望校選定、併願組みなど)
を行っています。👇