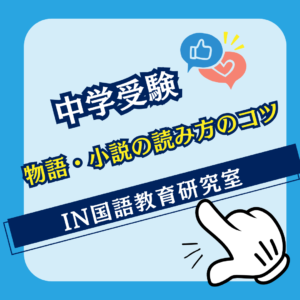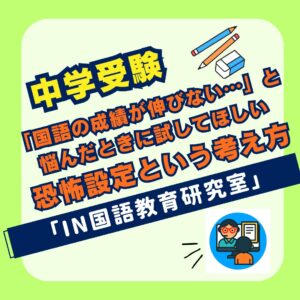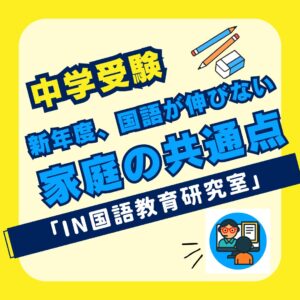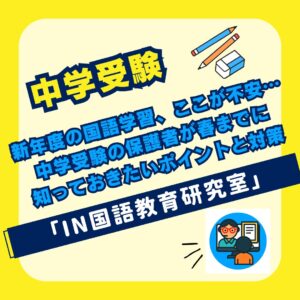物語・小説の読み方のコツ
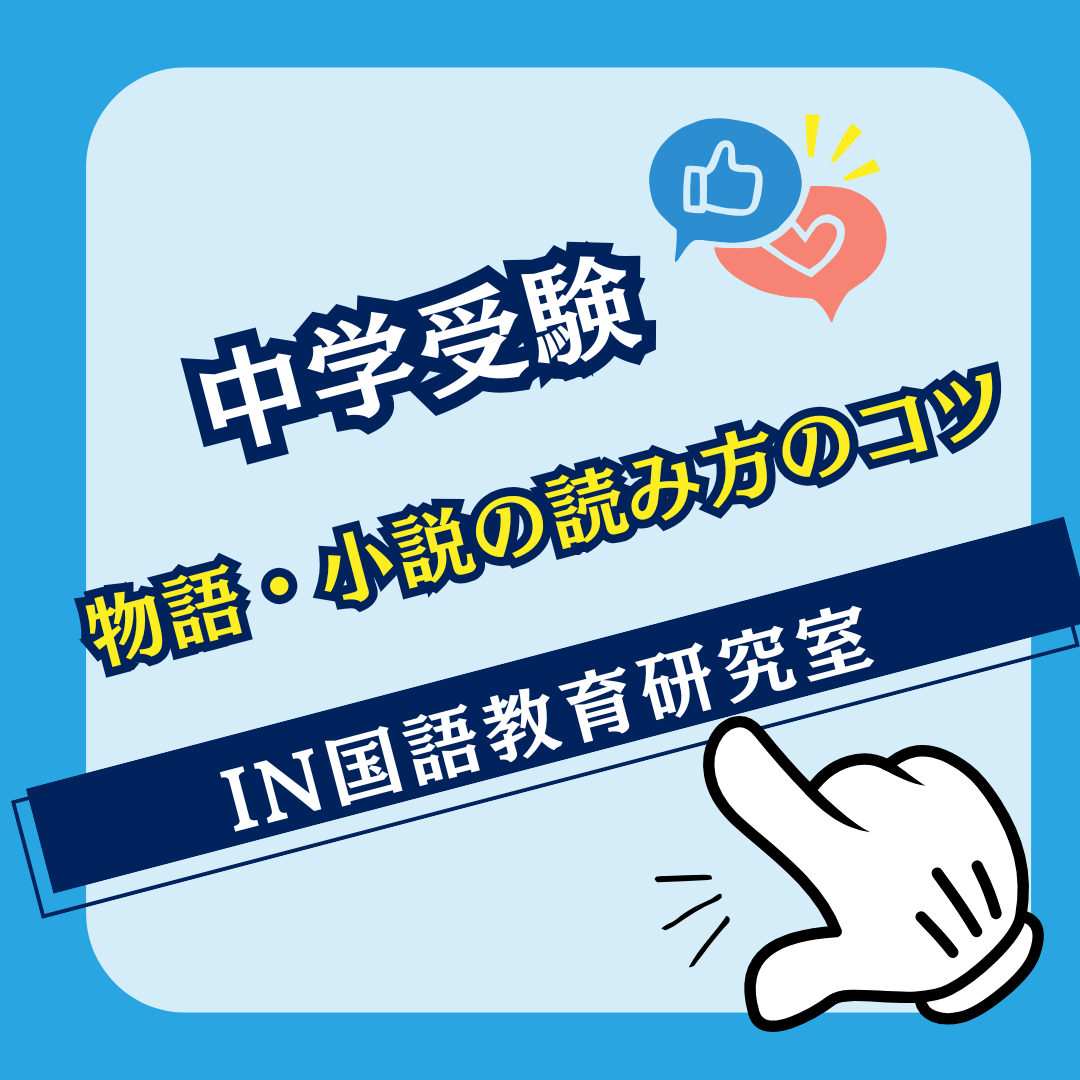
模試や過去問題、週のテストで頻繁に出題される物語・小説。中学受験の成功には、このジャンルの攻略が欠かせません。ただ読むだけではなく、深く分析し、問題作成者の意図を汲み取る力を養うことが大切です。今回は、物語・小説を読み解く際のポイントを3つご紹介します。素材文を読み、問題作成者の問いに答えられるよう「論理的思考力」さらに高めていけます。Tips for Reading Stories and Novels・
時代背景で読みやすさが変わる
物語の舞台となる時代背景を理解すると、登場人物の行動や価値観が読みやすくなります。例えば、大正時代の作品では家族や社会のしきたりが重んじられる場面が多く、その背景を把握することで人物像が明確に。おすすめの対策は、「作品内の時代設定を要約してみる」練習です。たとえば、1925年はラジオ放送です。ということは、これより前の小説は新聞、本、雑誌がメディアの主力であること。太平洋戦争まではラジオが加わること。1925年に普通選挙法、治安維持法、ラジオ放送が開始であることは受験生は知っていなければ古い小説の背景理解はできていると思います。テレビやスマートフォン、エアコンはない時代です。国語=酷語と感じる場合はまずは時代背景を丁寧に説明してあげる必要があるでしょう。最低限、最近の本屋大賞などの本との時代ギャップを感じることです。
オススメ図書
井上靖の「しろばんば」…重松清の「小学五年生」等を読了している場合は古い小説として読んでおくといいです。
Amazonはこちら→しろばんば
私の幼少時代の思い出は、みな伊豆の小さい土蔵に関連を持っている――。
おぬい婆さんとの、土蔵での生活。著者自身の少年時代を描いた自伝小説。紹介文より
古い小説は子どもには読みにくいと感じることがあるかもしれませんが、親が読んだことがある作品を紹介するのもいいです。たとえば、芥川龍之介、伊藤佐千夫、井伏鱒二、大江健三郎、川端康成、北杜夫、小泉八雲、志賀直哉、竹山道雄、太宰治、壺井栄、新見南吉、夏目漱石、三島由紀夫、宮沢賢治、椋鳩十、森鴎外などで子どもが読み易いものをお勧めします。既に読んだことがあったり、教材やテストで学んだりしているものもあると思います。文学作品の勉強にもなります。
問題作成者の問いに答える
作者の意図ではなく、出題者の問いに答える視点を持つことが重要です。例えば、「登場人物の心情について述べよ」という問いでは、物語の展開や言動に基づいた具体的な根拠が求められます。「誰が、何を、なぜ」といった質問を自分に投げかけながら回答を練習しましょう。
はじめてお会いするお子さんに質問すると、素材文の作者、問題作成者、自分の考え3つあるとすると、問題作成者に沿って答えを考えることができていない場合が多いです。他の教科にも影響しますね。
自分の感情は別にして問題に集中する
試験中は、自分の感情を物語・小説から切り離して問題のみに集中することがポイントです。感動や反感など個人的な感情を持ち込むと、答えがぶれる可能性があります。「今解いているのは試験問題である」という意識を持つことで、適切な答えを導きやすくなります。
心情描写・筆者独特の言い回し・主題に関する傾向と対策
心情描写
登場人物の感情やその変化が中心となる問題がよく出題されます。具体的には、行動や発言の背景にある心情を読み取り、その根拠を文章中から探す設問です。対策としては心情描写の対策 感情を示すキーワード(「嬉しい」「悲しい」「戸惑う」など)に注意を払いつつ、根拠となる文章を精読する練習をしましょう。例えば、「彼の驚きは、〇〇という場面で表れている」と具体的に書く練習を繰り返すと良いです。これは直接描写といい、小学3・4年生中にできるようになることです。小5以降は間接描写として登場人物の言動(会話や動作)、背景から察することも多いです。まずは直接表現を理解し、間接表現での登場人物の機微を理解することです。これは、教材やテストでの問題演習で訓練することができます。記号や、書き抜き、記述などで「どういう気持ち」「そういう気持ちになった理由」などを答えること、特に、根拠となりえる部分を素材文からみつけることで読解力が向上します。演習時に〇をもらうことだけでなく、やり直すことで直接描写か間接描写かを意識しなおすことが大切です。
演習時間とやり直し時間を含めて学習が成立することを丁寧に子どもと話し合ってみましょう。
筆者独特の言い回し
比喩表現や慣用句、作者の個性を表す語句がポイントとなります。これらを理解し、文脈からその意味を推測する力が求められます。筆者独特の言い回しの対策 文章中の比喩表現を抜き出し、その意味を文脈から読み取る訓練が効果的です。例えば「心に花が咲いた」という表現なら、どのような心情が表れているかを考え、対話形式で説明すると記憶に残りやすいです。「電車が走る」よく考えると電車は走るのでしょうか?進みますよね。擬人法が慣用化された言い回しです。こういう部分に気が付くようになると言葉に対して繊細な部分を敏感に読み取ることなどができるようになります。
主題(テーマ)
物語全体のテーマや作者が伝えたいメッセージを問う問題が頻出です。登場人物の関係性や物語の結末から主題を読み取る設問が多いです。主題の対策 物語を通じて登場人物が得た教訓や変化に注目しましょう。「主人公が何を学び取ったか?」を問う練習を重ねることで、主題を掴みやすくなります。また、物語の背景や作者の意図を調べるのも効果的です。個人的には素材文を読む前に、「題名」を読んでから読解することを勧めています。
まとめ
物語や小説は、ただ読むだけでは試験攻略にはつながりません。「時代背景を把握する」「出題者の問いに答える」「感情を切り離して問題に集中する」を実践することで、理解力と回答力が飛躍的にアップします。これらのコツを、模試や問題演習に組み込んでみましょう。記号問題の難易度も学年を経るごとに上がってきます。努力を積み重ねれば、きっと中学受験国語の成功向上が見えてきます!学びを楽しみながら、挑戦し続けてください。

国語のテストの得点が伸びない?成績をもっとあげたい?
お困りごとはIN国語教育研究室までご相談ください。
・子ども向け:成績向上するための授業
・保護者向け:学習相談(学習のペースメイク、志望校選定、併願組みなど)
を行っています。👇
にほんブログ村 ためになったらポチしてください。励みになります!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b57ec68.482857cc.3b57ec69.e9458fe8/?me_id=1213310&item_id=11295033&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3126%2F9784101063126.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)