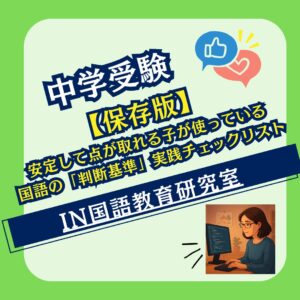【中学受験】得意を伸ばす?苦手を克服する?効果的な学習法とは?
![[Junior high school entrance exams] Improve your strengths? Overcome your weaknesses? What are effective study methods?](https://kokugokyousi-online.com/wp-content/uploads/2025/05/【中学受験】得意を伸ばす?苦手を克服する?効果的な学習法とは.jpg)
中学受験に向けた学習で「得意を伸ばすか、苦手を克服するか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。実は、学習効果を高めるためには、得意を伸ばすことが鍵になります。苦手克服の方法とあわせて、バランスよく取り入れる学習法を解説します。後半で国語の具体を書いていますので参考になれば幸いです。
[Junior high school entrance exams] Improve your strengths? Overcome your weaknesses? What are effective study methods?【初中考试】发挥你的优势?克服你的弱点?什么是有效的学习方法?
得意を伸ばす学習のメリットとは?
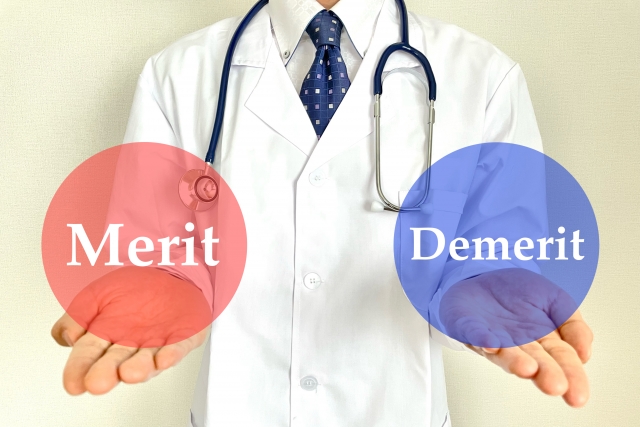
「得意な科目に力を入れると学習全体の底上げにつながる」これは、多くの学習法で実証されていることです。 得意な科目の定義は得点や偏差値を目安にするのが一般的ですが、子どもによっては、授業が好き、答えるのが好きなどでも得意の領域が広がっている場合もあります。
得意科目を伸ばすことで得られるメリットとは?
1.学習のモチベーションが上がる
得意な分野は取り組みやすく、楽しく学ぶことができます。結果として、集中力も持続しやすくなります。
2.他の科目にも好影響を与える
得意科目で身につけた「学び方・覚え方・考え方」は、他の科目にも活かせるケースが多いです。
例えば、数学の論理的思考力が理科や社会の理解力を高めることにもつながります。
3.成功体験が自信につながる
「これならできる!」という得意分野を持つことで、学習意欲が高まり、苦手な科目にも前向きになれるでしょう。
苦手な科目はどう克服する?
苦手科目を克服するには、地道ではありますが、「小さな得意を作る」ことがポイントになります。
1.得意になれる部分を見つける
苦手科目でも、特定の単元なら理解しやすいというケースがあります。 例えば英語なら、まずは簡単な基本文を繰り返し練習することで、少しずつ読める・書けるようになります。
2.小さく分けて習得する
「一度に全部を克服しよう」とすると負担が大きくなりがちです。 小さな範囲で確実に理解し、それを積み重ねることで、苦手意識を減らしていきましょう。
得意を伸ばす+苦手克服のバランスをとろう
学習では、「得意を伸ばす」ことを軸にしながら、「苦手科目の得意部分を作る」ことで、バランスよく力をつけることが重要です。 受験勉強だけでなく、進学後の学習や将来の仕事にも役立つ力を身につけましょう!
中学受験の国語に置き換えて具体的に考えてみましょう
国語は中学受験の中でも重要な科目の一つですが、「文章読解が苦手」「記述問題が書けない」と悩む受験生は多いですね。では、国語を得意に伸ばしながら、苦手部分も克服するにはどうすればよいのでしょうか?具体例を交えて解説します。

① 得意を伸ばす|好きなジャンルの文章で読解力アップ
国語が得意な子は、読書が好きだったり、文章の流れを自然と理解できたりすることが多いです。では、得意な読解力をさらに伸ばすにはどうすればよいでしょうか?
好きなジャンルの文章を読み込む
例えば、歴史が好きな場合は、歴史エッセイや伝記を読むことで「説明文の読解力」を鍛えることができます。逆に物語が好きな場合は、児童文学や小説を読み、登場人物の気持ちを考えながら読むことで「物語文の読解力」を向上させることができます。
読書について、私がよくする7つの質問です。
きっかけとして素材文選びの参考にしてください。
1.最近読んだ本の中で、特に面白かったものは何ですか?
2.この本の中で、特に印象に残っているシーンはどこですか?
3.この本を読んで何を感じましたか?どんなことを学びましたか?
4.本棚の中で、まだ読んでいないが、興味がある本はどれですか?
5.本を選ぶときに何を重視していますか?(タイトル、表紙、作者など)
6.友だちにおすすめするとしたら、どの本を勧めますか?その理由も教えてください。
7.もしこの本の続編を書くとしたら、どんな話にしますか?

子どもの創造力や論理的思考力が鍛えられる質問です。
答えが自分の中にしかないので脳内で整理して自分の言葉で伝えてくれます。
記述問題の練習は得意な文章からならば始められる
記述問題に苦手意識がある場合でも、好きなジャンルの文章なら書きやすいです。例えば、「歴史の話なら要約しやすい」「物語なら人物の気持ちが想像しやすい」といったケースがあります。まずは得意なジャンルの記述問題から始め、記述の型を身につけることで、苦手分野にも応用できるようになります。部分点だけでもよいので、得点を重ね、書けば認められるという自信をつけましょう。難関校になればなるほど、配点が高く、書ききる時間で合否に大きく影響します。
② 苦手を克服する|苦手な文章の得意な部分を見つける
苦手意識がある国語の分野でも、「得意にできる部分」が隠れていることがあります。例えば、説明文が苦手でも「図やグラフがあれば理解しやすい」、物語文が苦手でも「セリフなら意味がわかりやすい」といったケースが考えられます。
説明文は構成をつかめば読める
説明文が苦手なら、「筆者の主張」と「具体例」を意識して読むと理解しやすくなります。例えば、「〇〇という主張があり、それを説明するために△△の例が出ている」という構造に注目するだけでも、文章全体がスッキリと見えてきます。
物語文は登場人物の気持ちにフォーカスする
物語文が苦手な場合、「誰がどんな気持ちか?」に注目すると読みやすくなります。特に、「この人物の気持ちを表しているセリフや行動は?」と考えながら読むことで、問題の答えが見えてくることもあります。
③ 得意を活かしながら苦手を克服する学習法
1. 得意なジャンルの読解を強化する → 記述力も向上!
2. 説明文の「主張と具体例」、物語文の「登場人物の気持ち」に注目!
3.得意な文章を読むことで、苦手な文章への応用力がつく!
このように、得意な部分を伸ばしながら苦手分野を克服することで、国語の実力をバランスよくアップさせることができます。まずは得意な文章から始め、苦手な部分にも少しずつ挑戦していきましょう!
国語は読解力だけでなく、思考力や表現力も問われる科目です。得意を伸ばしながら苦手を克服する方法を活用し、受験本番でしっかり得点できるようにしていきましょう!テストや塾のカリキュラムに沿って学習している方がほとんどだと思いますので、カリキュラムに沿いながら、テストの復習や、手を付けていない問題など、やることを話し合って時間を決めることがポイントです。少しずつ(時間を決める)×回数が成果に結びつきます。ただし、阻害要因としては素材文の文字数や時間配分なども影響するので、問いに対する答えの考え方が導けていてたら、小さな「できた」こととして、さりげなく認めてあげることです。これも大人側の少しずつ(時間を決める)×回数です。
まとめ
1. 得意を伸ばすことで学習のモチベーションをあげる
2. 得意科目で培った学習方法は他の科目にも応用できる
3. 苦手科目は「得意になれる部分」を作ることで克服しやすい
4. 得意を活かしながら、苦手にも適切に向き合い、バランスよく学ぶ
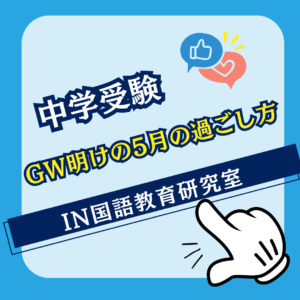
にほんブログ村 ためになったらポチしてください。励みになります!

![[Junior high school entrance exams] Improve your strengths? Overcome your weaknesses? What are effective study methods?](https://kokugokyousi-online.com/wp-content/uploads/2025/05/【中学受験】得意を伸ばす?苦手を克服する?効果的な学習法とは-300x300.jpg)