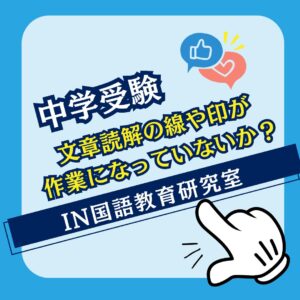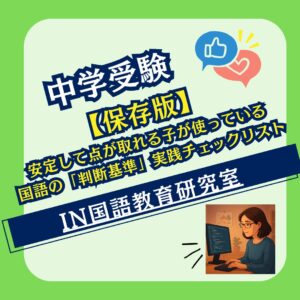文章読解の線や印が作業になっていないか?
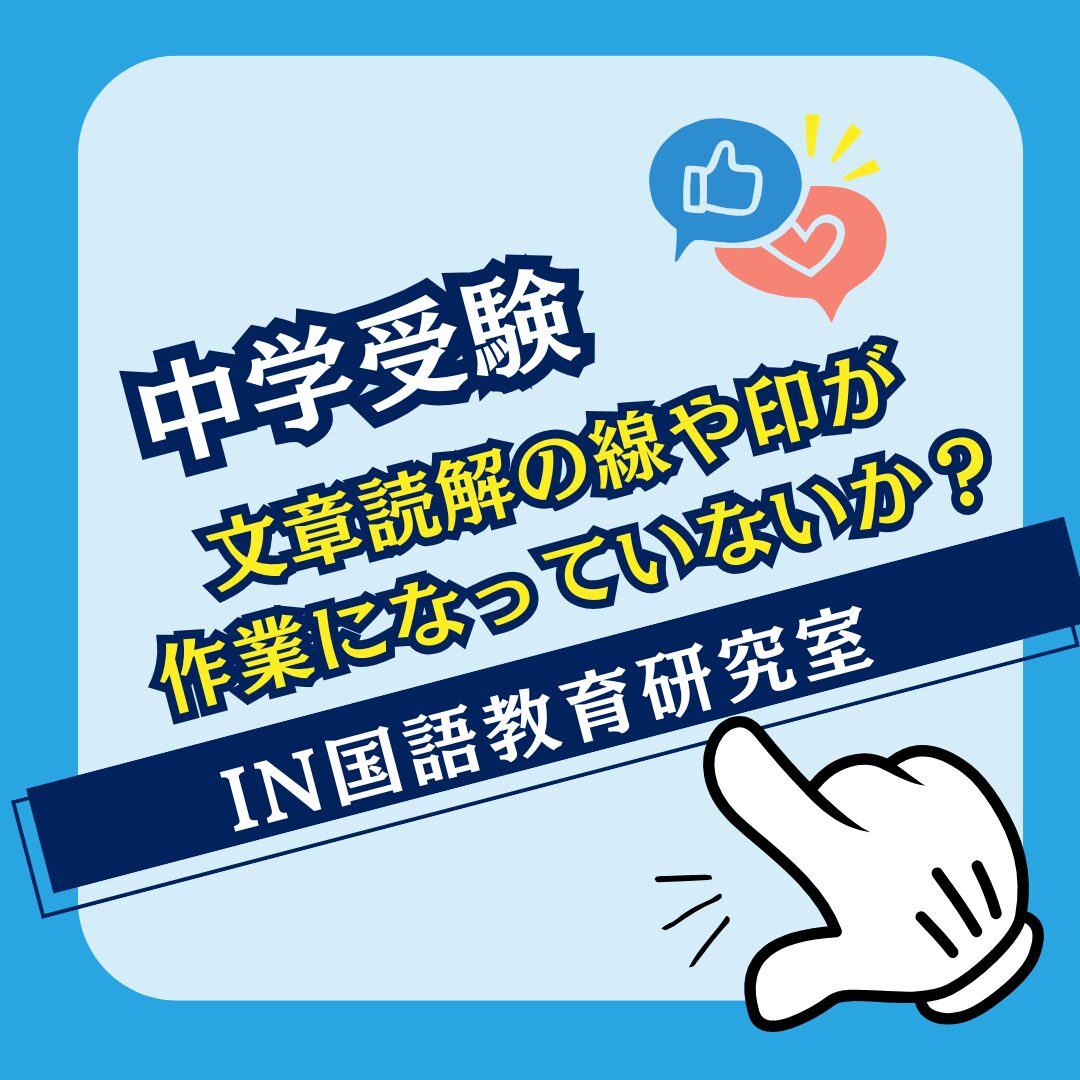
受験勉強において、文章への印や線引きがただの作業になっていませんか?大切なのは、文章を読み進めるごとに要約し、論理的思考力を鍛えることです。本記事では、効果的な印の活用法と、模試の振り返りを通じた学習の質向上について解説します。線を引くだけで満足するのではなく、本当に理解できているかを確認する方法を考えていきましょう。
Are the lines and marks in the reading comprehension process not just a chore?
阅读理解过程中的线条和标记难道不只是一件苦差事吗?
結論からいうと、大切なのは、文章を読み進めるごとに内容を要約・整理しているかどうかです。

1. 印や線引きの目的を見失わない
文章に線を引くことが目的になってしまうと、内容を正しく理解できない恐れがあります。読んだ内容を要約しながら、論理的思考力を活用して理解することが重要です。この作業は個人差があるので、一律に先生に言われたとおりにやれば読解力があがると思わないことです。線を引きまくった方が読める子ども、逆に線を引かない方が読める子どももいます。
具体例
例えば、長文読解の問題で、重要そうな部分に過剰に線を引いてしまい、結局どこが大切だったのかわからなくなることがあります。
対応策
・線を引く前に「この情報はなぜ重要か?」を考える。
・読んだ後に要約を作成し、線を引いた部分と照らし合わせてみる。
※要約は作成しなくてもよいですが、思い出す時間は必要です。
2. 模試の問題用紙と答案用紙を活用する
問題用紙や答案用紙を見直し、記憶の補助として活用することをおすすめします。時間切れになった問題を解き直し、「次は時間内に解く」という期待感を持つことが学習意欲につながります。
具体例
模試で時間切れになり、解けなかった問題をそのままにしておくと、同じ種類の問題で再び時間不足になることがあります。
対応策
・時間内に解く練習として、解き直しの際に制限時間を設ける。
・模試後の見直しで「時間が足りなかった原因」を分析し、次回の戦略を立てる。
3. 記述問題の振り返りのポイント
記述問題の採点基準は模試や採点者によって異なることがあります。複数の模試を比較し、「書けるべきところは書けているか」「得点を上げるには何をすれば良いか」を親子で冷静に分析するのも効果的です。
具体例
例えば、模試ごとに記述式の採点結果が異なり、模範解答や自分の解答それぞれに対して「この答え本当にで合っているのか?」と不安になることがあります。
対応策
・模試の採点基準にばらつきがあることを理解し、複数の採点結果を比較する。
・「採点基準が違っても安定して得点できる表現」を身につける。
まとめ
文章に印を付けたり線を引くことは有効な学習手法ですが、それに頼りすぎてしまうと本来の理解を妨げることがあります。読む力を鍛え、興味を持って文章と向き合うことが大切です。また、模試の活用や記述問題の振り返りを通じて、学習の質を向上させることが論理的思考力が育まれ、問題作成者の意図を読み、自分の言葉で説明することができるようになります。学年が上がるにつれて、文章の難易度や設問の問われ方も高度になるので、成績に直結しているか不安になる場合もあると思いますが、漢字・語句と同時に積み重ねていれば、最高難易度以外のテストでは自分なりに満足がいくようになってきます。たとえば、国語の最高難易度は個人的には筑波大附属駒場中です。

にほんブログ村