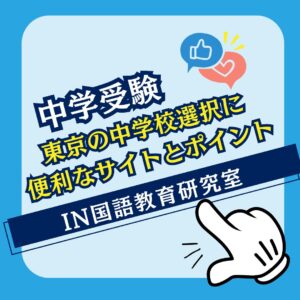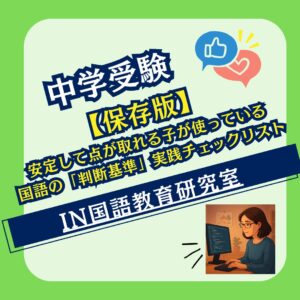東京の中学校選択に便利なサイトとポイント
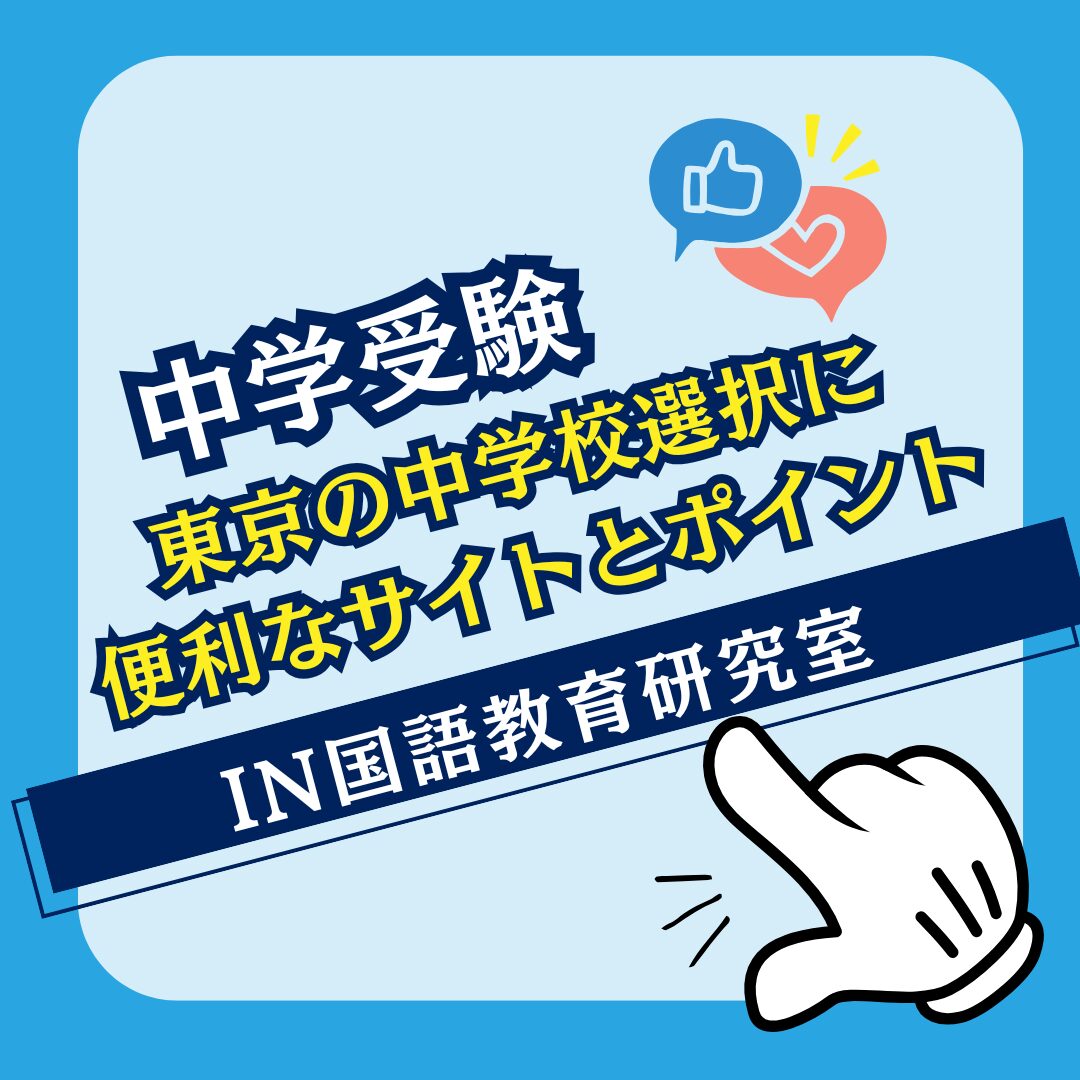
学校選びの重要な要素のひとつは、子どもの成長に適した環境かどうかを見極めることです。私立中学の学校説明会では、授業や部活動の様子、在校生の発表を通じて、好奇心・柔軟性・責任感・創造力・自己肯定感などの力を育めるかを感じ取ることができます。説明会では、教育方針だけでなく、学校生活全般の雰囲気を知ることができるため、子どもが楽しく学べる場かどうかを判断する貴重な機会となります。ぜひ積極的に参加し、子どもに最適な学びの環境を見つけましょう。
A convenient site for choosing middle and high schools in Tokyo.东京的中学和高中选择便利网站
今回は東京私学ドットコム中学校版をご紹介します。(高校もあります)
・マップから探す
・イベントで探す
・学校一覧から探す
・PR動画から探す
どの切り口でもよいので一度覗いてみてはいかがでしょうか。
ホームページは→コチラ
特に、お勧めなのは「部活動」の有無です。
部活動…中学のみ、中高合同、中高別、高校のみ等が一覧であるので便利です。
詳しくは→東京都内私立中学校・高等学校クラブ一覧
【イベントのお知らせ 】
Discover私立一貫教育2025東京私立中学合同相談会
開催日/2025年5月18日(日)
場所/東京国際フォーラム地下2階ホールE
開催時間/10時~17時30分
事前予約申し込みは4/18より開始です→→相談会HP・申し込みはコチラ
合同相談会での質問ポイント
保護者が質問すべきこと
1.学習カリキュラムの特徴
学校の教育方針や、授業の進め方、使用する教材について詳しく聞くことで、子どもに合った環境かどうか判断しやすくなります。
2.進学実績とサポート体制
卒業生の進学先や、学校独自の進学指導、塾との連携などを確認することで、受験時の支援体制を知ることができます。
3.学校生活(部活動・行事・校風)
子どもの性格や興味に合った部活動があるか、学校行事の特徴、校風について聞くことで、子どもが楽しく通えるかの判断材料になります。
4.生徒の生活習慣・校則
持ち物の制限、スマートフォンの使用ルール、服装規定などを確認することで、家庭の教育方針と合っているかを考えられます。
5.通学のしやすさと安全面
通学経路の安全性や通学時間、バス・電車の利用状況を確認し、無理なく通えるかどうかをチェックすることが重要です。
子どもが質問すべきこと
1.授業の進め方や雰囲気
授業のスピードや先生の教え方について聞くことで、自分が学びやすい環境かどうかを知ることができます。
2.部活動の種類や活動頻度
部活がどれくらい活発なのか、初心者でも参加しやすいかなどを確認し、充実した学校生活を送れるか検討できます。
3.学校の雰囲気や生徒同士の関係
先輩や先生との距離感、クラスの雰囲気について聞くことで、自分が楽しく通えるかイメージしやすくなります。
4.昼食(給食・お弁当)の選択肢
学校の食事環境を知ることで、自分の希望に合うかどうか判断できます。学食があるか、お弁当が必要かなども重要なポイントです。
5.宿題の量や自主学習の支援
宿題の負担や、先生がどの程度フォローしてくれるかを聞くことで、学習と遊びのバランスを考えやすくなります。

相談会では、ただ情報を集めるだけでなく、実際に先生や、もしいれば「在校生」とも話しをすることで学校の雰囲気を感じ取ることも大切です。ぜひ積極的に質問して、納得のいく学校選びをしてください!
ここだけの話
学校の先生は当然、広報活動として会場にやってきます。よりよい学習者に入学してほしいということ。受験生を集めることを念頭に開催しています。とてもたいへんなお仕事ですので、労ってあげてください。その姿勢を子どももみています。親の行から他者との距離感とその詰め方を子どもも学ぶことになります。
もし、合同説明会に行きピンとこない場合は我が子がレジリエンス(逆境に負けない心)をつけられそうかどうかを5段階評価してみましょう。
具体的には以下のいずれかをより多く感じられるかです3を基準に5段階をつけてみるといいです。HPで見た時、合同説明会にいったとき、学校見学に行ったときそれぞれで変化があると思います。
・好奇心が育めそう
・責任感が育めそう
・柔軟性が育めそう
・創造力が育めそう
・洞察力が育めそう
・忍耐力が育めそう
・自己肯定感が高まりそう
・楽観的に未来を信じられそう
・感情のコントロールが育ちそう
私がもし学校の担当だったら、親子のどちらが先に質問してくるかをまず見ます。主体者がどちらかという意味で子どもが先に質問する場合は場慣れしているか、積極性があるといったん判断します。
中学受験の国語の学習について
どんな対策をしておくとよいか聞いてみましょう。小学生の時に読んでおくとよい本などを聞いてみてもいいです。ただし、受付した担当が国語の担当でない場合もあるので「過去問の入試傾向」に置き換えて聞くのでもいいです。
学校説明会につながる例
① 在校生による学校紹介やプレゼンテーションを聞くとき
学校の生徒自身が、学校の魅力や取り組みについてプレゼンする場面では、創造力や洞察力を感じることができます。生徒たちが自分の言葉で学校の特徴を説明したり、ユニークな視点で学校生活を語る様子を見ると、「この学校は好奇心や柔軟性を育てる環境なのかもしれない」と感じるでしょう。
② 授業の様子を見学するとき
学校説明会では実際の授業風景を見られる場合があります。先生が生徒の発言を尊重しながら対話的に授業を進めている様子や、生徒同士が意見を交わしながら課題に取り組んでいる場面では、責任感や忍耐力、感情のコントロールを育む環境があると感じるかもしれません。
③ 学校行事や部活動について説明を受けるとき
説明会では、学校の行事や部活動の取り組みについて話があることが多いです。例えば、文化祭や運動会で生徒が主体的に企画運営する様子を知ると、自己肯定感や責任感の大切さが伝わってきます。また、部活動で仲間と協力しながら成長していく話を聞くと、忍耐力や柔軟性が育つ環境があるのではないかと感じるでしょう。
Q&A
Q.学校見学に行った方がいいかどうか
A.可能であれば足を運びましょう。
勉強で忙しく、なかなか時間がとれない背景があります。可能であれば、説明会やイベントに親子で参加はしたいところですが、難しい場合は校門までは行きましょう。さらに、もし可能であれば、登下校中や部活動の先輩に一言なんでもいいので質問してみてください。最後に先輩から「受験頑張ってね」「待ってるよ!」と言ってくれる先輩がいると子どものやる気もアップします。(少なからず実際にあります)
まとめ
学校説明会では、単なる情報収集にとどまらず、実際に学校の雰囲気を感じ取ることが重要です。在校生の発表や授業見学を通じて、責任感や自己肯定感が育つ環境かを確認し、部活動の取り組みから忍耐力や柔軟性を学べるかを見極めましょう。また、先生や生徒との交流を通じて、楽観的に未来を信じられる学校かどうかも感じることができます。学校選びは子どもの成長に大きな影響を与えるため、ぜひ説明会で多くのことを学び、最適な学びの場を探してください。
にほんブログ村 ためになったらポチしてください。励みになります!