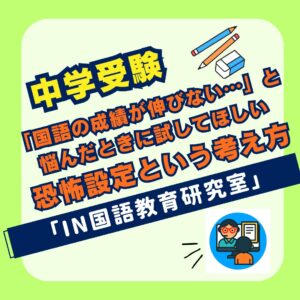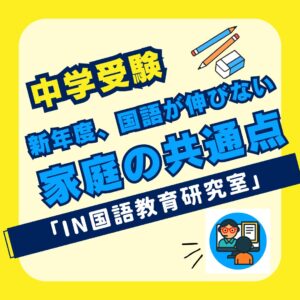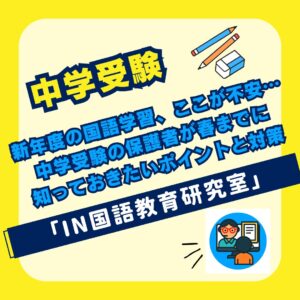2025年渋谷教育学園幕張中学校1次入試問題の考察

渋谷教育学園幕張中学校は千葉県共学の私立最難関中の一つです。首都圏から多くの受験生が集まってきます。「自調自考」を教育目標とし、自らの手で調べ、自らの頭で考えるという”調と考”が建学の精神となっています。一人ひとりの生徒が思いやりのある心・向上心・主体性にあふれる個性豊かな人間となることを目指しています。50分で大問2題。全21問の構成。大問1は随筆(エッセイ)、大問2は小説。記述問題は4題。長文記述もあるため、全問書き切り、倍率を乗り越えるヒントになれば幸いです。
Consideration of the first entrance examination questions for Shibuya Educational Academy Makuhari Junior High School in 2025.2025年涩谷教育学院幕张中学第一次入学考试问题的考察。
■実質倍率は2.5倍
試験について入試データ→渋谷教育学園幕張中入試結果
渋谷教育学園幕張中学校の2025年第1次の実質倍率は2.5倍でした。国語の受験者平均点は53点、合格者平均点は61点。最高点が88点なので、最高レベルの生徒ができる問題をミスなく取り+記述で得点を重ねる勝負することです。
目次自調自考の力を伸ばす
本校でもっとも大切にしている目標で、様々な活動の指針となっています。「自らの手で調べ、自らの頭で考える」何事にもあきらめることなく、積極的に取り組むことの出来る人間の育成を目指します。
Developing the Power of Self-Thinking and Self-Awareness
This is the principal objective of Makuhari Junior and Senior High School for guiding students in a diverse range of activities. In all things, we advise students “to investigate with their own hands, think with their own minds.” We cultivate in students the ability and confi dence to engage actively with the world, never giving up in the face of adversity but seeing each challenge through to the end.
倫理感を正しく育てる
倫理とは人が常に守るべき道です。高い倫理観は様々な価値観を持つ多様な人々と生活するグローバル時代には人として信頼される基本的条件となります。何が正しく、何が善であるかを判断する力を身につける「感性」の成長を図ります。
An Ethically Grounded Education
Ethics are principles that every person must adhere to. In a global age, when we live among diverse groups of people with widely varying values, the attainment of high ethical and moral standards is essential to earn the trust of others.We assist students in growing as ethically sensitive individuals who can discern what is right and proper.
国際人としての資質を養う
国際人としての意識を持つことはこれからの世界を生きていく為には不可欠と言えるでしょう。本校には多様な海外留学プログラムや、帰国生・留学生の受け入れ、海外との文化交流、海外大学進学へのサポートなど、幅広い教養を身につける環境があります。
Fostering the Right Qualities to Be an Internationally-Minded Individual
We are entering a period when every successful person needs to become an internationally-minded individual. At Makuhari Junior and Senior High School, we undertake a wide range of initiatives to cultivate this international outlook. For example, we participate in a wide range of overseas study programs, actively recruit foreign exchange students and Japanese students returning from abroad, engage in cultural exchange with other countries, and regions around the world, and support students in applying to universities overseas.
引用:渋谷教育学園渋谷HPより
日本文と英文を用いて掲載していることから、グローバル教育に力を入れていることが伺えます。
■大問1:随筆文(哲学)
随筆「水中の哲学者たち」
永井玲衣著 晶文社 2021年9月に発行された文章です。
「もっと普遍的で、美しくて、圧倒的な何か」それを追いかけ、海の中での潜水のごとく、ひとつのテーマについて皆が深く考える哲学対話。若き哲学研究者にして、哲学対話のファシリテーターによる、哲学のおもしろさ、不思議さ、世界のわからなさを伝える哲学エッセイ。当たり前のものだった世界が当たり前でなくなる瞬間。そこには哲学の場が立ち上がっている! さあ、あなたも哲学の海へダイブ!
晶文社HP紹介文より
この文書は、哲学や人間の経験についての考察を含む、教育的な入試問題の一部です。この文章のテーマは、日常の断片や個人的な体験を通じて哲学的な対話を行うことの重要性です。 普段は目に見えない生活の営みや感情を言語化し、共有することの意義が強調されています。
Amazonはこちら→水中の哲学者たち [ 永井玲衣 ]
出題は11問、14解答 文字数は約5200文字
51×17×6で概算しています。
前半の小問は漢字・知識・語句。特に、文学について、特に問2についてはかなり突っ込んだ問題が出題されています。割り切って次に進むのがよいですね。又吉直樹氏が太宰治が好きなことを知っていれば即答できますが、アンテナを貼っていないと適応は難しいと思います。東京の三鷹の禅林寺に太宰治と森鴎外のお墓があることを知っていれば解けたかもしれません。また、菊池寛、宮沢賢治、三島由紀夫、志賀直哉、太宰治から又吉氏が尊敬する太宰治をを選ぶので、文面に川端康成に手紙を書いたということ、すなわち、芥川賞の選考委員の川端康成が、太宰の私生活の問題を理由に芥川賞受賞を邪魔したと考えた抗議だったことを知っていたか、そう書きそうな人を連想できたかということです。また、問3では自由律俳句についての問いがあります。詩歌についての基礎知識を備えたうえで解かなければならないので、詩歌を軽んじている場合は得点は取れないでしょう。しかし、設問をよく読めば、定型句を選べばできる問題ですのでこれはできないといけません。表面的に設問を読んでいると致命的なミスをします。
問10は必須記述。「恐れるとはどういうことか」の説明。恐れと言葉の関係を説明する訓練ができているかがポイントです。問11は哲学についての文章であることから、3択にはすぐできるか。あとは「特徴」を文章読了後に問題作成者がどう捉えたかをふまえ、選ぶことです。キーワードから身近なことや日常生活から2択にまでできればあとは普段の仕上げです。強調や比較、例などを考察できることです。
■大問2:小説 「球のゆくえ」 安岡章太郎著
・講談社文芸文庫 「走れトマホーク」 の「球のゆくえ」1988年06月06日頃
・新潮文庫 日本文学100年の名作 第6巻 1964-1973 ベトナム姐ちゃん
「球のゆくえ」 安岡章太郎著 2015/1/28に発行された短編小説集です。
当時の時代背景を思いながら読めたか。主人公は植民地で生活していたことでいわゆる「いい暮らし」をしていたことが想像できます。(弘前高校が今の弘前大学であることは認識したうえで読めるとなおいいです。)都会と田舎、標準語と方言、勉強のできる子とできない子、スポーツのできること苦手な子。対立的に書かれています。ナイーブな少年の疎外感を抱きながら読んだ子どもが多かったと思います。あとは問題が導いてくれるかもしれません。
出題は1問、15解答 文字数は約6000文字
57×18×6で概算しています。
前半問3までは漢字、語句の知識問題、問4で「どういう気持ち」かという記述。そわそわした、落ち着かない気持ちを対比表現で組み立てられれば時間をかけずに書き切れたのではないでしょうか。問56は心情を選ぶ5択問題。時間をかけずに対立的に書かれていることが念頭にあれば解ける問題です。問7は理由が問われており、「ショック」であることはわかるが、何がショックだったのかを読み取れているか。目の前のものとは何かを「置換」する必要があります。問56の続きとしてとらえながら解いた子どもも多かったと思います。問8は「なぜ恥ずかしくなったのか」を記述する問題。「文章全体の内容をふまえて」と条件があるため、対比と因果を組み合わせて答えられれば解き切れます。普段から発展や最難関レベルで練習してあれば、時代背景の把握、上から目線、対比表現から主要部分と補助部分を組み立てて記述する。落ち着いて書き切って欲しい問題。最後に定番の文学作品問題。ジャンルや作者、作品名から、消去しながら解くと時間を取られずに済みます。社会の歴史で学んでいるものもあるので、解きやすいものもあったと思います。
まとめ
漢字語句から詩歌や文学まで幅広い知識や、質の高い、文章題を50分でしっかり解き切ることがポイントです。特に文学作品は、できるものとできないものを割り切って引きずらないことです。可能であれば、文学作品の対策としては便覧などを用いて、明治から昭和まで作者や作品名をグループ分けしておくとよいでしょう。記述を書き切ることができれば手ごたえを感じられるはずです。
記述力は一長一短には身につきません
記述力とは、文章を的確に読み取って整理し、問題作成者の問いに理解したことを表現する能力です。このスキルは、短期間で急激に向上するものではなく、日々の地道な努力と適切な訓練が求められます。
- 読解力が基盤
記述力を高めるためには、読解力が不可欠です。文章を正確に理解できなければ、その要点を押さえた記述が困難になります。 - 論理的思考力が必要
情報を整理し、論理的に文章を組み立てる能力が求められます。このスキルを身につけるには繰り返しの練習が必要です。 - 表現力の向上
適切な言葉や文法を使い、自分の考えを正確に伝える表現力も重要な要素です。これもまた継続した学習によって育まれます。
対策
- 日々の読書習慣
本や新聞を読むことで、語彙力や読解力が向上します。また、読んだ内容を簡単にまとめる練習を行うと効果的です。国語の問題文を読むこともい同じです。 - 過去問や模擬問題の演習
実際の中学受験の問題を使い、記述の練習を積み重ねることが重要です。定期的に時間を設けて解き、回答の質を高めていきます。 - プロによる添削と指導
演習した記述問題を、国語指導に精通したプロの先生や家庭教師に添削してもらいましょう。プロからの具体的なフィードバックを受けることで、自分の弱点を発見し、効果的に改善できます。 - 文章の要約練習
新聞記事や短い文章を読んで、それを自分の言葉で要約する練習を継続的に行うことで、要点を押さえた記述が可能になります。 - アウトプットを増やす
作文や感想文を書くなどの機会を増やし、それを他人に読んでもらいフィードバックを受け取る習慣を身につけます。どんな話だったか、どんな設問だったかを話し合うだけでも効果はあります。
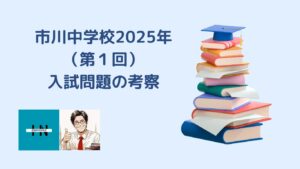
にほんブログ村 ためになったらポチしてください。励みになります!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f4620db.881380ff.3f4620dc.3f2f0e63/?me_id=1220950&item_id=15549412&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_1554%2Fneobk-2661317.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f6047ac.d7d30f28.3f6047ad.af79f7d9/?me_id=1278256&item_id=16044819&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F0365%2F2000004820365.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)