中学受験親子の疑問「塾に通い始めるのは何年生から?」

かれこれ指導歴30年以上経ちますが、永遠に変わらないだろうと思われる疑問や時代とともに考えていかなくてはいけない疑問など、経験を踏まえて振り返ります。子を持つ親の心がちょっとでも軽くなれれば幸いです。

中学受験の塾に通うために、就学前から小学6年生まで様々なタイミングがあります。早すぎないか?遅すぎないか?と不安になると思います。習い事の整理も含めていつごろから準備を始めるとよいでしょうか。「小さいうちから塾通いは大変だでかわいそう。」また、「子どものうちは遊ぶことが大切だ」という方もいるでしょう。しかし、子どもにとっては塾や受験勉強は学校とは違う先生や友達との出会いや刺激、競争(塾や担当により特色はあります)により、楽しんだり、心が強くなっていくものです。ご家庭の方針や子どものやる気によって、開始時期を悩んでいるようでしたら、小学校3年生の2月からスタートさせることを親として決めるといいです。
1.就学前
先手必勝という考え方。幼児教室に通っている場合はゆくゆくは中学受験を意識して学ばせている家庭も多いと思います。習い事として学ぶことが楽しい感覚ならばよいと思います。そうでない場合は、習い事や身近な友達とのふれあい、家族との時間を大切にする時期です。
2.小学校低学年
博物館や科家館に行ったり、自然に親しむ機会を積極的に作る時期です。家族の思い出にもなります。受験勉強が始まると、なかなか出かけるのも大変になります。準備期間として国語や算数、英語の習い事をするご家庭は多いです。国語の学習でいうと、読書や音読の時間をたくさんとることをお勧めします。塾で学ぶ場合も家庭では音読をする習慣をつけることがポイントです。文章のどこでつっかかっているのか、設問をどう理解し答えるのかを指導してくれる塾であれば、親として助かりますが、親自身が勉強を見る必要はある時期と考えます。新小学4年生(小3の2月)開講より前に塾に慣れる目的で通わせることも検討でします。算数/国語セットの週1回通塾の塾が多いです。
3.小学校3年生の2月から
多くの中学受験(算数・国語・理科・社会の4教科受験)の塾は2月開講です。受験までのカリキュラムが組まれます。これは、2月に第一志望の入試を開催する学校が多いためです。(1月・年内もあります。)6年生の1月からは入試が始まると思ってください。週に2~3日塾に通うため、通塾や、学習が生活の一部になるかがポイントです。
4.小学校4年生の2月から
塾通いしているご家庭からみると「遅め」の受験開始です。送迎や、学童、習い事の調整で4月以降の開始になるご家庭に多いです。ただし、講習を経て、小学5年生のうちにカリキュラム不足はある程度補えます。興味がわく教科があればチャンスです。学校と違い、刺激的だと思えるようならばよいでしょう。
5.小学校5年生
私立中受験のカリキュラムは既に進んでいるため、遅めのスタートです。カリキュラムと生活のペースを優先し、未履修分野は塾の先生と相談しましょう。ペースがつかめれば、6年生の夏期講習ですべて追いつきます。絶対的に算数で苦労することは覚悟しましょう。算数は学校の算数というよりかは、算術として「別物」としておくといいです。公立中高一貫対策の塾は4年生の2月に5年生として進める塾が多いです。ただし、私立併願も含めた対策をしてくれる塾をお勧めします。公立中高一貫の場合は倍率が高いことと、初見の問題を解く適応力が必要なため、安全圏はあるようでないと思ってください。
小6.小学校6年生
かなり遅いスタートなので無理はしないことです。通塾も多くの塾が週2~4日。テストも含めるとかなりハードな状態です。塾によっては途中からは難しいと断られる場合もあります。詰め込みにも限界があるので、どうしてもという場合は算数・国語の2教科受験になりますが、相当厳しいと思い受験に臨む必要があります。ただし、公立中高一貫校受験の場合は適応できるかもしれません。公立・私立含めて指導してくれる塾がよいでしょう。個別の塾にする場合は本当に受験・受検に間に合うかを事前に確認しましょう。





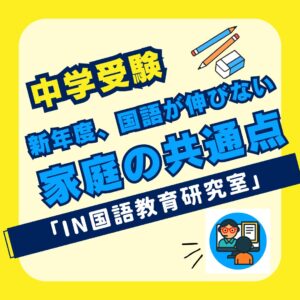
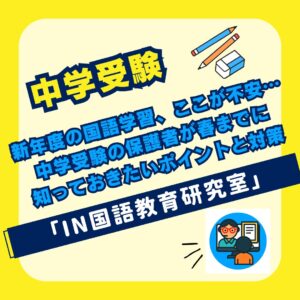





コメント