絵本「夜、空をとぶ」を読み解く(外国の作品を詩人が訳す)
.png)
前回は星新一のSF絵本の紹介と、話の流れの変化のきっかけをつかむ話でした。今回は20世紀後半のアメリカの詩人ランダル・ジャレルの詩を日本の詩人長田弘が翻訳した絵本。長田弘の詩は入試や教材で出題されることが多い。外国の絵本と思って読み解くことをお勧めします。テーマは孤独、愛情。
ランダル・ジャレル(作) モーリス・センダック(絵)長田弘(訳)
森のはずれの、おおきなヤナギの木のある家に、デイヴィッドという少年が住んでいる。「夜になると、デイヴィッドは、空をとぶことができました。昼のあいだは、とべないのです。じぶんがとべるということを思い出すこともありません」
詩人ジャレルの遺した最後の子どもの本ある本書は、センダックの「もっとも真摯でもっとも冴えわたった世界」を具現した絵本の代表作の1つでもある。
「ぼくがこの本から読みとったのは、少年の心の飢え、満たされない心の激しい痛みだった」とセンダックは語る。夜にだけ空をとべる少年は、月の光のなかに、なにを見、なにを発見したか?
森のフクロウは、少年になにを教えてくれたか?子どもも大人も一度読んだら忘れられない、詩的ミステリーにみちた絵本の傑作!
みすず書房 夜、空を飛ぶ カバー袖解説より
個人的にはちょっと難しく感じ、最後の一文にひっかかって、もう一度2度読みしました。
「詩人が贈る絵本」が副題
「夜、空をとぶ」は、子どもから大人まで、幅広い読者層に心を奪う素晴らしい絵本です。ふりがなもふられているので読み聞かせから大人まで楽しめる本です。年齢によって自分の像と重ねて読む方も多いと思います。絵本というよりは短編小説として読んでしまします。長田弘の繊細な翻訳により、原作の魅力が詩人によって見事に再現されています。外国の作品だからでしょうか、二度読みしました。
この絵本は、ひとりぼっちの少年が夜空を飛び立ち、星や月と友達になる物語です。作者は言葉だけでなく、美しいイラストを通して、読者を夢の世界へと誘います。長田弘の翻訳は、原作の詩的な雰囲気を保ちながら、日本語に自然に溶け込んでいます。彼の言葉は、読者を幻想的な世界へと連れて行き、原作の情感と深さを的確に伝えています。
また、この絵本は、孤独や夢、友情といった普遍的なテーマを通して、読者に心の琴線に触れるメッセージを届けます。そのため、子どもたちだけでなく、大人もこの絵本から新たな気づきや感動を得ることができるでしょう。
長田弘の見事な翻訳によって、原作の美しさと魅力を余すことなく伝える優れた絵本です。もしこの作品を手に取る機会があれば、ぜひ読んでみてください。
入試問題では、最後の一文が問われる
母親は、少年をじっと見妻ます。母親のように。
みすず書房 夜、空を飛ぶより
詩人の長田弘がどうしてこのような表現をしたのか。倒置法と比喩を用いていたこの文からは、母親が子どもを見守っている様子が伝わってきます。そして、「母親のように」という表現から、母親が子どもを愛情深く思いやる、温かい存在であることがわかります。つまり、母親は子どもを大切にしていて、彼女の目線が子どもに対する理解と支援を示していると解釈できます。
中学入試だけではなく、最後の一文についてどう解釈するかを記述させる問題は論理的思考力だけでなく、自身に重ねて表現するような問題として出題されたら難易度が高いですね。
長田弘の詩の特徴とお勧め本
長田弘の詩は親子で何度か詩の問題で解いたことがあると思います。
詩の特徴
詩の特徴は優しい言葉で表現されていることにつきます。読むときには静かで落ち着いた感覚で読めるのではないでしょうか。
「本を読もう。
もっと本を読もう。
もっともっと本を読もう。書かれた文字だけが本ではない。
世界は一冊の本』より引用
日の光り、星の瞬き、鳥の声、
川の音だって、本なのだ。…」
- シンプルかつ直接的な言葉の選択: 詩の言葉は非常にシンプルであり、日常的なイメージが用いられています。例えば、「日の光り、星の瞬き、鳥の声、川の音」といった具体的な要素が挙げられています。
- 身近なテーマへのアプローチ: 詩は本を読むこと以外にも、日常の中にある自然や風景が同じく本であることを強調しています。これにより、読者は日常の中にある美しさや学びを見出すことができるというメッセージが伝わります。
- 抒情性と哲学性の融合: 詩は日常の中にある美しい景色や音に対する感謝や賞賛が表現されています。同時に、この詩は「本」という概念を超えて、人生そのものが学びや成長の場であるという哲学的な側面も持っています。
- 音楽的なリズムと韻律の活用: 詩の中にはリズミカルで韻律豊かな表現が見られます。これにより、詩が朗読される際に音楽的な響きが生まれ、詩の中のメッセージがより深く響く印象を与えます。
長田弘が書いた本の紹介本「小さな本の大きな世界」
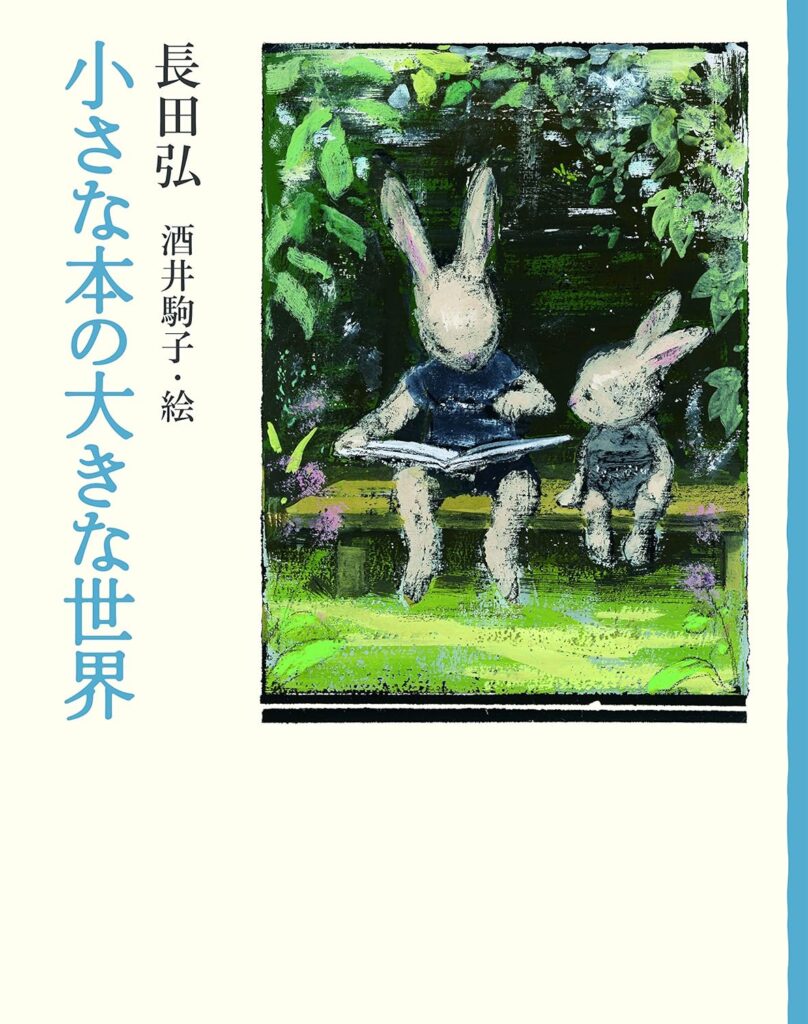
長田 弘 (著), 酒井 駒子 (イラスト)
詩人・長田弘がお気に入りの145冊が紹介されています。東京新聞などの連載をまとめたものです。1冊1冊丁寧に語られており、酒井駒子の挿絵も、紹介本にマッチしています。また、ジャンルも様々にわたり、ブックガイド的な本。たくさん読みたい本が出てきて嬉しくなります。ある意味、キケンな本です。
前回の記事はコチラ↓

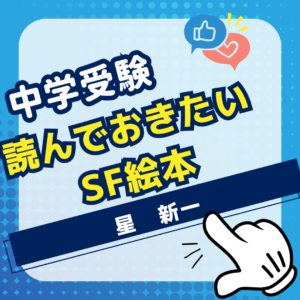
-300x300.png)






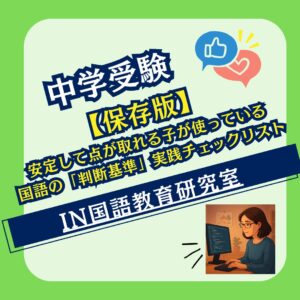

コメント