国語– tag –
-

中学受験の勉強習慣を確立!宿題の答え合わせは誰がするべきか?
「親が丸付けするのはおかしい?」と疑問を持たれることがあります。中学受験に向けての家庭学習において、宿題の答え合わせを誰がするのかは大きな課題です。低学年・高学年・中学生では考え方が異なりますが、理想の答えは「本人が丸つけをすること」。... -

習い事の意味や意義
習い事は文字通り習い事ではありますが、興味・関心・好奇心が芽生えることを心に留めておくと嬉しい瞬間があります。習うための準備、習っている間の集中、習ったあとの達成感、その後の復習はスキルアップにつながりますが、副次的な効果もあります。大... -

受験で勝つ!国語力を伸ばす個別指導の最短ルートとは?
中学受験の国語は、「読解力」「記述力」「語彙力」がカギを握ります。しかし、集団授業では一人ひとりの苦手を細かく補うことが難しく、思うように成績が伸びないことも。そこでおすすめなのが1対1の個別指導です。個別最適化されたレッスンなら、お子様... -
![[Junior high school entrance exams] Improve your strengths? Overcome your weaknesses? What are effective study methods?](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)
【中学受験】得意を伸ばす?苦手を克服する?効果的な学習法とは?
中学受験に向けた学習で「得意を伸ばすか、苦手を克服するか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。実は、学習効果を高めるためには、得意を伸ばすことが鍵になります。苦手克服の方法とあわせて、バランスよく取り入れる学習法を解説します。後半で国語... -

GW明けの5月の過ごし方―中学受験生と保護者が気をつけること
ゴールデンウィーク後の5月のスタートのポイント。連休の余韻が残る中、気持ちを切り替えて充実した毎日を過ごすためには、ちょっとした工夫が必要です。5月は気温も上がり、環境の変化や新しい生活リズムに慣れる重要な時期。ここでは、GW明けのスムーズ... -

超簡単!記述解答を素早く組み立てる方法
今回は、簡単な記述解答の組み立てにチャレンジしてみましょう! テストや試験でスムーズに答えを書くための大事なスキルのひとつですので、何かの時に、コミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか。Super easy! How to quickly construct a writt... -

灘中学校2025年2日目入試問題の考察
灘中学校の入試は全国屈指の難関とされ、特に国語は高度な思考力と表現力を問われます。2日目の国語の問題では、文章読解の深掘りや記述力を求める出題が多く見られます。この記事では、例年の出題傾向や、日々の学習で注意すべきポイントを整理し、受験... -

文章読解の線や印が作業になっていないか?
受験勉強において、文章への印や線引きがただの作業になっていませんか?大切なのは、文章を読み進めるごとに要約し、論理的思考力を鍛えることです。本記事では、効果的な印の活用法と、模試の振り返りを通じた学習の質向上について解説します。線を引く... -

中学受験国語をオンラインで学ぶメリットとは?
中学受験に向けて国語を強化したいと考える保護者向けに書いています。。国語の学習は単なる演習ではなく、読解力や記述力を鍛えることが求められます。しかし、「どうやって学習すれば効果的なのか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。What ar... -

2025年灘中学校国語試問題の考察(1日目)
灘中学校は兵庫県の男子校最難関中の一つです。関西の男子最高峰校の一つです。首都圏男子最高峰の開成高校と同様に全国から受験者が集まります。2025年は1月18日(土) 国語・理科・算数 1月19日(日) 算数・国語で実施されました。調査書も考慮されます。一...


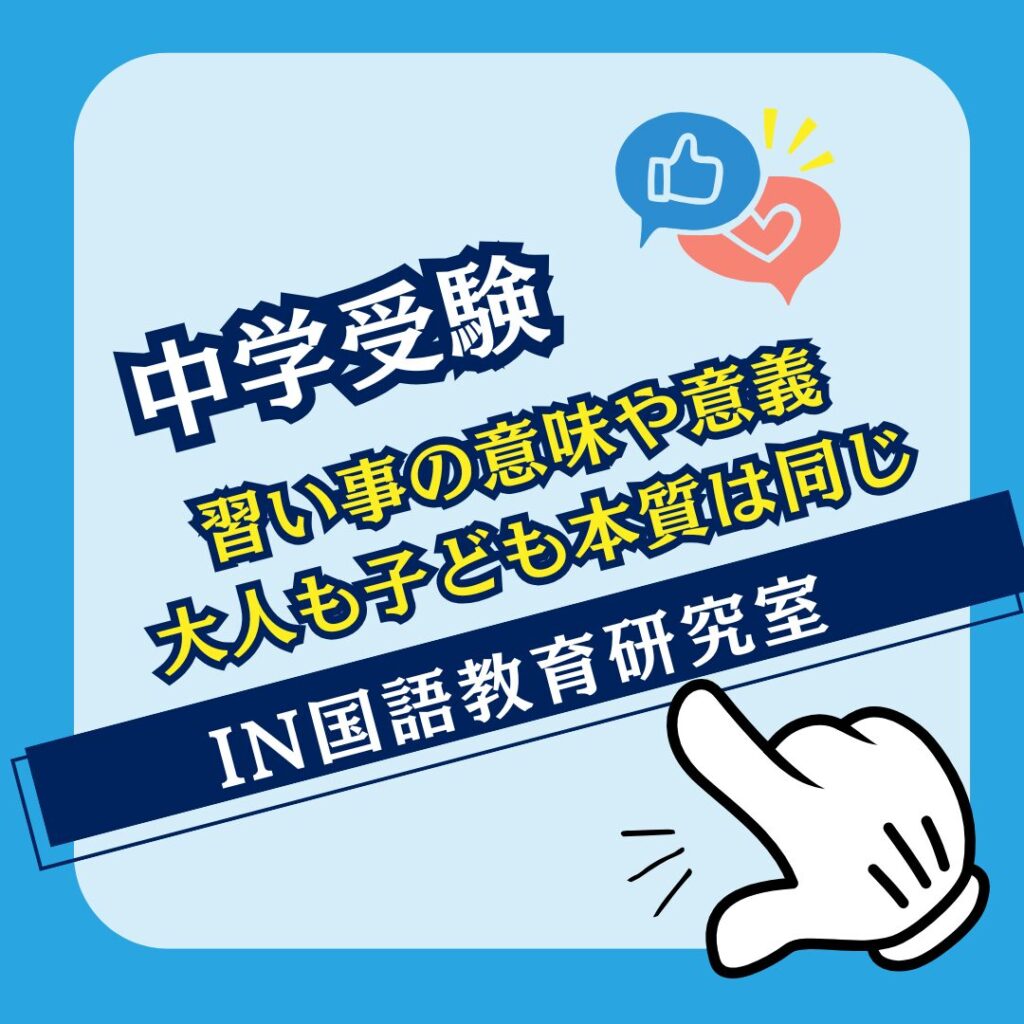

![[Junior high school entrance exams] Improve your strengths? Overcome your weaknesses? What are effective study methods?](https://kokugokyousi-online.com/wp-content/uploads/2025/05/【中学受験】得意を伸ばす?苦手を克服する?効果的な学習法とは-1024x1024.jpg)
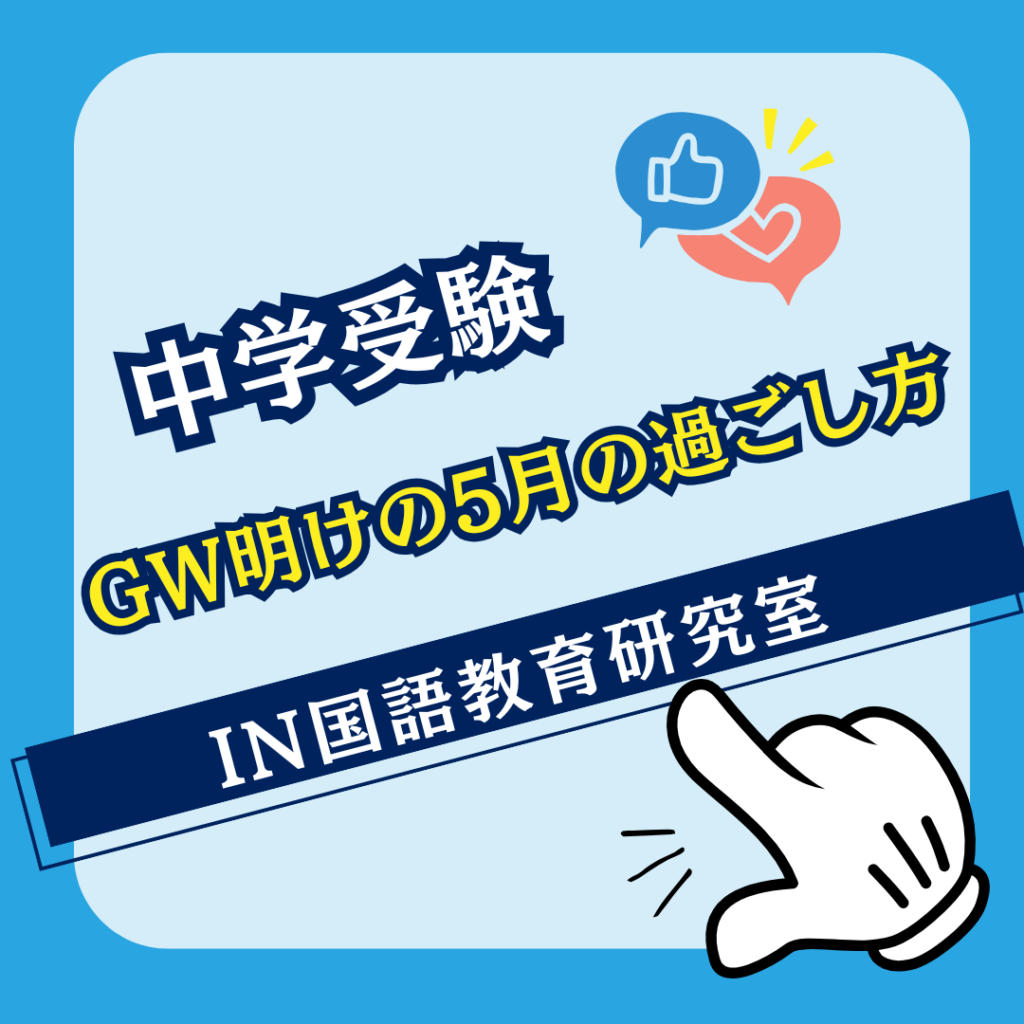


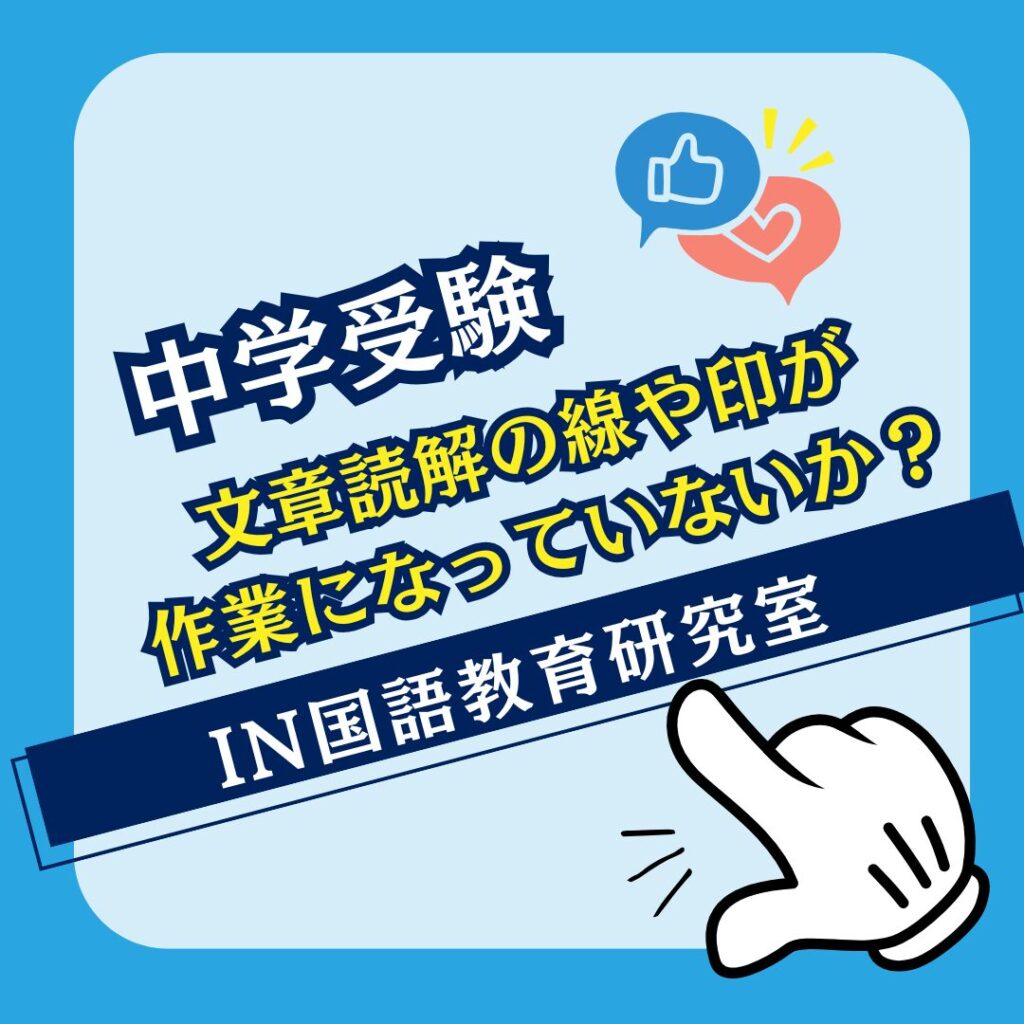

-2-1024x576.jpg)